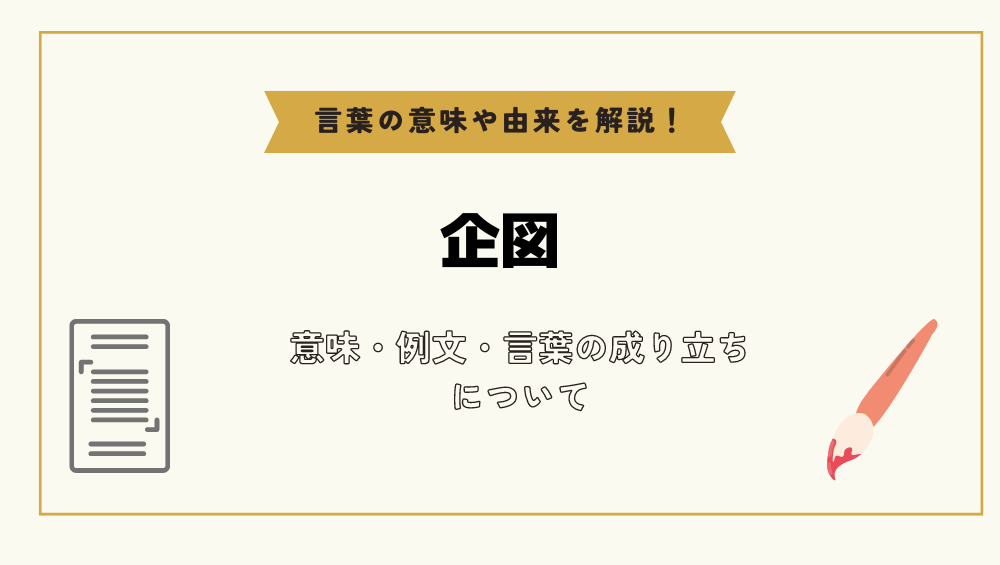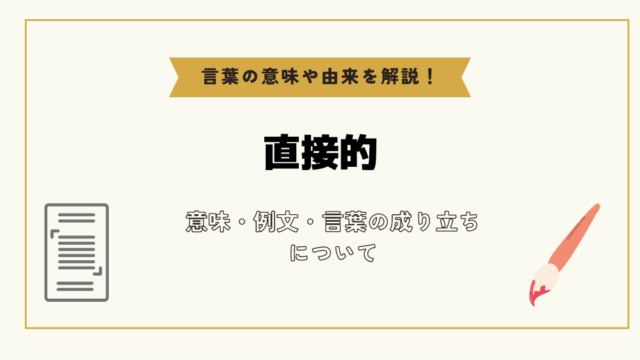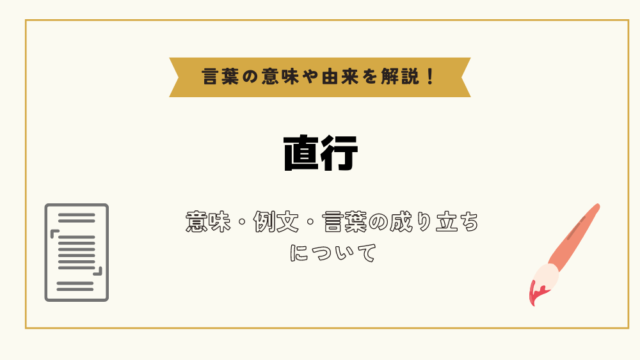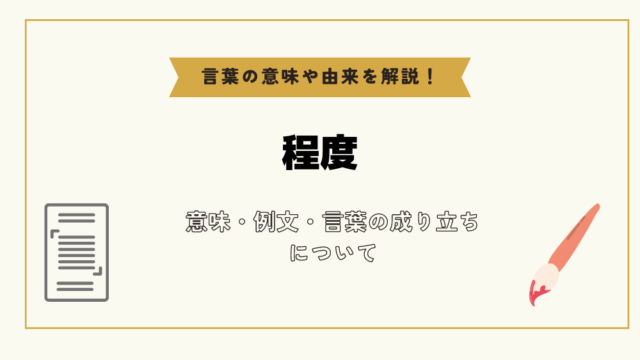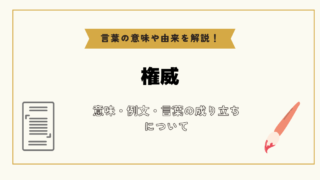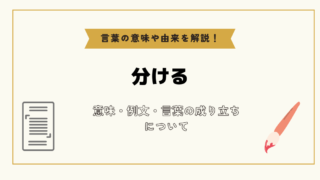「企図」という言葉の意味を解説!
「企図」は「きと」と読み、「ある目的を実現するために計画を立て、その実行をはかること」を示す二字熟語です。目的を達成するための方針や手段、時には仕組みまで含めて考えるというニュアンスをもつため、単なる思いつきや希望を表す語とは一線を画します。行政文書や法律文で用いられることも多く、ややフォーマルで硬質な語感を漂わせる点が特徴です。
計画を表す「企画」や「計画」と似ているものの、「企図」は結果として実現したいゴールを強調する言葉です。目的達成のための戦略的な構想そのものを示す場合に最も適切なのが「企図」です。そのため事業計画書や研究開発の提案書など、目的と手段をシステマチックに示したい文脈で重宝されます。
「〜を企図する」と動詞化して使うことで、「〜を計画して実行を試みる」という意味が生まれます。ビジネスシーンはもちろん、公共政策や法令においても頻繁に登場し、「新制度導入を企図する」「地域振興を企図した施策」という形で用いられます。
国語辞典では「企(くわだ)て図(はか)る」から転じたとも説明されますが、現代では二字熟語で独立語として扱うのが一般的です。文章全体に目的意識やプロフェッショナリズムを加味できる便利な語として覚えておく価値があります。
「企図」の読み方はなんと読む?
「企図」は音読みのみで「きと」と読みます。「企」は音読みで「キ」や「キツ」、「図」は「ト」や「ズ」と読まれますが、本語では「キト」が正式です。いずれの漢字も日常的に目にする文字であるため、読めそうで読めない意外性がある言葉でもあります。
「企画」は「きかく」、「企て」は「くわだて」と読むため、混同し「くわだてず」と読んでしまうケースが少なくありません。「企図」は音読みで一気に読むことが正しい読み方であり、訓読みを混在させると誤読になります。
会議資料や新聞記事で登場した場合、読み上げ担当者が「きず」と誤る例も見られます。特にスピーチやプレゼンテーションで読み上げる際は、事前に「きと」と何度か声に出して練習しておくと安心です。
覚え方としては「企てる(くわだてる)」の「企」と、設計図の「図」で「計画を立てる行為」と連想させると定着しやすくなります。「キト=計画+図面」とイメージすれば、音読みと意味を同時に記憶できるでしょう。
「企図」という言葉の使い方や例文を解説!
「企図」は主にビジネス文章や公的文書で使用され、目的語を前に置き「〜を企図する」という形が定番です。目的を端的に示したいとき、ほかの動詞を補わずとも意志と計画性を伝えられる点がメリットです。以下の例文で使い方の幅を確認してみましょう。
【例文1】新製品の海外展開を企図し、市場調査を開始した。
【例文2】地域活性化を企図した官民連携プロジェクトが始動した。
【例文3】環境負荷低減を企図する技術革新が求められている。
【例文4】学際的な協力体制を企図する研究センターが設立された。
否定形として「〜を企図しない」「企図していない」が使われる場合は、「意図していない」「故意ではない」というニュアンスになります。「犯意を企図する」といった法的表現も存在し、犯罪行為を実行する前段階の計画を示す厳密な用語として機能します。
ビジネスメールでは「本施策は○○の実現を企図しております」などと書くと、敬意と論理性が同時に伝わります。硬すぎる印象を避けたい日常会話では「計画している」「狙っている」に置き換えるのが自然です。
「企図」という言葉の成り立ちや由来について解説
「企図」は「企」と「図」の二文字から構成されます。「企」は古代漢語で「くわだてる・はかる」を意味し、上を見渡して計画する姿勢を象徴する会意文字です。「図」は「計画を図面に写し取る」ことから転じ、「はかりごと・計画」を示す形声文字と考えられます。
中国の古典『礼記』や『周礼』には、国家行事を「図る」「企つ(おきつ)」という語が散見され、計画立案を意味する文字として両者は早くから対をなしていました。この二文字を並べた「企図」は、目的と計画を同時に示す熟語として漢語圏で成立し、日本にも輸入されたとされています。
日本最古級の法典である『大宝律令』(701年)にはまだ登場しませんが、奈良時代の漢詩文に「企図」の表記が確認されており、当初は貴族階級の公文書語として用いられていました。平安期以降は漢詩文集から武家の記録にも広まり、江戸期には儒学者が政治論で多用したことで一般教養語となります。
結果として明治期の近代法整備において「企図」は条文や判例に登場し、法令用語として定着しました。この過程が現代まで続き、ビジネス・行政・学術の三領域で共通語となっています。由来的に公的・学術的色彩が強い言葉である点を理解すると、使用場面の判断がつきやすくなります。
「企図」という言葉の歴史
「企図」は奈良時代以降、主に知識人の書き言葉として使用されてきました。平安中期の漢詩文集『本朝文粋』には、策を講じて政治改革を試みる文脈で「企図」という語がすでに見出されます。また鎌倉期の武家記録にも散見され、武家政権が政策を計画する際の用語として採用されました。
江戸時代になると朱子学や陽明学が盛んになり、武士や豪商が経営論・兵法論を記す中で「企図」を多用します。明治維新後は西欧的な「プランニング」の訳語を補う形で法令や官公庁文書に定着し、近現代日本語の重要な語彙として根づきました。
第二次世界大戦後は占領政策や企業経営論において「企図」が国際的概念「strategy」「plan」を包含する語として使用され、学術論文にも連続的に引用されます。現在では経営戦略論や公共政策論のテキストに必ず登場するといえるほど一般化しました。
それでも日常会話では頻出語ではないため、歴史的に見ても一貫して「知的・公式的場面」で使われ続けていることが分かります。公文書・学術論文・ビジネス報告書という三つの舞台を中心に発達してきた歴史が「企図」の硬質な響きを形成しているのです。
「企図」の類語・同義語・言い換え表現
「企図」と近い意味を持つ語には「計画」「企画」「構想」「目論見」「戦略」「策定」「プラン」などが挙げられます。それぞれニュアンスや使用場面が微妙に異なるため、文脈に合わせて選択すると文章の説得力が高まります。
「計画」は広義で最も一般的な語であり、難易度が低く日常会話でも自然に使えます。「企画」は娯楽イベントや商品のアイデア出しを強調するときに便利です。「構想」や「戦略」は大局的な設計を示し、「目論見」はやや含みや私的な思惑を帯びる表現です。
言い換えの例文を確認しましょう。
【例文1】新製品の海外展開を企図する。
【例文2】新製品の海外展開を計画する。
【例文3】新製品の海外展開を構想する。
【例文4】新製品の海外展開を目論む。
同義語を用いる場合は、文章の堅さや読者層を考慮して適切に選択しましょう。ビジネス文書でフォーマルさを保ちつつ柔らかさを出したい場合、「計画」や「構想」に置き換えるのが無難です。
「企図」の対義語・反対語
「企図」の対義語として最も分かりやすいのは「無計画」です。行き当たりばったりで目的や手段を明示しない状態を指し、「企図」の持つ戦略性と対照的です。
また「放棄」「断念」「中止」など、途中で計画をやめる行為を示す語も対義的に用いられます。「企図」が目的達成へ向けた積極的姿勢であるのに対し、「放棄」は目的を捨てる受動的な行為として正反対の立場をとります。
短期的な偶然性を示す「偶発」や「突発」は、長期的な計画性を帯びる「企図」と相反する概念として説明しやすいでしょう。文章表現の幅を広げるためには、こうした反対語も合わせて覚えておくと便利です。
日常表現では「ぶっつけ本番」「成り行きまかせ」などの口語的フレーズが反意的なニュアンスを担います。読者に企画性の欠如を印象づけたい場合、あえてこれらの表現を対比させると効果的です。
「企図」を日常生活で活用する方法
「企図」はビジネス専門語のイメージが強いですが、日常生活に応用することで自己管理能力や説得力を高められます。まず家計管理では「一年間で○○円の貯蓄を企図する」と書き出すことで、貯蓄目的と計画を同時に意識化できます。
学習計画でも「英検準一級合格を企図し、勉強時間を週15時間に設定する」と記録すれば、目標と手段が明示され行動が継続しやすくなります。「企図」を用いることで言語化が具体性と決意を帯び、主体的に行動管理できる点が大きな利点です。
家族や友人に対しても、「来年は健康増進を企図して毎朝ジョギングを始める」と宣言すれば応援を得やすくなります。手帳やデジタルメモに「企図リスト」を作成し、目的・手段・期限を書き込むことでセルフマネジメントツールとしても機能します。
ただし日常会話で多用すると堅苦しい印象を与える可能性があります。口頭では「計画している」「狙っている」と言い換え、書き言葉としてメモや日記で活用するのがバランスの良い取り入れ方と言えるでしょう。文章化する場面を選ぶことで、「企図」の持つ力強いニュアンスを最大限に活用できます。
「企図」についてよくある誤解と正しい理解
最も多い誤解は「企図=悪だくみ」というイメージです。確かに法律用語で「犯行を企図する」と使われるためネガティブに捉えられがちですが、「企図」自体は価値中立の語であり、善悪を問わず計画そのものを示します。ポジティブな目標であっても「企図」を用いるのは適切で、むしろ本来はこちらが標準的な用例です。
次に多いのが「企図」と「企画」の混同です。「企画」はアイデアを練る段階を指し、「企図」は目的に至るための方策を定める段階を表します。「企画書」と「企図書」の書式が異なる企業もあるため、実務上の区別は厳密です。
また読み方を「きず」「くわだてず」と誤る例が後を絶ちません。文書作成時はフリガナを併記する、会議では最初に読み方を共有するなど、ミスを防ぐ工夫が望まれます。正しく理解し使いこなすことで、誤読や誤解によるコミュニケーションロスを大幅に減らせます。
最後に、計画性のないアイデアに対して「企図」という語を充てるのは誤用です。あくまでも明確な目的と手段が存在するときにのみ使用し、単なる思いつきには「発案」「試案」などを利用するのが正しい使い分けになります。
「企図」という言葉についてまとめ
- 「企図」は目的達成のために計画を立て実行を試みる行為を示す言葉。
- 読み方は音読で「きと」となり、訓読みとの混在は誤りである。
- 古代漢語由来で奈良時代から公文書語として発展し、近代法令で定着した。
- 硬質な語感を活かし、公的文書やビジネス文で使い、日常では言い換えに留意する。
「企図」はフォーマルな文脈で目的と計画を一気に表現できる便利な語です。読み方を含む基本知識を押さえ、類語や対義語との違いを理解すれば、文章に戦略性と説得力を付与できます。
歴史的背景から硬い響きを帯びるものの、日常のセルフマネジメントにも応用可能です。誤読やネガティブイメージに注意しつつ、適切な場面で上手に使いこなしてみてください。