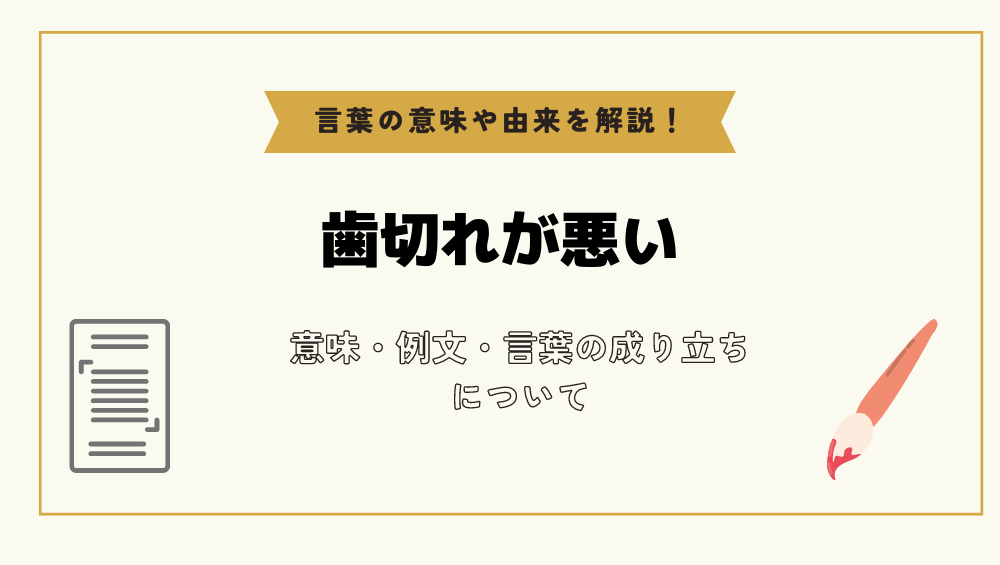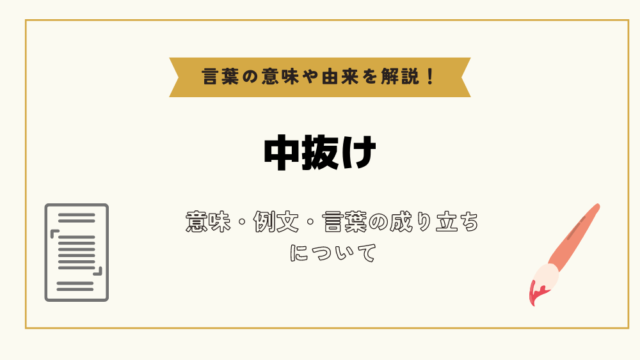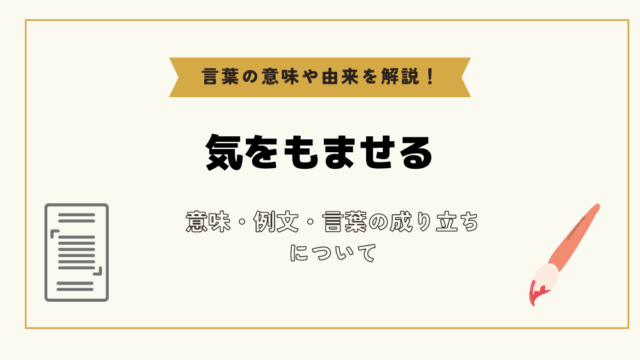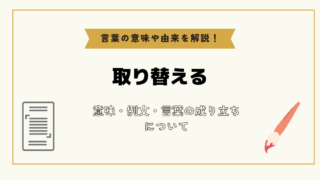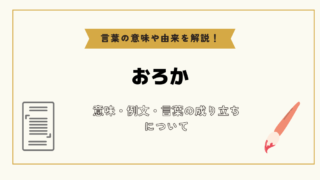Contents
「歯切れが悪い」という言葉の意味を解説!
「歯切れが悪い」とは、物事や文章がスムーズに進まず、状況がうまく進展しないことを表現した言葉です。
例えば、文章が読みにくく、伝わりにくい場合や、スピークに詰まりがちな話し方などで使われます。
つまり、物事の進行がうまくいかない状況や、円滑なコミュニケーションができない状態を指す言葉となります。
例えば、プレゼンテーションをする際に、言葉遣いや語彙が乏しく、伝えたい内容をうまくまとめられない場合、そのプレゼンテーションは「歯切れが悪い」と表現されることがあります。
「歯切れが悪い」の読み方はなんと読む?
「歯切れが悪い」は、日本語の訓読みで「はきれがわるい」と読まれます。
読み方には注意が必要で、即座に理解しにくい方もいるかもしれません。
しかし、一度覚えれば、スムーズに使えるようになるでしょう。
「歯切れが悪い」という言葉の使い方や例文を解説!
「歯切れが悪い」は、口述や文章で使用されることが一般的です。
会話の中で相手に対して物事がうまく進まない状況を伝えたい場合にも使われます。
例えば、友人との会話で、「最近仕事が忙しくて、連絡も取れないし、プライベートもうまく調整できないんだよ。
なんだか歯切れが悪い感じだ」と話すことがあります。
「歯切れが悪い」という言葉の成り立ちや由来について解説
「歯切れが悪い」という表現は、はっきりした由来はありませんが、文語表現である「歯切れの良い文章」という言葉が由来となっています。
文章や物事がスムーズに進展し、読み手や聞き手に良い印象を与えることを目指した言葉が「歯切れの良い」と表現されることから、逆に「歯切れが悪い」と言われるようになったのでしょう。
「歯切れが悪い」という言葉の歴史
「歯切れが悪い」という言葉の起源は明確には分かっていませんが、昔から存在する表現であることは間違いありません。
日本語の表現において、文章や語り口がうまく進行しない状況を「歯切れが悪い」と表現することは、歴史の中で定着してきたものと言えるでしょう。
「歯切れが悪い」という言葉についてまとめ
「歯切れが悪い」は、物事の進行がスムーズでない状況や円滑なコミュニケーションができない状態を表現する言葉です。
口述や文章で使われることが一般的であり、会話の中で相手に対してうまく進まない状況を伝える際にも利用されます。
日本語の表現として長い歴史を持ち、歯切れの良い表現とは逆に、物事の進行がうまくいかない様子を示す言葉として定着しています。