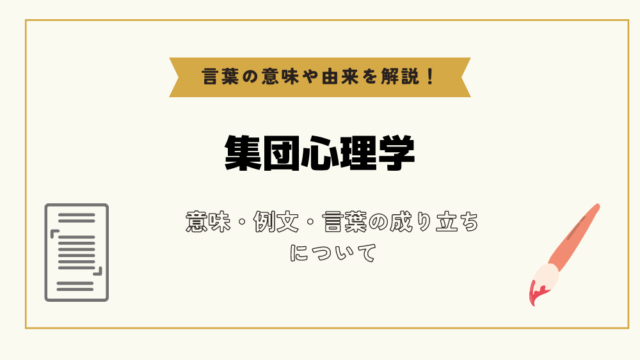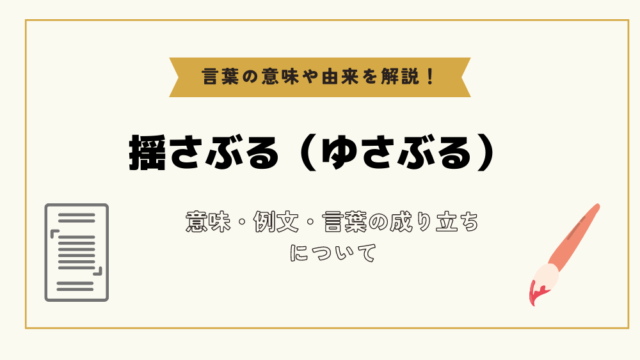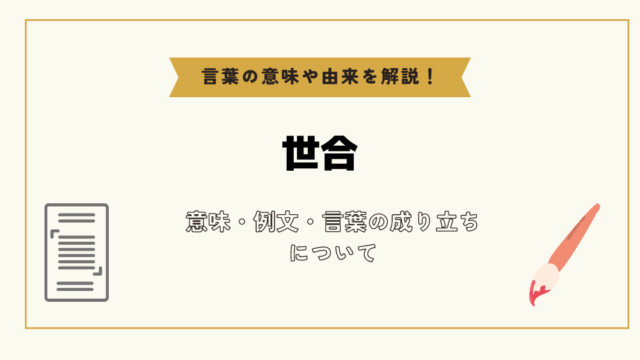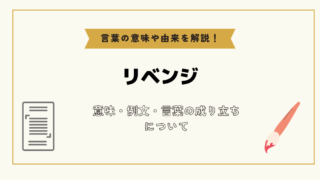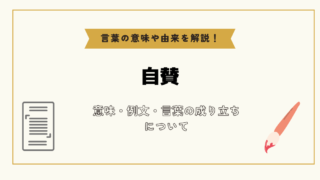Contents
「わざわざ」という言葉の意味を解説!
「わざわざ」という言葉は、特別な手間や努力をして物事をすることを表します。
何かしらの行動をすることに対して、普通であれば必要ではないと思われる手間や努力を惜しまずに行動する様子を表現する言葉です。
例えば、友人の誕生日にプレゼントを贈る際には普通は近くのお店で買って渡すことが多いですが、「わざわざ」遠くの専門店まで行って特別な品物を購入するなど、努力や手間をかけて贈ることを指します。
「わざわざ」は親しみやすい言葉であり、相手に対して特別感を与えたいときや感謝の気持ちを伝えたいときに用いられます。
「わざわざ」という言葉の読み方はなんと読む?
「わざわざ」という言葉は、珍しい読み方をすることなく、そのまま「わざわざ(wazawaza)」と読みます。
この言葉の響きは、特別感や丁寧さを表現する上で大切な要素となっています。
この響きによって、「わざわざ」の意味や表現する感情がより強く伝わるのです。
「わざわざ」という言葉の使い方や例文を解説!
「わざわざ」という言葉は、相手への心遣いや感謝の気持ちを表現するために使用されます。
例えば、友人が忙しい中でわざわざ時間を作って自分のために手紙を書いてくれた場合、「わざわざ手紙を書いてくれたんだよ」というように使います。
また、お店に行くためにわざわざ遠くまで足を運んだ場合には、「わざわざ店まで来てくれてありがとう」というように使われます。
このように、「わざわざ」という言葉は、相手にかける言葉であることを忘れずに使いましょう。
「わざわざ」という言葉の成り立ちや由来について解説
「わざわざ」という言葉は、平安時代の言葉であると言われています。
元々は「優(すぐり)」という単語があり、特別な労力や手間を掛けることを表していました。
その後、江戸時代になると「すぐれ」という言葉が「わざ」と変化し、さらに「わざ」と「わ」という言葉が合わさり、「わざわざ」という形になったと言われています。
日本語の変遷の中で、徐々に使われるようになり、現代まで継承されている言葉なのです。
「わざわざ」という言葉の歴史
「わざわざ」という言葉の歴史は古く、平安時代にさかのぼります。
最初は「優」という言葉が使われ、特別な労力や手間をかけることを意味していました。
江戸時代になると、「優」が「すぐれ」と変化し、更に「すぐれ」と「わ」という発音が合わさって「わざ」となりました。
そして、その後「わざ」と「わ」が重ねられて、「わざわざ」という形になりました。
この言葉の形が定着したのは、江戸時代後期から明治時代のころとされています。
「わざわざ」という言葉についてまとめ
「わざわざ」という言葉は、特別な労力や手間をかけて物事を行うことを表す言葉です。
相手に対しての心遣いや感謝の気持ちを示す場面で使われることが多く、親しみやすい言葉として広く使用されています。
また、この言葉の由来は平安時代までさかのぼり、現代まで続く言葉として受け継がれてきました。
丁寧さや特別感を表現する際には、ぜひ「わざわざ」という言葉を使用してみてください。