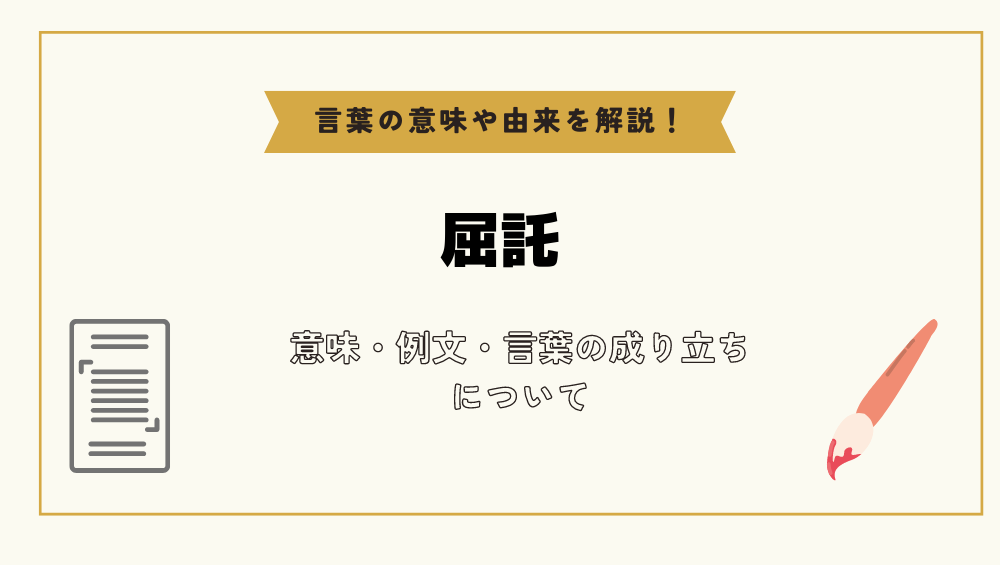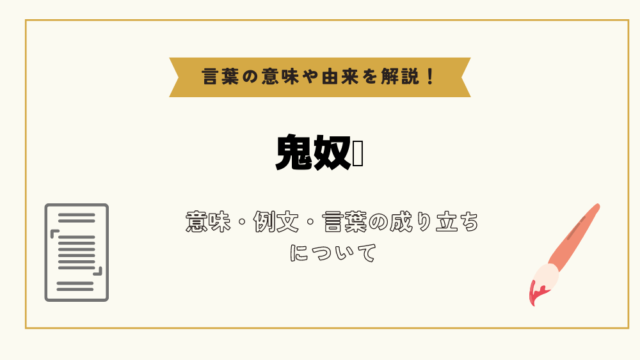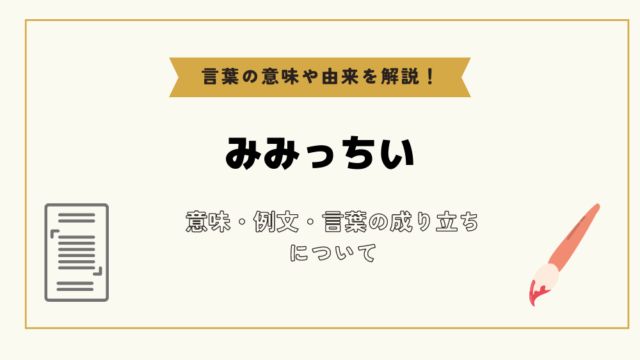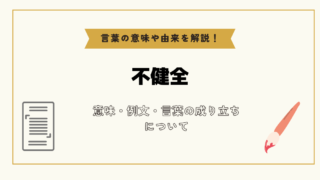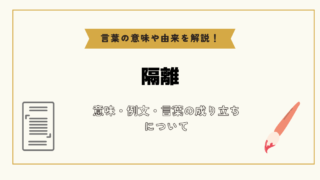Contents
「屈託」という言葉の意味を解説!
「屈託」という言葉は、心配や悩みの表情を表すために使われる言葉です。
何か心に重荷を抱えていたり、困難な状況に直面しているときに、表情に現れる深いしわや苦悩が「屈託」として表現されます。
屈託という言葉は、日本語の美しい表現の一つです。
人々の心の内面を端的に表すことができ、その表情から相手の気持ちや状況を感じ取ることができるでしょう。
「屈託」という言葉の読み方はなんと読む?
「屈託」という言葉は、「くったく」と読みます。
この読み方は、普通の言葉として広く使われていますが、やや堅いイメージもあるため、日常会話ではあまり使われないかもしれません。
「屈託」という言葉の使い方や例文を解説!
「屈託」という言葉は、主に文学作品や詩、または物語や小説などのフィクション作品で使われます。
例えば、「彼は口角に微かな屈託を浮かべて話す」と表現されるように、登場人物の表情や心情をより豊かに表現するために使われます。
また、日常会話ではあまり使われることはありませんが、場面や文脈によっては、「彼女の顔には屈託が見えた」といった表現も用いられることがあります。
「屈託」という言葉の成り立ちや由来について解説
「屈託」という言葉の由来は、江戸時代にさかのぼります。
当時の人々は、人間の表情や心情をより深く表現するために、独自の言葉を生み出していました。
その中で、「屈託」という言葉が生まれ、心の奥底に抱える悩みや苦悩を象徴する言葉として定着しました。
「屈託」という言葉の歴史
「屈託」という言葉は、江戸時代に文学や芸術が発展した時代に広まりました。
その後も、文学や詩、小説などの表現手法として使われ続け、現代に至っても多くの人々に愛されています。
また、心理学や演劇などでも重要な概念として取り上げられています。
「屈託」という言葉についてまとめ
「屈託」という言葉は、心配や悩みの表情を表す言葉です。
その深いしわや苦悩が、人々の内面を表す重要な要素となります。
日常会話ではあまり使われないものの、文学や芸術、心理学などで広く使われる言葉として知られています。
屈託は、人間の心の奥底に抱える思いや苦悩を表現するための貴重な言葉であり、その使い方や歴史を理解することで、より豊かな表現が可能となります。