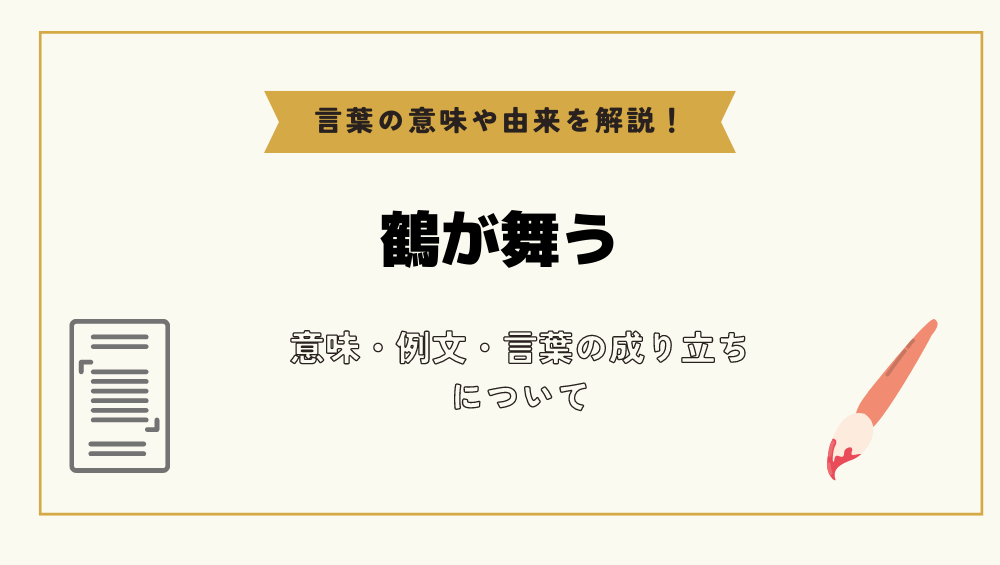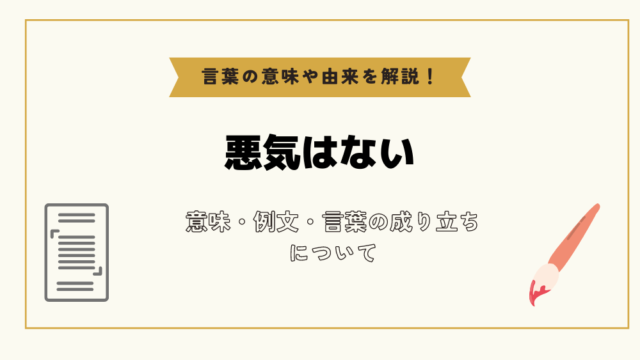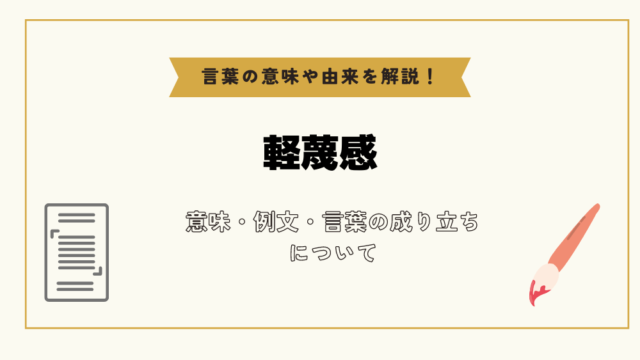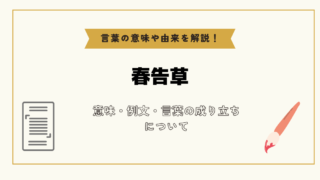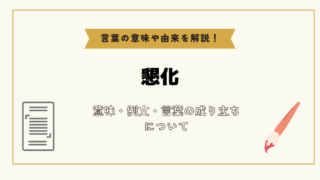Contents
「鶴が舞う」という言葉の意味を解説!
「鶴が舞う」という言葉は、鶴が空気を感じて翼を広げ、美しく舞い踊る様子を描いた言葉です。
この言葉は、自由で優雅で美しい姿勢や行動に対して使われることが多く、高貴さや優雅さを表現するために使用されます。
「鶴が舞う」の読み方はなんと読む?
「鶴が舞う」は、つるがまうと読みます。
つるという漢字は、しゃれた感じを持っているため、綺麗に舞う様子にピッタリの読み方です。
また、この読み方は一般的な読み方であり、言葉のイメージにぴったり合っています。
「鶴が舞う」という言葉の使い方や例文を解説!
「鶴が舞う」という言葉は、自然やアート、パフォーマンスなど、美しいものや優れたものを表現する際に使われます。
例えば、「彼の音楽はまるで鶴が舞うように美しい」といった使い方があります。
また、「彼女の優雅なダンスは鶴が舞うようだ」と言われることもあります。
「鶴が舞う」という言葉の成り立ちや由来について解説
「鶴が舞う」という言葉の成り立ちや由来は明確ではありませんが、鶴は古来から日本の文化において優雅さや長寿、幸福を象徴する存在とされてきました。
そのため、鶴が舞う様子は人々にとって美しいシンボルとなり、言葉としても広く愛されるようになりました。
「鶴が舞う」という言葉の歴史
「鶴が舞う」という言葉の歴史は古く、日本の古典文学や俳句などで見られます。
特に、万葉集や源氏物語などの文学作品には、鶴が舞う光景やその美しさが詠われています。
また、鶴が舞う様子は絵画や浮世絵、舞台芸術にも多く描かれ、多くの人々に愛され続けてきました。
「鶴が舞う」という言葉についてまとめ
「鶴が舞う」という言葉は、鶴の美しい舞いを表現する言葉であり、自由で優雅な行動や美しい姿勢を表現するために使用されます。
また、古典文学や芸術作品、日常会話などさまざまな場面で使われる言葉でもあり、日本の文化に深く根付いています。