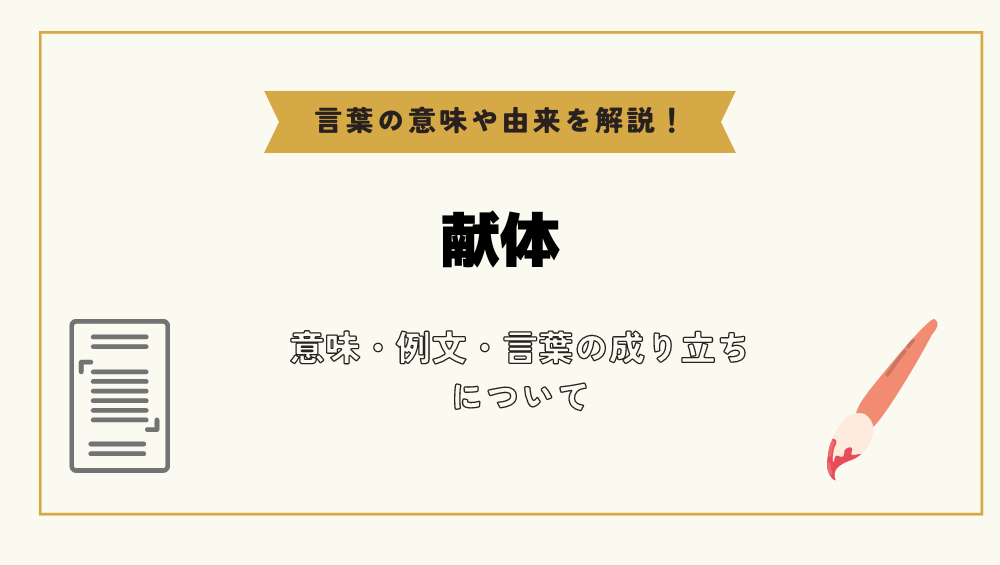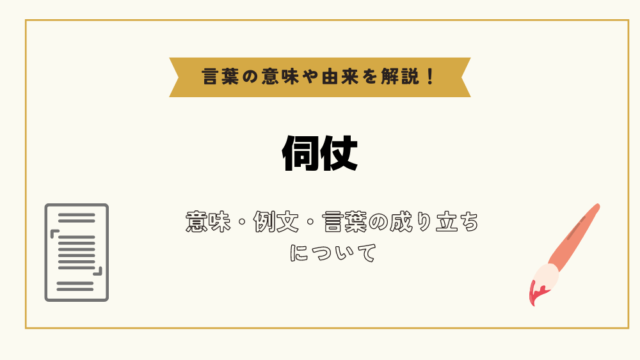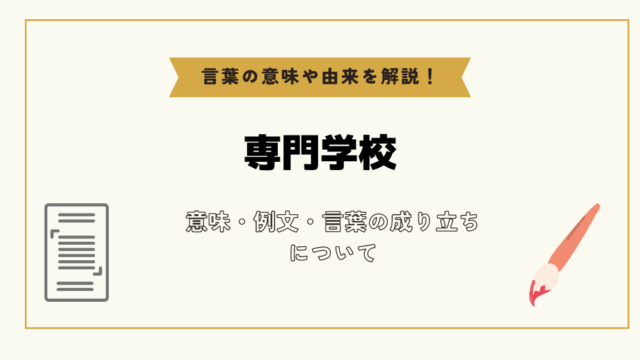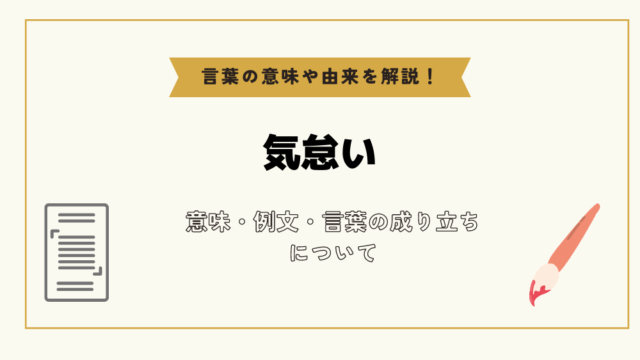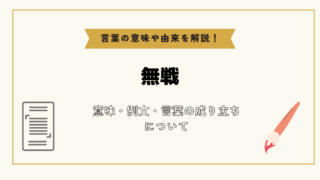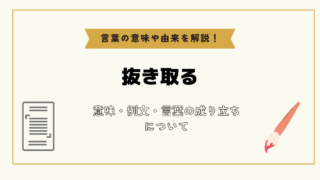Contents
「献体」という言葉の意味を解説!
「献体」とは、人間や動物の死体を科学的な目的で寄贈することを指す言葉です。
具体的には、解剖学や医学の研究、教育、臓器移植のために、著作権の実施者が自発的に遺体を提供することを指します。
献体の提供は、医学の発展や技術の向上に非常に重要な役割を果たしています。
また、献体を受け入れる側もそれを尊重し、責任を持って取り扱わなければなりません。
「献体」という言葉の読み方はなんと読む?
「献体」は、「けんたい」と読みます。
日本語の「けん」と「たい」の2つの音から成り立っています。
特に難しい読み方ではありませんので、覚えやすいですね。
「献体」という言葉の使い方や例文を解説!
「献体」という言葉は、主に医学や臨床医療の分野で使われます。
例えば、「医学生は臨床経験を積むために献体を観察しています」というように使われます。
また、「献体制度の活用によって、医学の研究が進歩している」というようにも使われます。
このように「献体」は、医学や臨床の現場で重要な役割を果たしている言葉です。
「献体」という言葉の成り立ちや由来について解説
「献体」という言葉は、古代中国や古代日本の宗教的な儀式に由来しています。
古代の人々は神への奉納や自己の尊重を示すために、生け贄の動物や植物を献上することがありました。
この文化が後の時代において、人間の遺体を科学的な目的で献上するという行為につながったのです。
現在の献体制度は、このような歴史的な背景をもつ言葉です。
「献体」という言葉の歴史
「献体」という言葉の歴史は古く、人類が医学や解剖学の研究を始めた頃から存在します。
古代ギリシャでは、解剖学の始祖であるヒポクラテスが人体の解剖を行ない、解剖学の基礎を築きました。
その後、ヨーロッパやアジアでも解剖学の研究が進み、献体の必要性が高まりました。
そして、現代の献体制度が整備され、医学や臨床医療の発展に大きく寄与してきました。
「献体」という言葉についてまとめ
「献体」とは、人間や動物の遺体を科学的な目的で提供することを指す言葉です。
献体制度は、医学の研究や教育、臓器移植にとって非常に重要な存在であり、医療の発展に大きく寄与しています。
また、「けんたい」と読みますが、特に難しい読み方ではありません。
古代の宗教的な儀式から由来し、古代から現代へ受け継がれてきた言葉です。
献体の歴史は古く、世界中で解剖学の研究が進む中で発展してきました。