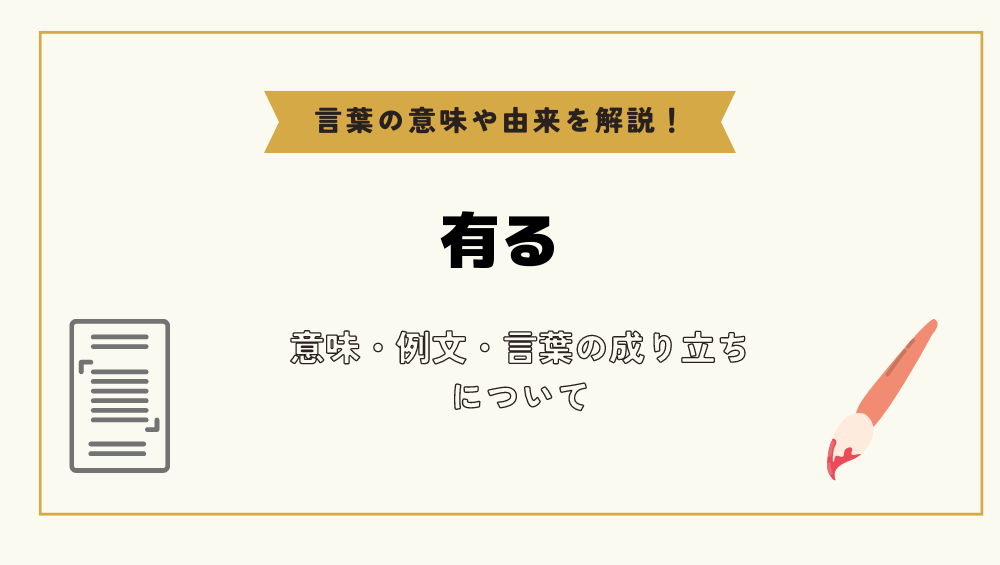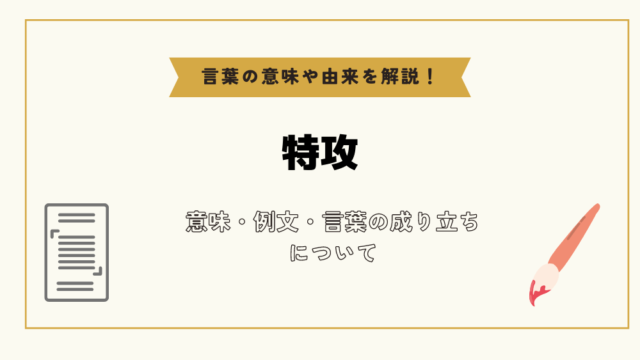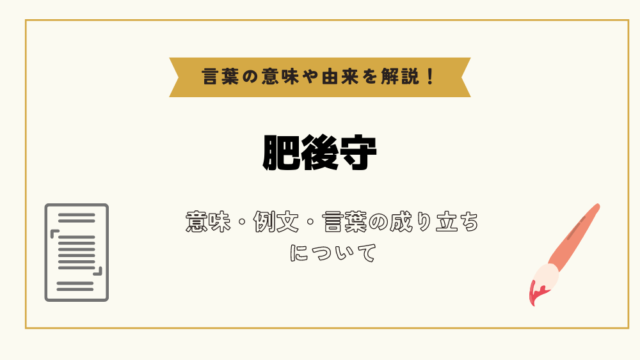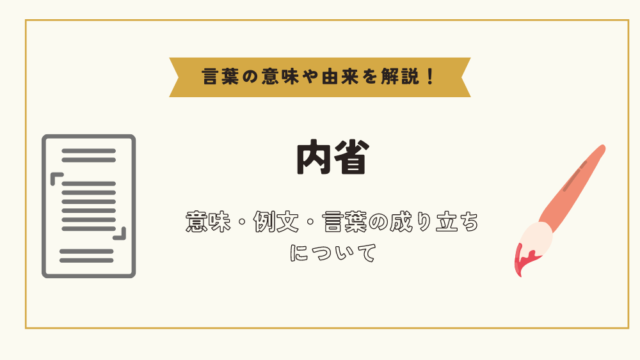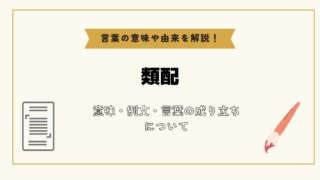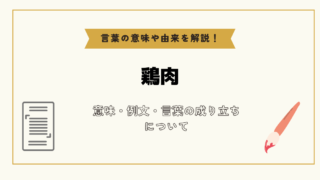Contents
「有る」という言葉の意味を解説!
「有る」という言葉は、日本語の動詞であり、存在すること、持っていることを表します。
何かがあるときに使われることが多く、対象が物や事象、場所、状況などさまざまなものに及びます。
例えば、部屋に本があります、「明日は予定があります」など、さまざまな場面で用いられます。
「有る」の読み方はなんと読む?
「有る」は、通常は「ある」と読まれます。
この読み方は古代日本語から引き継がれたもので、「ありむ」と言われることもあります。
ただし、特定の文脈や地域によっては、「おる」とも読まれることがあります。
例えば、関西方言などでは「おる」という表現が一般的です。
しかし、一般的には「ある」という読み方が一番馴染み深いです。
「有る」という言葉の使い方や例文を解説!
「有る」は、さまざまな文脈で使われます。
ものや事象、場所、状況など、様々な対象に対して使用できます。
例えば、「机の上に本がある」、「友達との約束がある」、「彼の話にはある考えが含まれている」など、日常生活や文章の中で頻繁に使われます。
また、「本当にその話はあるのか?」のように、疑問の意味で使用することもあります。
「有る」という言葉の成り立ちや由来について解説
「有る」という言葉は、古代日本語から派生したものです。
その由来は、古代中国の文献や漢字の語源などに関連しています。
古代中国の「有」という字が、日本で「有る」という形で日本語に取り込まれたものと考えられています。
このように、言葉の由来や成り立ちは、長い歴史と文化の中で形成されてきたものと言えます。
「有る」という言葉の歴史
「有る」という言葉の歴史は古く、日本語の起源にまで遡ることができます。
古代の日本語では、「有る」はさまざまな表現の一部として使われていました。
その後、日本語が変化していく中で、現代の意味や用法が形成されました。
現代の日本語では、日常的に「有る」を使うことが多いですが、その使用方法や文脈は、歴史的な変遷を経て現在に至っています。
「有る」という言葉についてまとめ
「有る」という言葉は、日本語の基本的な動詞であり、存在や所有を表す役割を果たします。
さまざまな対象に対して使用され、日常生活や文章の中で頻繁に使われます。
その由来は古代中国の文献などに関連しており、日本語の歴史と文化に根付いています。
日本語の起源にまで遡る歴史を持ち、現代の日本語においても重要な役割を果たしています。