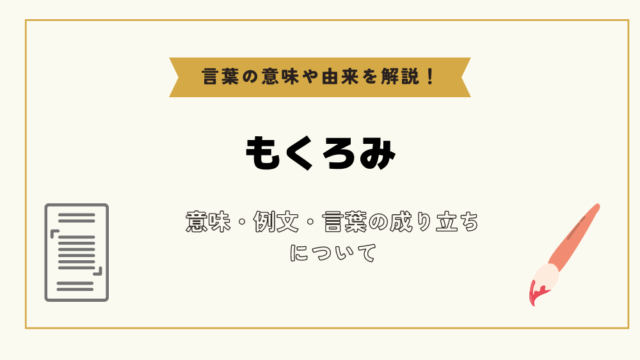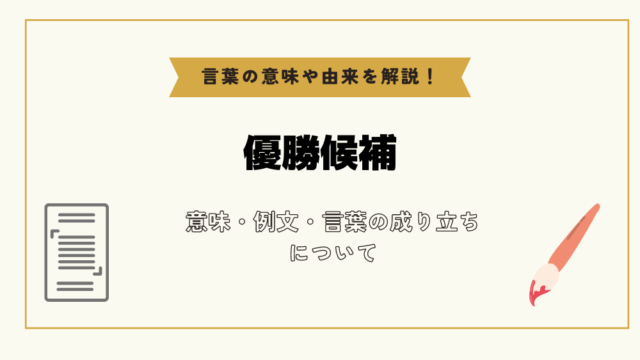Contents
「国家予算」という言葉の意味を解説!
「国家予算」とは、国家が一定期間の経済活動において計画的に使用する財源と支出をまとめたものです。
具体的には、国が所得や税金などの収入を予測し、それに対して教育や医療などの公共サービス、公共事業、国防などの支出を計画します。
国家予算は、国の経済や政策を適切に運営するための重要な要素であり、国民の福祉や発展のために不可欠なものです。
予算は政府の方針や社会のニーズに応じて編成され、民主的なプロセスを経て国会で審議・承認されます。
国家予算は、国の計画的な財政運営を支え、国民の暮らしや経済の安定に大きな影響を与える重要なものです。
。
「国家予算」という言葉の読み方はなんと読む?
「国家予算」という言葉は、「こっかよさん」と読みます。
日本語の発音で読むと、どこか親しみやすさを感じるかもしれませんね。
国家予算は、国が計画的に財源を集め、支出を決める上で欠かせないものです。
そのため、その言葉自体も身近で使いやすいものとして、広く一般的に使われています。
「国家予算」は「こっかよさん」と読むので、覚えておくと便利です。
。
「国家予算」という言葉の使い方や例文を解説!
「国家予算」という言葉は、財政や政治に関する話題でよく使われます。
政府が年度ごとに予測した収入と支出をまとめたものを指し、国の財政状況や経済政策の評価・分析にも使われます。
例えば、「今年の国家予算はエネルギー政策に重点を置いている」というような使い方があります。
ここでの例文では、政府がエネルギー政策に資金を投じることを予測していることが分かります。
「国家予算」は、国の財政に関する話題で使われ、政府の予測や方針を表現するために用いられます。
。
「国家予算」という言葉の成り立ちや由来について解説
「国家予算」という言葉は、日本語の経済・財政用語として長い歴史を持ちます。
その由来は、明治時代にさかのぼります。
明治政府が施行した「国法」によって、国家の収入や支出を計画的に管理する体制が整備され、国家予算が導入されたのです。
それ以来、国家予算は日本の財政運営の基本的な枠組みとなり、現在に至っています。
「国家予算」の由来は明治時代にさかのぼります。
明治政府の政策によって導入され、日本の財政運営の基本となっています。
。
「国家予算」という言葉の歴史
「国家予算」という言葉は、日本の近代化とともに歩んできた歴史があります。
明治時代の政府改革によって制度が整えられ、国家予算が初めて編成されました。
その後、国家予算は戦争や経済の変動などによって度々見直され、現在の形に進化してきました。
今では、国会での予算審議や国民の関心が高まる予算案の発表など、国家予算の歴史は日本の政治・経済の中で重要な位置を占めています。
「国家予算」という言葉は、明治時代からの長い歴史を持つものです。
戦争や経済の変動によって度々見直され、現在の形に発展してきました。
。
「国家予算」という言葉についてまとめ
「国家予算」とは、国家が一定期間の経済活動において計画的に使用する財源と支出をまとめたものです。
国の計画的な財政運営を支える重要な要素であり、国民の暮らしや経済の安定に大きな影響を与えます。
読み方は「こっかよさん」といいます。
政府や財政に関する話題で使われ、政府の予測や方針を表現するために用いられます。
明治時代から続く歴史を持ち、日本の財政運営の基本となっています。
予算審議や予算案の発表など、国家予算は日本の政治・経済の中で重要な位置を占めています。
「国家予算」という言葉は、国家の財政運営において不可欠なものであり、日本の政治・経済の重要な要素となっているのです。
。