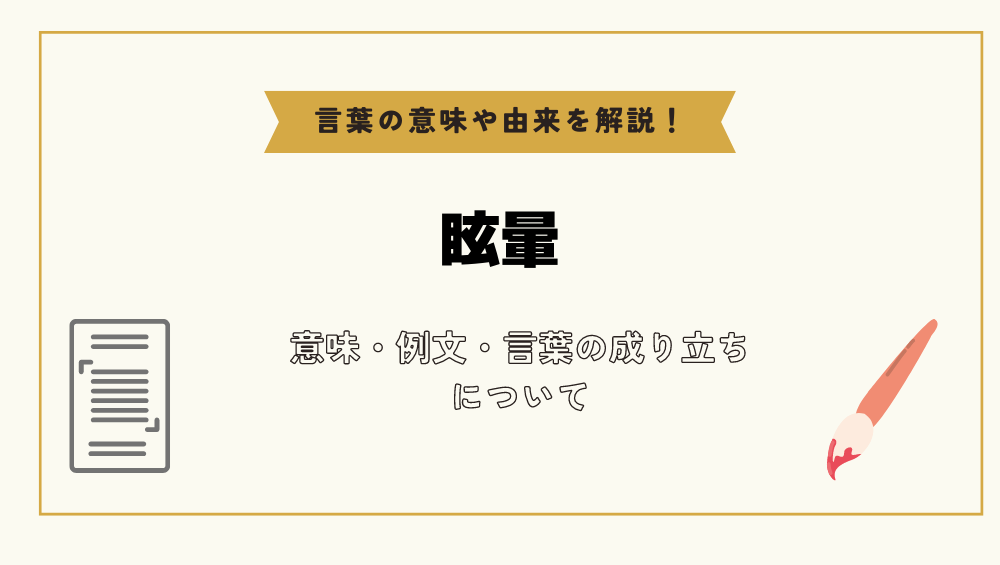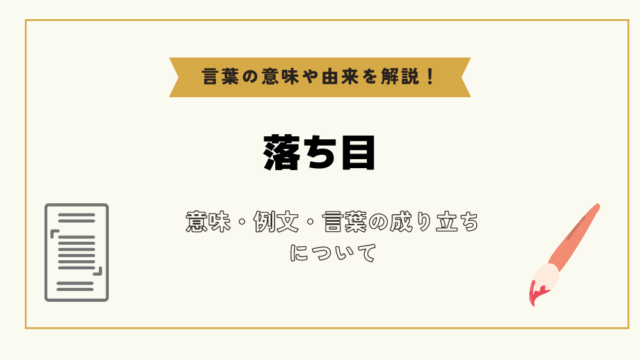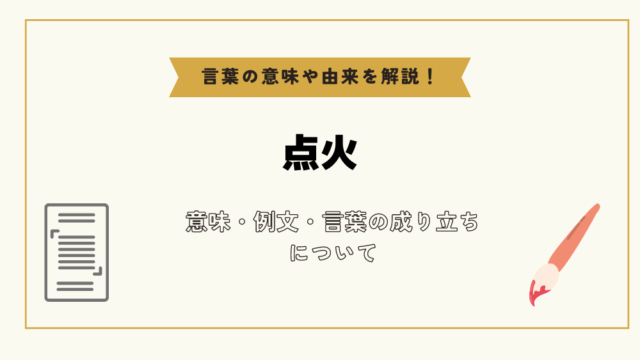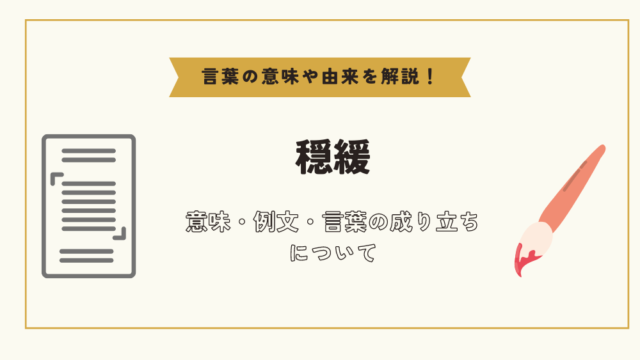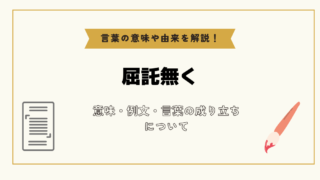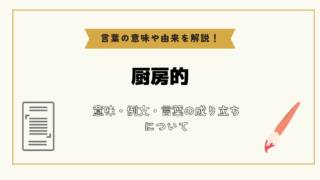Contents
「眩暈」という言葉の意味を解説!
「眩暈(めまい)」とは、視覚や身体のバランス感覚が乱れる症状を指します。
患者は回るような感覚やふらつきを経験し、時には吐き気や立ちくらみを伴うこともあります。
この症状は、内耳や脳の機能の異常によって引き起こされることが多いです。
いつも安定した感じのする立ち位置であれば、眩暈を感じることはほとんどないでしょう。
しかし、中には酔ったり、目が回ったり、頭が痛くなったりするといった症状を感じる方もいます。
眩暈は日常生活にも悪影響を与えることがあり、早期の対処が重要です。
「眩暈」という言葉の読み方はなんと読む?
「眩暈(めまい)」と読みます。
この言葉は「めん」という漢字を使っており、その意味は「まぶしい」や「ぼんやりする」といった感覚を表現しています。
このような感覚が確かに眩暈の特徴であるため、その読み方が選ばれたのかもしれません。
「眩暈」という言葉は日本語において一般的に使用されていますので、これからも「めまい」と読むことが一般的とされていくでしょう。
「眩暈」という言葉の使い方や例文を解説!
「眩暈(めまい)」という言葉は、症状の表現に使用されることが多いです。
例えば、「スピンクラスをしていたら、急に眩暈がしてきて倒れそうになった」というような使い方があります。
旅行中に熱中症で眩暈を起こし、病院に搬送されることもあります。
また、「最近仕事が忙しくて、ストレスがたまって眩暈を感じることが多い」といったような使い方もできます。
「眩暈」という言葉の成り立ちや由来について解説
「眩暈(めまい)」という言葉の成り立ちは、古い中国語から派生しました。
その意味は「目がくらむこと」や「妄想すること」といった意味合いがあります。
この言葉が日本語に進入したのは、平安時代の終わり頃からと言われています。
当時の人々が回転するような感覚を「めまい」と表現し、それが現代まで受け継がれています。
「眩暈」という言葉の歴史
「眩暈(めまい)」という言葉は、日本語において古くから使用されてきました。
鎌倉時代や室町時代には既に文献に見られる言葉であり、近代以降もその使用頻度は増え続けています。
特に、現代社会ではストレスや疲労が原因となり、眩暈を感じる方が増加しています。
これにより、この言葉の重要性や理解の必要性がますます高まってきています。
「眩暈」という言葉についてまとめ
「眩暈(めまい)」という言葉は、視覚や身体のバランス感覚が乱れる症状を表現する言葉です。
回るような感覚やふらつきを伴い、日常生活に支障をきたすこともあります。
「眩暈」は日本語において古くから使われており、その使用頻度は増え続けています。
ストレスや疲労などが原因となり、この症状を感じる方も増えていますので、早期の対処や予防が大切です。