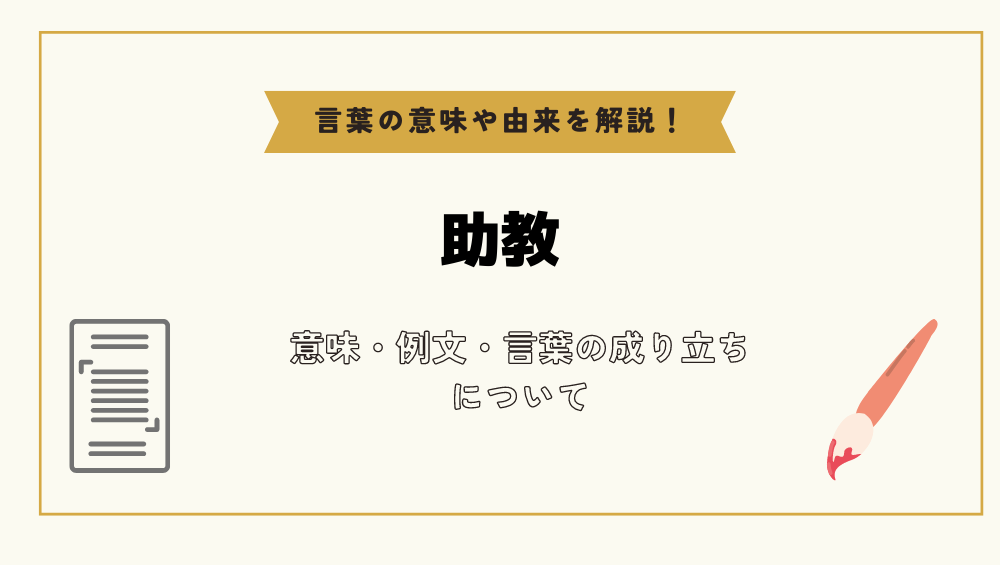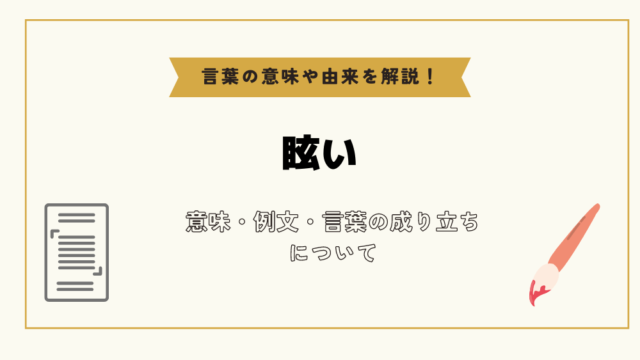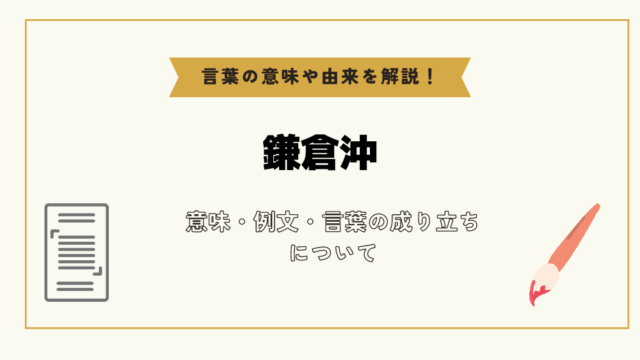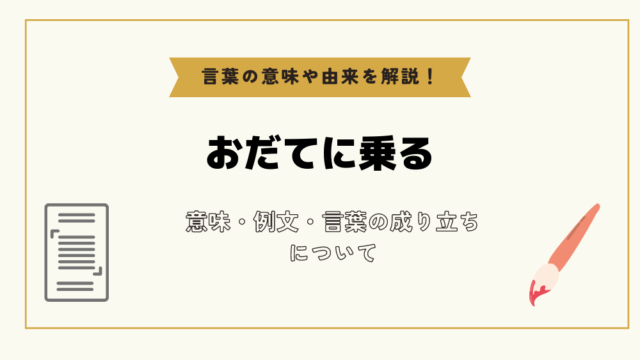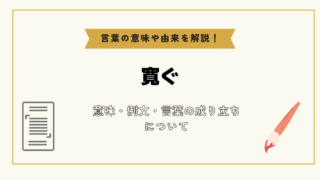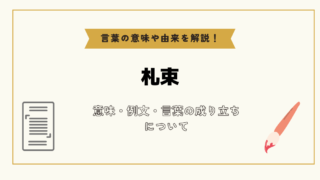Contents
「助教」という言葉の意味を解説!
「助教」とは、大学や研究機関において、教授の補佐をする役職のことを指します。具体的には、教授が行う研究や教育活動をサポートする役割を担っています。助教の主な業務は、研究実験の指導や研究論文の執筆、学生への指導や講義の担当など、幅広い活動が含まれます。
助教は、研究や教育において高い専門性を持ちながらも、教授ほどの権限は持っていません。しかし、助教は若手研究者や教員の登竜門として位置づけられており、将来的な教授昇任の道も開かれています。
「助教」という言葉の読み方はなんと読む?
「助教」という言葉は、「じょきょう」と読まれます。ただし、読み方には地域によって差がある場合もありますが、一般的には「じょきょう」となります。
「助教」という言葉の使い方や例文を解説!
「助教」という言葉は、教育や研究の分野で頻繁に使用されます。例えば、以下のような文脈で使われることがあります。
1. 彼は大学で助教として働いています。
2. 助教の指導のもと、学生たちは優れた研究成果を上げました。
3. 助教の授業は非常にわかりやすくて人気があります。
「助教」という言葉は、大学や研究機関の教育・研究において重要な役割を果たす人々を指すため、使い方は正確かつ適切に行う必要があります。
「助教」という言葉の成り立ちや由来について解説
「助教」という言葉は、日本の教育制度において洋学の導入とともに使われるようになりました。元々は、西洋の「Assistenzprofessor」が訳語として用いられ、「助教授」と呼ばれていましたが、後に「助教」と省略されるようになりました。
この言葉の由来は、大学教育において教授の補佐をする役割を果たすことから来ています。さらに、ドイツやオーストリアの教育制度においても同様の役職が存在し、その影響もあったと考えられています。
「助教」という言葉の歴史
「助教」という言葉の歴史は長く、日本の近代教育制度の始まりとともに存在しています。明治時代になると、洋学の導入が進み、西洋の教育制度に基づいた教育機関が設立されます。
大学では、教授の補佐をする役職である「助教授」が置かれ、その後「助教」という省略形が一般的に使用されるようになりました。現在も、日本の大学や研究機関において、助教の役職は重要な存在として位置づけられています。
「助教」という言葉についてまとめ
「助教」とは、大学や研究機関において教授の補佐をする役職のことを指します。教育や研究の分野で頻繁に使用され、専門性を持ちながらも若手研究者や教員の登竜門としての役割も果たしています。
この言葉は、日本の教育制度の中で成立し、洋学の導入とともに使われるようになりました。現在でも、助教の役割は重要であり、教育や研究の発展に貢献しています。