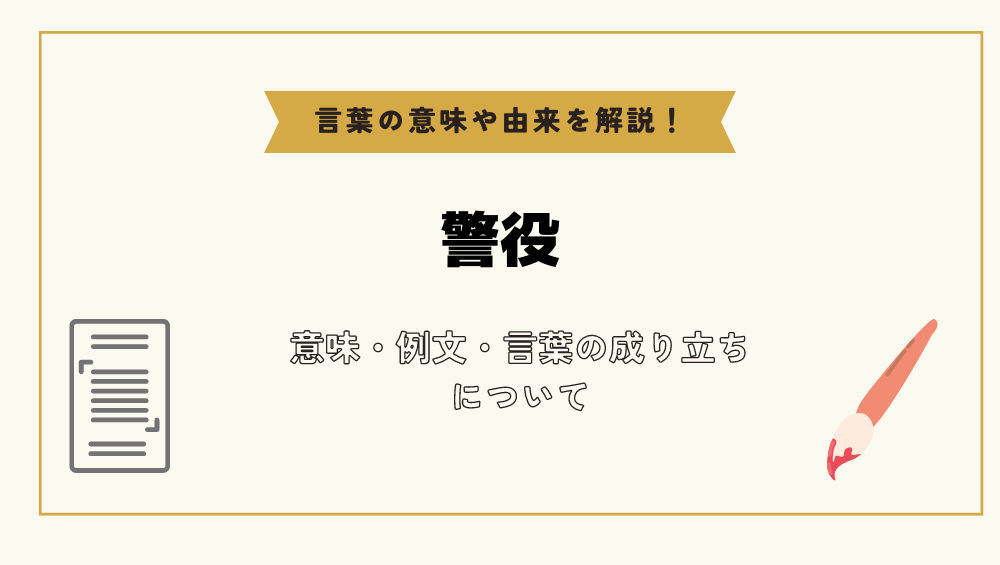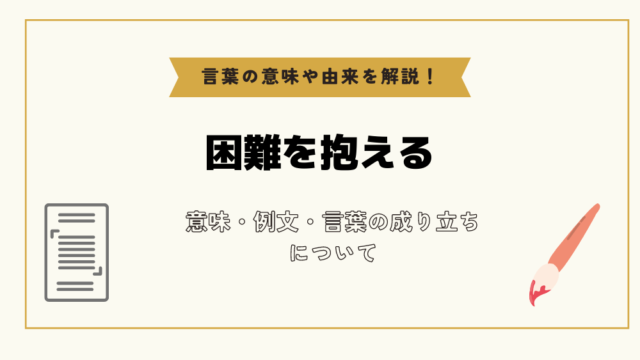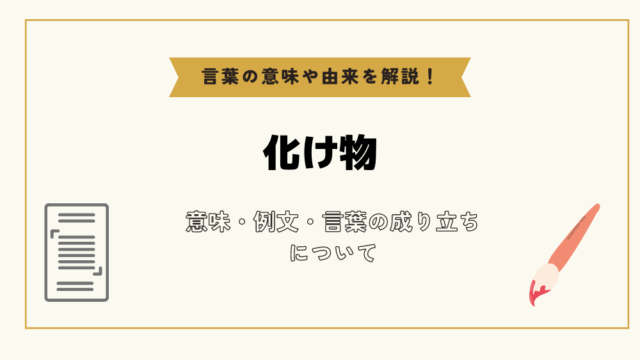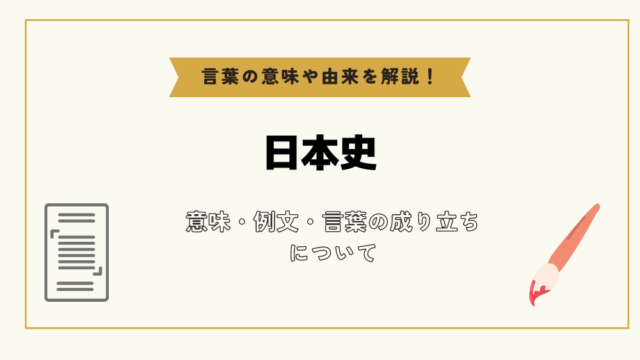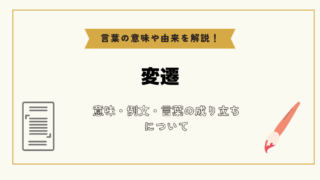Contents
「警役」という言葉の意味を解説!
警役とは、警察が犯罪の防止や治安の維持を目的として行う業務のことを指します。
具体的には、街頭の巡回や交通規制、パトロールなどが含まれます。
警役は地域の安全を守るために欠かせない役割を果たしており、警察官の重要な業務の一つです。
「警役」という言葉の読み方はなんと読む?
「警役」という言葉は、「けいえき」と読みます。
この読み方は一般的なもので、警察関連の仕事や業務を表す場合に使用されます。
警察官が地域の安全を守るためにおこなう業務のことを指すときには、この読み方が使われます。
「警役」という言葉の使い方や例文を解説!
警役という言葉は、警察における業務や任務を指すため、以下のような使い方があります。
。
例文1:地域の治安を守るために、警察官が日夜警役に当たっている。
。
例文2:私は来週から警役につくことになった。
「警役」という言葉の成り立ちや由来について解説
「警役」という言葉は、「警察の業務や責務」を意味する言葉です。
日本では、明治時代の警察制度の整備に伴い、警察官が地域の安全を守るためにおこなう業務の名称として定着しました。
警察官の役割や任務の一つとして重要な位置を占める「警役」は、現在も継続して使われています。
「警役」という言葉の歴史
「警役」という言葉の歴史は、明治時代以降にさかのぼります。
明治時代になると、西洋の警察制度が導入され、それに伴い日本でも警察の業務が整備されていきました。
その際に「警役」という言葉が生まれ、警察官の業務の一つとして用いられるようになりました。
現在も変わらず「警役」という言葉が使われているのは、その由来によるものです。
「警役」という言葉についてまとめ
警役は、警察が地域の安全を守るためにおこなう業務を指します。
日本語の「けいえき」と読みます。
警察官が巡回や取り締まりなどを行い、社会の平和と秩序を守るために欠かせない役割を果たしています。
明治時代以降、警察制度の整備に伴い「警役」という言葉が生まれ、今もなお使われ続けています。