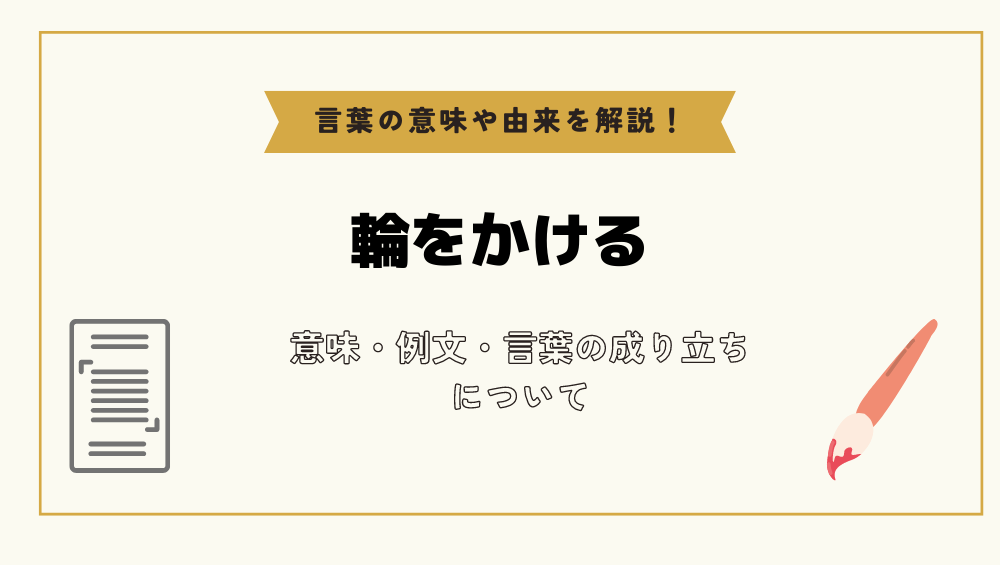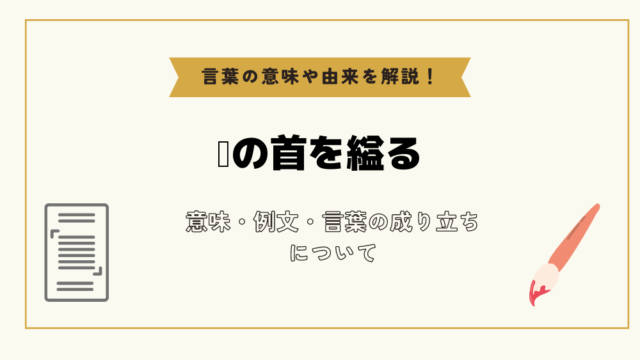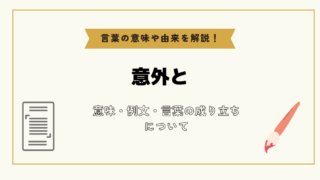Contents
「輪をかける」という言葉の意味を解説!
「輪をかける」という言葉は、さらに進化や発展をすることを表現した表現です。
「輪」とは円の形を意味し、その形状が繰り返されることで強調された状態を示しています。
「かける」は「さらに増す」「強める」という意味がありますので、合わせて「輪をかける」となると、一つの努力や成果に物足りなさを感じ、それ以上の成果を得るためにさらに努力をすることを表現しています。
「輪をかける」という言葉の読み方はなんと読む?
「輪をかける」という言葉の正しい読み方は、「わをかける」となります。
漢字の「輪」は「わ」と読み、「かける」は「かける」と読みます。
この言葉は比喩的な表現であるため、読み方に注意が必要です。
「輪をかける」という言葉の使い方や例文を解説!
「輪をかける」という言葉は、他の表現としても使われることがあります。
例えば、趣味や才能に磨きをかける、スキルを輪にかける、努力を輪にかけるなどです。
これらは一つの領域での成果や努力を通り越して、更なる高みを目指すという意味合いを含んでいます。
例えば「輪をかけて頑張って勉強する」という言い回しは、普通の頑張りでは満足せず、さらなる成績向上を目指して、日々の勉強に真剣に取り組む様子を表現しています。
「輪をかける」という言葉の成り立ちや由来について解説
「輪をかける」という言葉の成り立ちや由来は明確にはわかっていませんが、日本の言葉遣いや表現の美しさを表現するために使われるようになりました。
「輪」は円の形を表し、その形状が繰り返されることで強調された状態を示し、「かける」は増す、強めるという意味があります。
この二つを組み合わせることで、一つの領域での成果や努力に物足りなさを感じ、それ以上の成果を得るためにさらなる努力をすることを表現できるようになりました。
「輪をかける」という言葉の歴史
「輪をかける」という言葉の歴史は古く、日本の古典文学や民話にも見受けられます。
例えば、江戸時代の随筆家・林芙美子の「お寺まいり」には、「ある人がお寺で念仏を唱えながら心を落ち着ける様子を、輪をかけたような凛々しさがある」という表現があります。
また、童話「かぐや姫」にも「かぐや姫の美しさは一度見た者が皆驚き、その美しさに輪をかけて言い伝えされた」という表現があります。
これらの例からも、日本語の美しさや表現力を強調するために、「輪をかける」という言葉が使われてきたことが伺えます。
「輪をかける」という言葉についてまとめ
「輪をかける」という言葉は、さらに進化や発展をすることを表現した表現です。
一つの努力や成果に物足りなさを感じ、それ以上の成果を得るためにさらに努力をすることを示しています。
この言葉は比喩的な表現であり、日本の言葉遣いや表現の美しさを表現するために使われています。
日本の古典文学や民話でも見られる言葉であり、その歴史の長さや日本語の美しさを感じさせるものです。