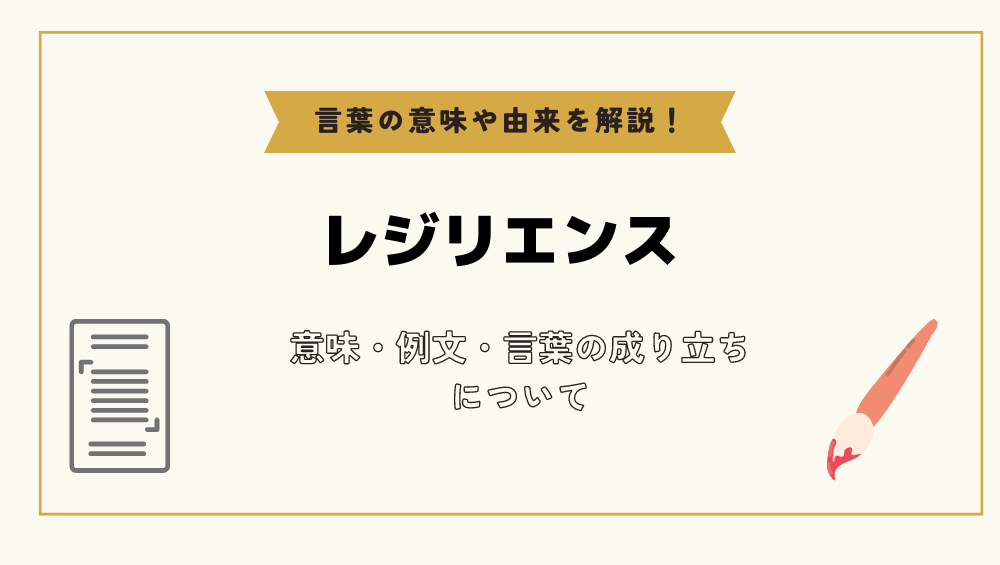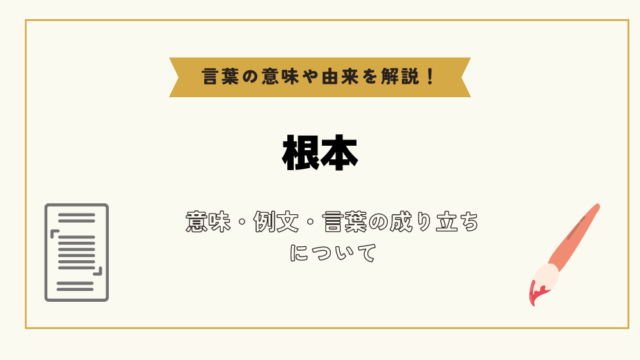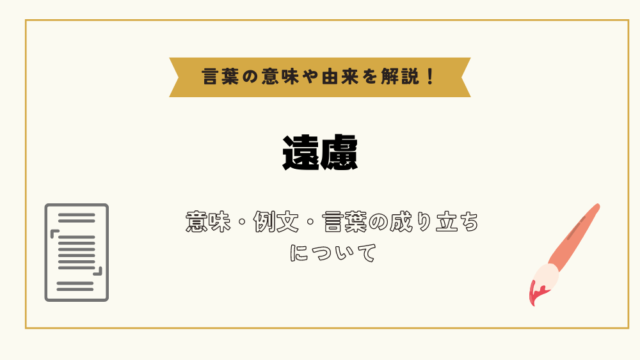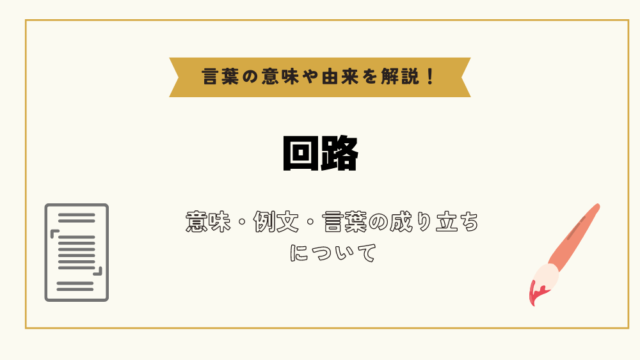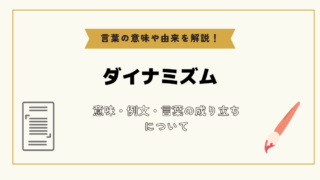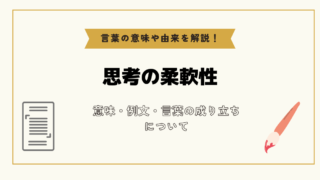「レジリエンス」という言葉の意味を解説!
レジリエンスとは、逆境やストレスから立ち直り、元の状態あるいはそれ以上の状態へと回復する力を指す言葉です。ビルが地震の揺れを吸収して元に戻るように、人間も心理的な衝撃を受けても再び前向きに立ち上がることができます。近年は個人だけでなく、組織や社会全体の適応力を示す概念としても使われています。
レジリエンスの要素には「自己効力感」「社会的サポート」「現実的な楽観主義」などが挙げられます。これらが相互に作用することで、困難に直面した際の回復速度や質が大きく変わります。
心理学や災害対策、経営学の分野でも幅広く研究されており、学術的にも実務的にも高い注目を集めています。ビジネスでは市場変動への適応力、教育では子どもの学習意欲を保つ力として活用されるなど、応用範囲が広がっています。
「レジリエンス」の読み方はなんと読む?
「レジリエンス」はカタカナで「レジリエンス」と表記し、英語の“resilience”(リジリアンスに近い発音)を日本語に定着させたものです。日常会話では「レジリエンス」とそのまま読むのが一般的で、アクセントは「レ・ジリ・エンス」の第2拍に置くと自然に聞こえます。
日本語の同音語が存在しないため誤読は少ないものの、しばしば「レジリ“ア”ンス」と最後を「ア」で読んでしまうケースがあります。ビジネス会議や学会で使用する際は、正しいアクセントで発音すると理解度が高まります。
「レジリエンス」という言葉の使い方や例文を解説!
レジリエンスは形容詞や副詞形を持たず、名詞として単体で用いるのが基本です。文章では「レジリエンスを高める」「レジリエンスが求められる」などの形で使われます。人や組織の適応力を示す場合に限定され、単なる体力や瞬発力とは区別されます。
【例文1】不確実な時代だからこそ、企業にはレジリエンスが欠かせない。
【例文2】彼女は困難を経験するたびにレジリエンスを強化してきた。
注意点として、レジリエンスは「努力すれば無限に伸ばせる万能スキル」ではありません。過剰なストレスにさらされれば誰でも限界があるため、「適切な休息」や「支援を求める姿勢」とセットで語る必要があります。
「レジリエンス」という言葉の成り立ちや由来について解説
レジリエンスの語源はラテン語の「resilire(跳ね返る)」で、17世紀に英語圏で「弾力性」を意味する科学用語として誕生しました。19世紀には物理学において「外力を受けても元の形状に戻る能力」を示す専門語として使われ、その後心理学へ転用された歴史があります。
心理学分野では1970年代、米国の発達心理学者エミー・ワーナーが「困難な家庭環境で育ってもしなやかに成長する子ども」を研究し、初めてレジリエンスを人間の特性として定義しました。この視点が現代のメンタルヘルスや教育への応用の礎となりました。
現在では「複雑で変化の速い社会システム全体がショックから復元する力」という広義の意味も持つようになり、環境学・都市計画・ITセキュリティなど多岐にわたる分野で使用されています。
「レジリエンス」という言葉の歴史
レジリエンスは物理学用語から心理学概念へと移行した後、1990年代のポジティブ心理学ブームで一気に注目されました。特に米国同時多発テロ(2001年)以降、社会的トラウマの克服に関する研究が活発化し、レジリエンスの実証的データが蓄積されました。
東日本大震災(2011年)を契機に日本でも「地域レジリエンス」や「防災レジリエンス」という語が行政文書に登場し、国土強靱化のキーワードとなりました。同時期に企業経営でもサプライチェーンの強化やBCP(事業継続計画)の文脈で用いられ、日常語として浸透しました。
2020年代にはパンデミック対応で再び脚光を浴び、テレワークや教育現場のICT化を支える考え方として取り入れられています。歴史的に見ると、社会が大きな危機に直面するたびにレジリエンスという言葉の需要が高まり、そのたびに定義や応用範囲が拡張されてきました。
「レジリエンス」を日常生活で活用する方法
日常生活でレジリエンスを育むためには、まず自己認識を高めることが重要です。具体的には「ストレスを感じた状況を言語化し、感情を客観視する」習慣をつけると、回復の糸口が見えやすくなります。
次に、信頼できる人間関係を築き、困ったときに相談できるネットワークを確保することが、レジリエンス向上の最も有効な方法とされています。週に一度でも友人や家族とポジティブな会話を交わすだけで、心理的なバッファーが形成されることが研究で示されています。
さらに、十分な睡眠・適度な運動・バランスの取れた食事は、心と体の復元力を支える基本条件です。小さな成功体験を積み重ねる「スモールステップ戦略」や、マインドフルネス瞑想で感情の波を観察する技法も有効とされています。
「レジリエンス」についてよくある誤解と正しい理解
レジリエンスは「強がり」や「我慢強さ」と同一視されることがありますが、本質的には柔軟な思考と適切な助けを求める行動を含む概念です。「弱音を吐かない人=レジリエンスが高い」という誤解は、むしろメンタルヘルスを悪化させる原因となります。
また、レジリエンスは生まれつき決まっているという誤解も根強いですが、研究では後天的なトレーニングや環境整備で大きく向上することが示されています。例えば認知行動療法を取り入れたプログラムでは、ストレス対処能力が平均20〜30%改善したという報告があります。
「困難を乗り越えれば自動的にレジリエンスが高まる」というのも誤りです。経験を振り返り、意味づけを行い、学びを抽出するプロセスを経て初めて内在化されるため、「経験の質」と「振り返りの質」が鍵になります。
「レジリエンス」という言葉についてまとめ
- レジリエンスは逆境から素早くしなやかに立ち直る力を示す概念。
- 読み方は「レジリエンス」で英語の“resilience”が語源。
- ラテン語の「跳ね返る」が起源で、物理学から心理学へと拡張した歴史を持つ。
- 現代では個人・組織・社会で活用され、支援ネットワークとセルフケアが重要。
レジリエンスは一時的な気合ではなく、柔軟な思考や人間関係、適切な休息といった複数の要素が組み合わさった総合的な適応力です。読み方や成り立ちを理解することで、単なる流行語ではなく学術的背景を持つ重要概念であることがわかります。
歴史を振り返ると、社会が大きな危機に直面するたびにレジリエンスは進化してきました。今後も私たちが不確実な世界を生き抜くうえで、レジリエンスを意識的に培い、互いに支え合う姿勢が求められるでしょう。