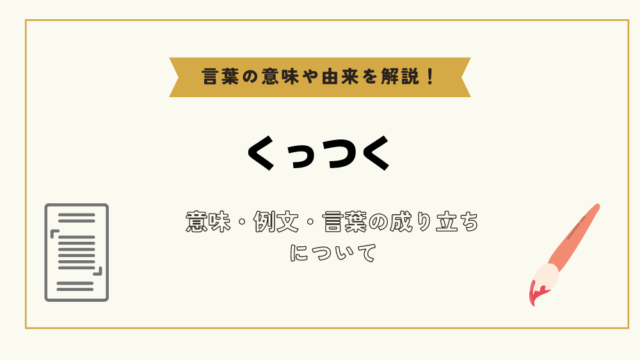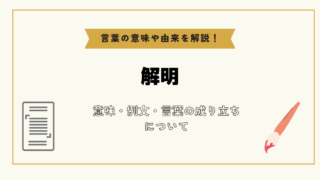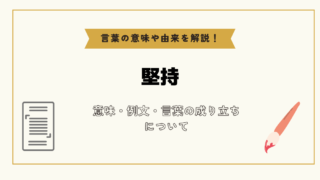Contents
「僭越」という言葉の意味を解説!
「僭越」とは、謙虚さをもって他人と比べて出し抜こうとすることや、自分の地位や権限を超えて他人と同じようなことをすることを指します。
つまり、自分が本来持っていない権限や地位を持つような振る舞いをすることを表現した言葉です。
この言葉は、謙虚さや適切な範囲での行動を大切にする日本の文化において、よく使われます。
「僭越」の読み方はなんと読む?
「僭越」は、「せんえつ」と読みます。
一つ目の「せん」は平仮名の「せん」と同じ音で、「えつ」は「え」と「つ」を合わせた音です。
「せんえつ」という読み方で、この言葉を使うことが一般的です。
「僭越」という言葉の使い方や例文を解説!
「僭越」という言葉は、自分の地位や立場を超えて他人よりも優れた立ち振る舞いをすることを指します。
例えば、自分が新入社員であるのにも関わらず、経験豊富な先輩社員の意見に対して自己主張をする場合、「僭越」と言えます。
この言葉は、謙虚さや礼儀を欠いている態度を表す際にも使用されます。
「僭越」という言葉の成り立ちや由来について解説
「僭越」という言葉は、中国の古典文献である「易経」から派生したものです。
中国では、自分の地位や権限を越えて他人と同じような振る舞いをすることは、大変失礼であるとされてきました。
日本においても、この考え方が受け継がれ、鎌倉時代以降の文献に「僭偽(せんぎ)」という表現が見られますが、現在の「僭越」という表現に近い意味で使われるようになったのは江戸時代以降と考えられます。
「僭越」という言葉の歴史
「僭越」の言葉は、古くは中国の文献に見られますが、日本においては鎌倉時代以降から使用されるようになりました。
特に、江戸時代には謙虚さや節度を大切にする精神が重要視され、この言葉も広く認知されるようになりました。
現代でも「僭越」の意味や使い方は、日本人の多くに共有されています。
「僭越」という言葉についてまとめ
「僭越」という言葉は、自分の地位や権限を超えて他人よりも優れた立ち振る舞いをすることを指します。
謙虚さや適切な範囲での行動を大切にする日本の文化において、この言葉はよく使われます。
読み方は「せんえつ」といいます。
中国の古典文献から派生した言葉であり、鎌倉時代以降、日本でも広まってきました。
現代でも、「僭越」の意味や使い方は広く認知されています。