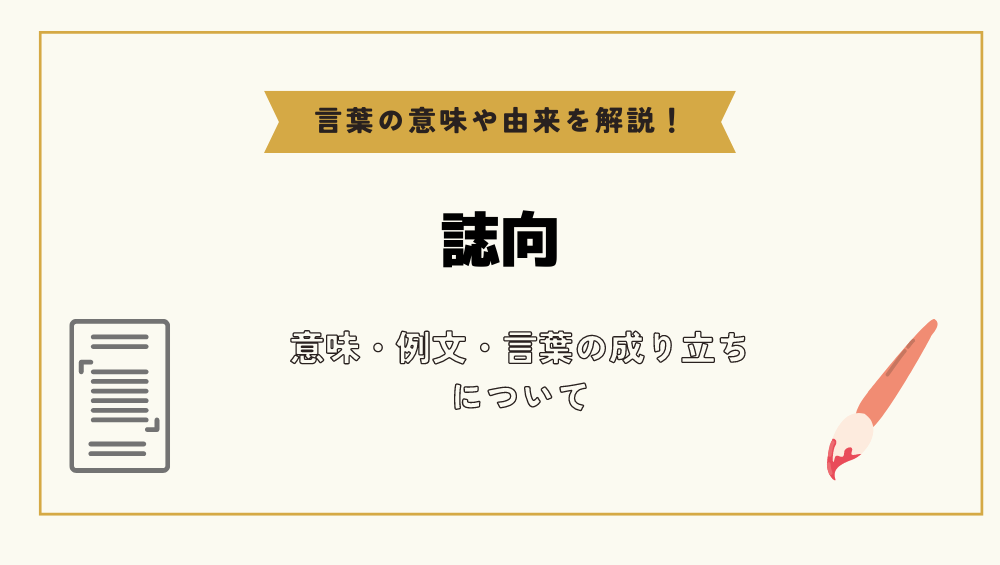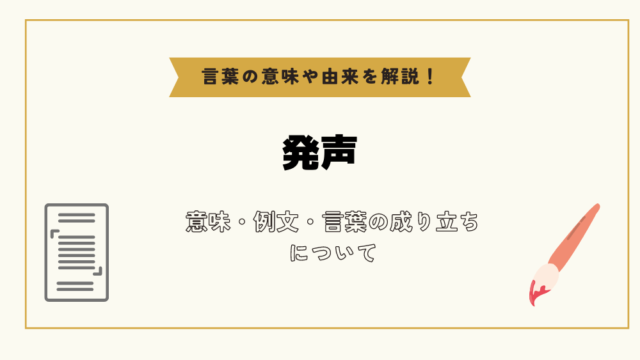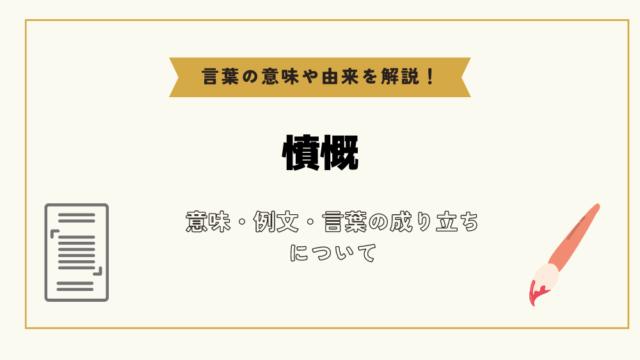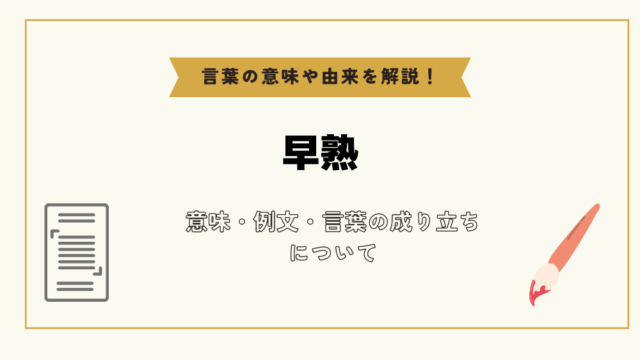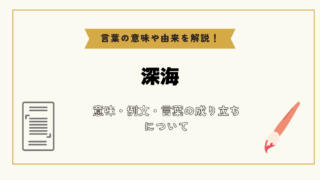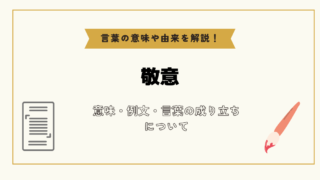「誌向」という言葉の意味を解説!
「誌向(しこう)」は、出版・編集の現場で「雑誌が目指す方向性や編集方針」を示す専門的な言葉として使われるのが最も一般的です。この語は一般的な国語辞典には掲載されておらず、あくまで業界内の実務用語として存在しています。たとえばファッション誌であれば「若年層のライフスタイルを誌向とする」といった具合に、ターゲット読者層や内容の軸を示す際に利用されます。つまり雑誌が「誰に」「何を」届けるかというコンセプトの核心部分を説明するときに欠かせないキーワードなのです。
出版以外ではほとんど見かけないため、日常語と誤解するケースもあります。特に「志向」「指向」との混同が多く、文字変換の際に誤って入力される例も少なくありません。業界関係者にとっては常識的な単語ですが、読者や新人編集者には意味が通じないこともあるので、文脈に応じた補足説明が重要です。
編集会議では「誌向がぶれると読者が離れる」という警句まで存在します。誌向は誌面全体のトーンから扱う企画、写真やフォントの選定に至るまで影響を与えるため、一度定めたら簡単には変えられない指針と考えられています。
業界誌・社内報などでも用いられますが、そこでは「業界人向けの実務情報を誌向とする」など、より限定された読者像に特化します。なお書籍編集ではほぼ使われず、雑誌特有の連続性や定期発行の性質と深く結び付いている点が特徴です。
「誌向」の読み方はなんと読む?
「誌向」は音読みで「しこう」と読みます。頻出する「志向」「指向」と同じ発音のため、口頭では区別が付きません。そのため会議や電話連絡では「雑誌の誌に向かうと書いて誌向」と説明することが一般的です。
読み誤りとして最も多いのが「しむき」ですが、これは誤読なので注意しましょう。とくに新人ライターや校正者にとっては「誌」という字から「雑誌=マガジン」というイメージが先行しがちで、意味と発音が結びつきにくいのが実情です。
漢字としては「誌(し)」が常用漢字外というわけではないため、パソコンやスマホの変換で問題なく入力できます。ただし「志向」「指向」との変換候補が同列に並ぶため、誤入力を未然に防ぐためには確定前に文脈を必ず確認するクセを付けると安心です。
「誌向」という言葉の使い方や例文を解説!
使い方は「雑誌が目指す方向性や編集方針を示す名詞」としての用法が中心です。動詞的に扱う場合は「〜を誌向とする」「誌向を定める」の形で用いられます。
【例文1】新創刊のライフスタイル誌は「サステナブルな暮らし」を誌向として掲げている。
【例文2】誌向が曖昧なまま企画を量産すると、読者層が散漫になりやすい。
ポイントは「誰に向けて・何を伝えるか」というコンセプトレベルの内容を指す点で、単なる「テーマ」や「特集」とは異なるということです。誌向は中長期的に雑誌のアイデンティティを決める要素であり、毎号のトピックよりも一段上位に位置付けられます。特集タイトルや連載枠だけを見て誌向を判断するのではなく、創刊号の巻頭言や企画意図書に記載されるケースが多いのも特徴です。
誤用例としては「誌向を変えた特集を組む」といった表現が挙げられます。正しくは「誌向に沿った特集を組む」または「誌向を刷新するため特集を組む」のどちらかを選ぶ必要があります。
「誌向」という言葉の成り立ちや由来について解説
「誌向」という表記は、雑誌を意味する「誌」と方向を示す「向」からなる合成語です。一般的な国語辞典に掲載がない理由は、出版業界の内部で自然発生的に使われはじめた「現場語」であるためと考えられています。
成り立ちの背景には、1970年代以降に多様化した専門誌・ムックが急増したことで、編集方針を端的に示す言葉が求められた事情があります。当時の編集会議資料や創刊企画書を調べると、「誌向(しこう)を明確にすること」というフレーズが散見され、そこから定着したと推測されています。
「誌」は古来「しるす」「ふみ」といった意味を持ち、江戸期から「雑誌」の語に用いられてきました。「向」は「むかう・方向性」などを示す常用漢字です。両者の組み合わせ自体はいわゆる熟字訓ではなく、意味的にも素直な合成と言えます。
なお古い活版印刷の技術書には「誌向性」という語も登場し、「雑誌らしさを志向する」というニュアンスで説明されています。ただし現在は「誌向」に一本化される傾向が強いです。
「誌向」という言葉の歴史
「誌向」という語が文献上確認できる最古の例は、昭和55年(1980年)発行の編集実務書『月刊誌創刊マニュアル』とされています※1。この書籍では「創刊前に誌向を可視化せよ」という表現が使われており、当時から専門用語として認識されていたことがわかります。
1980〜90年代にかけて、情報誌ブームにより新創刊が相次ぎました。その過程で「誌向の明確化」が成功・失敗を分ける要因として語られ、多くの編集者が口にするキーフレーズになりました。インタビュー集『編集現場の証言』(1994年)でも複数の編集長が誌向の重要性を語っています。
2000年代に入るとWebメディアの台頭で雑誌市場が縮小しますが、逆にニッチな読者を狙う専門誌が増加し、誌向の定義づけはさらにシビアになりました。近年の編集指南書では「誌向=ブランドアイデンティティ」と同義で扱われることも多く、マーケティング用語と接近した解釈が見られます。
こうした流れからわかる通り、「誌向」は40年ほどの歴史を持ちながらも、常に出版業界の変化に伴って意味の輪郭を広げてきた言葉だと言えるでしょう。
「誌向」の類語・同義語・言い換え表現
「誌向」と似た意味を持つ語として最も一般的なのが「編集方針」です。どちらも雑誌の方向性を示しますが、編集方針はより広い文脈で使える汎用語です。
次に「メディアポジショニング」も近しい概念として挙げられます。こちらはマーケティング領域の用語で、ターゲット市場における立ち位置を明確にすることを意味します。
出版現場では「冊子コンセプト」「誌面スタンス」「誌面指向」など、ニュアンスの近い言い換えが多数存在します。ただしこれらは厳密には微妙な温度差があり、誌向は「編集哲学」にも踏み込む深さが特徴です。
カジュアルな場面では「カラー(誌のカラー)」という言い方も用いられますが、抽象度が高いため正式な企画書では避けられる傾向にあります。
「誌向」と関連する言葉・専門用語
関連用語の筆頭は「ターゲット読者像」です。これは誌向を考える際に必ずセットで定義される要素で、年齢・性別・職業・趣味嗜好などを具体的に設定します。
「ペルソナ設計」も重要なキーワードで、一人の典型的読者像を細かく設定することで誌向を具体化する手法として活用されます。
さらに「ラダリング」「編集マトリクス」などのマーケティング手法は、誌向を視覚的に整理しチーム全体で共有するためのツールとして用いられます。これにより企画と誌向のズレを早期に発見できるメリットがあります。
他には「トーン&マナー」「ブランドガイドライン」も誌向と密接に絡み、写真の色調やコピーの文体にまで統一感を持たせる役割を果たします。
「誌向」を日常生活で活用する方法
「誌向」は専門用語ですが、個人ブログやSNS運営でも応用が可能です。自分の発信が「誰に・何を伝えたいのか」を明確にすることで、内容のブレを防げるからです。
【例文1】旅行系ブログでは「初めて海外旅行する20代女性」を誌向(=発信方針)に設定する。
【例文2】料理動画チャンネルは「共働き家庭が15分で作れる晩ご飯」を誌向に掲げている。
このように誌向を意識すると、コンテンツの質と読者満足度が向上し、結果としてファンが増える好循環が生まれます。会社の広報誌や社内報でも誌向を定義することで、社員のニーズに合った情報提供ができ、エンゲージメント向上につながります。
注意点は、誌向を細かく決めすぎるとテーマが限定されてネタ切れを起こしやすいことです。定期的に読者アンケートやアクセス解析を用いて、誌向と実際の読者ニーズのギャップをチェックすると良いでしょう。
「誌向」についてよくある誤解と正しい理解
よくある誤解の第一は「誌向=特集テーマ」という思い込みです。特集は毎号変わる短期的な話題であり、誌向は中長期にわたる指針という点でまったく異なります。
第二の誤解は「誌向は編集長だけが考えるもの」という先入観です。実際には営業やマーケティング、場合によっては印刷・流通部門も含めて議論し、総合的に決定されます。
第三の誤解として「誌向を変える=読者離れが必ず起こる」と語られますが、実際にはリニューアルによって新規読者を獲得した成功例も多数あります。ただし変更時には既存読者への説明や段階的な移行が不可欠です。
正しい理解のポイントは「誌向はブランドのコアだが、社会環境や読者ニーズに合わせて微調整する柔軟性も必要」というバランス感覚にあります。
「誌向」という言葉についてまとめ
- 「誌向」とは雑誌が目指す方向性や編集方針を示す出版業界の専門用語。
- 読み方は「しこう」で、「雑誌の誌」に「向かう」で表記される。
- 1970年代後半の専門誌ブームを背景に現場で生まれ、現在も使用されている。
- 使用時は「志向」「指向」との混同に注意し、文脈に応じて補足説明を行う。
まとめとして、「誌向」は一般の辞書には載っていないものの、出版編集の現場では欠かせないキーワードです。雑誌の個性を決める上位概念であり、読者像や企画内容、デザインの方向性を包括的に束ねる役割を果たします。
正式な読みは「しこう」で、同音異義の「志向」「指向」との区別がポイントになります。誤入力・誤読を防ぐには、「雑誌の誌」と明示する習慣が有効です。
歴史的には昭和後期に登場し、その後の情報誌ブームやWeb時代を経てもなお生き残った言葉であることから、実務的価値の高さがうかがえます。
最後に、専門用語だからこそ正確な意味と使い方を押さえ、企画書や会議で的確に用いれば、チーム全体の認識統一と読者満足度向上に大きく貢献できるでしょう。