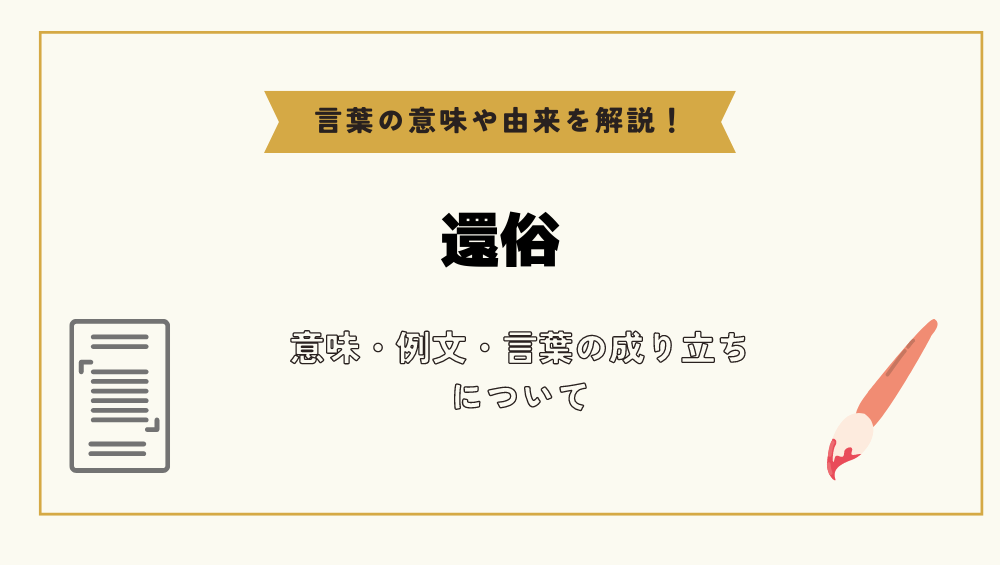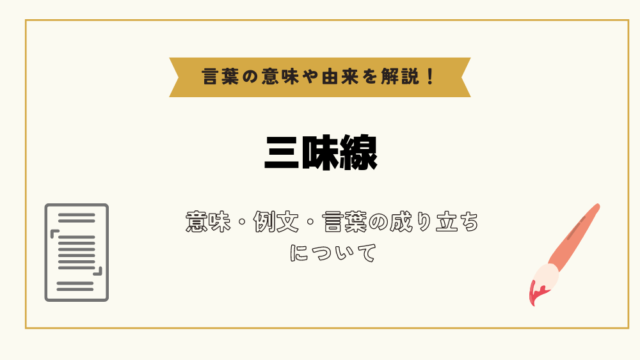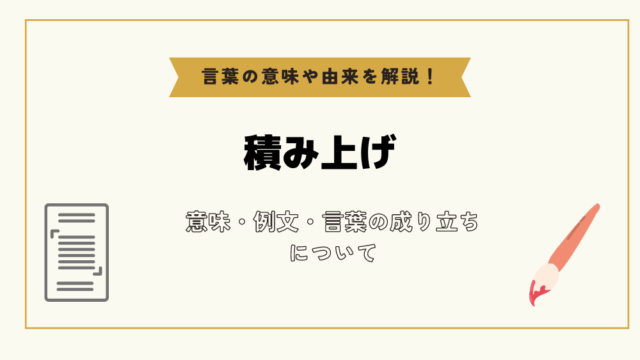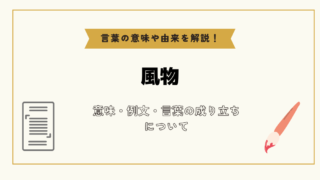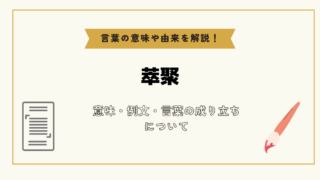Contents
「還俗」という言葉の意味を解説!
還俗(かんぞく)とは、仏教の修行者や僧侶が出家した身分から普通の生活者に戻ることを指す言葉です。出家は仏教の教えに基づき、世俗的な欲望から離れ精神的な修行に励むために行われるものですが、変心や衝動的な決断などにより修行を途中で断念する場合にも使われます。
還俗は、一度出家することで修行に努めた後、宗教的な活動や献身的な生活を続けずに、元の日常生活に戻ることを意味します。このような人々は、家族や友人たちと同じように働き、家庭を持ち、社会的な義務を果たしていきます。
還俗をする理由は、人生の目標や価値観が変化したり、家庭や社会への責任を果たす必要性を感じたりすることが一般的です。出家は精神的な追求に従事する生活であり、それがいつまでも続けられるわけではありません。そのため、還俗は出家者自身の意思に基づいて行われるのが一般的です。
「還俗」という言葉の読み方はなんと読む?
「還俗」という言葉は、かんぞくと読みます。漢字の読み方をそのまま読むという形になります。
「還」は「かえ(る)」とも読みますが、この場合は「かん」と読みます。「俗」は「俗世」(ぞくせ)とも読みますが、こちらも「ぞく」と読みます。それぞれの漢字の意味を考えると、仏教の修行から世俗の世界に戻ることを意味していることがわかります。
「還俗」という言葉の使い方や例文を解説!
「還俗」という言葉は、主に仏教や出家に関連した文脈で使われます。「還俗する」「還俗者」「還俗活動」といったように使われることが一般的です。
例文:
- 。
- 彼は長年の出家生活に別れを告げ、還俗を選びました。
- 還俗者たちは社会的な義務を果たしながら、日常の生活を送っています。
- 彼女の還俗後は、家族との絆がより深まりました。
。
。
。
。
「還俗」は、出家者が元の普通の生活に戻ることを表す言葉です。この言葉は特定の宗教的な文脈で使用されることが多く、そのままの意味で一般的な会話や文章では使われることはあまりありません。
「還俗」という言葉の成り立ちや由来について解説
「還俗」という言葉は、中国の仏教に由来します。中国では、仏教の修行者や僧侶が出家した後に普通の人々の生活に戻ることを「還俗」と言います。
「還」はもともと「帰る」という意味で、出家者が元の生活に戻ることや帰還することを表しています。「俗」は「世俗」とも読み、出家者が世間の人々と同じように一般的な生活を送ることを指します。
中国の仏教が広まるにつれ、出家者の一部は修行に限界を感じたり、家族や社会への責任を果たす必要性を感じるようになりました。そのため、「還俗」の概念が生まれ、仏教の教えの中で出家と還俗が対比されるようになったのです。
「還俗」という言葉の歴史
「還俗」という言葉の歴史は古く、中国の仏教が起源です。仏教は中国に初めて伝えられた時から、出家と還俗の二つの生活様式が存在していました。
出家は、庶民が世俗の束縛から解き放たれ、修行に専念するために行うものでした。しかし、出家者の中には修行に限界を感じる者や家族への責任を果たしたいと考える者もいました。彼らは還俗を選択し、普通の生活に戻りました。
こうした出家と還俗の二つの生活様式は、中国の仏教教義の中で存在感を持っていました。また、出家者の還俗には多様な理由や背景があるため、個々の出家者の体験や決断によってさまざまな歴史が生まれました。
「還俗」という言葉についてまとめ
「還俗」という言葉は、出家した仏教の修行者や僧侶が元の生活に戻ることを指します。出家者の中には修行に限界を感じたり、家族や社会への責任を果たしたいと考える者がいるため、還俗が行われます。
「還俗」は、特定の宗教的な文脈で使われることが多く、一般的な会話や文章ではあまり使用されません。しかし、仏教の教えや出家者の生活に興味を持つ人々にとっては、興味深い言葉であり、日常的な用語としても理解されています。