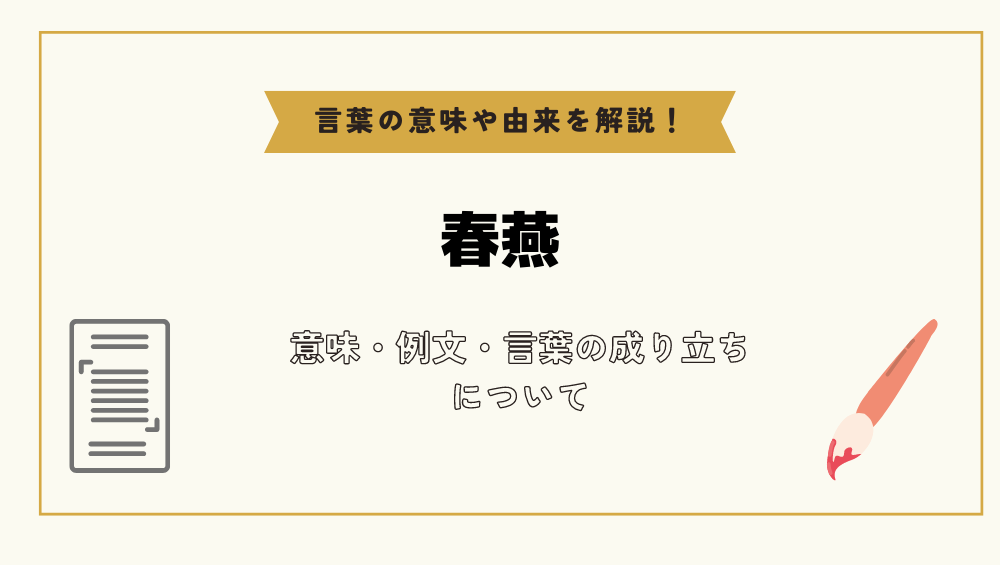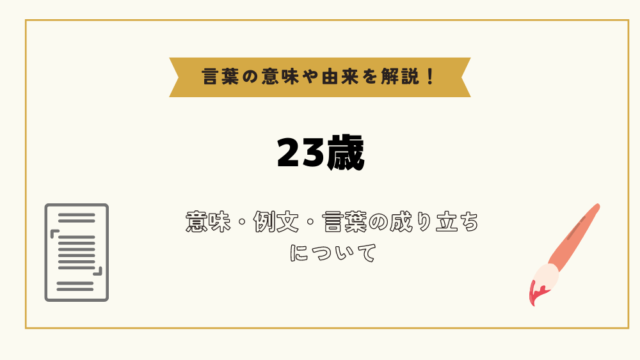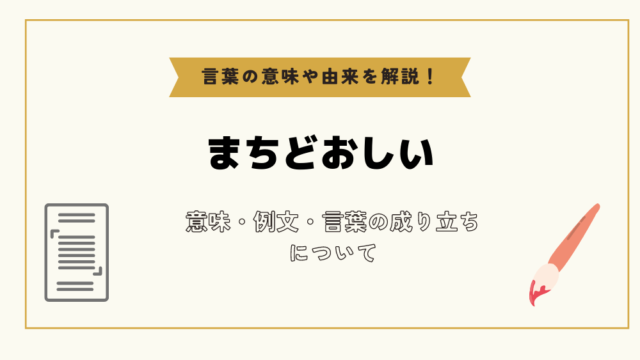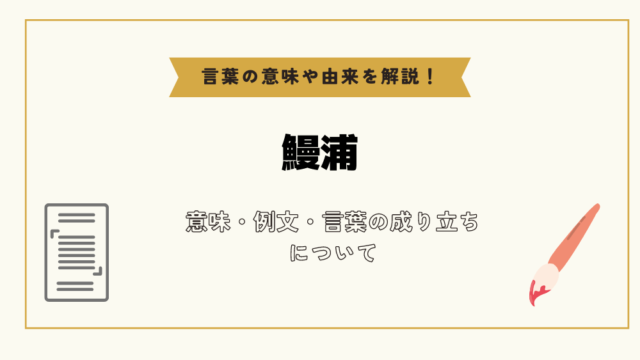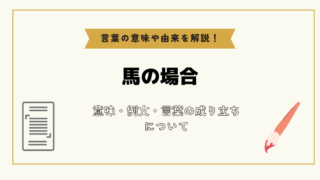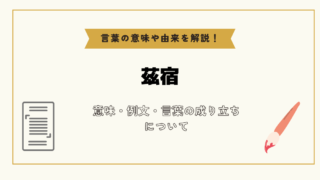Contents
「春燕」という言葉の意味を解説!
「春燕」という言葉は、日本語で「春に飛来するツバメ」という意味を持ちます。ツバメは春になると遠くからやってきて、夏になるとまた旅立って行く姿が美しいと評されています。
ツバメは春の象徴として、新しい季節の始まりや冬からの解放を表しています。春燕は、その美しいツバメの姿を指して使われることが多く、春の訪れや生命の息吹を感じさせる言葉として愛されています。
ツバメのように、春燕は新たな始まりや希望を象徴する言葉なのです。
「春燕」という言葉の読み方はなんと読む?
「春燕」という言葉は、「しゅんえん」と読みます。なめらかで優しい響きがあり、春の訪れを感じさせるような読み方です。
「春燕」という言葉の使い方や例文を解説!
「春燕」という言葉は、主に詩や文学作品などで使用されることが一般的です。例えば、「春燕の飛来に心が躍る」といった表現がよく見られます。
このように「春燕」という言葉は、春の訪れや新しい始まりに対しての喜びや期待感を表現するために使用されます。日本の古典文学にもしばしば登場する言葉であり、その美しい響きが文学作品に彩りを与えています。
「春燕」という言葉の成り立ちや由来について解説
「春燕」の成り立ちや由来については明確には分かっていませんが、おそらくツバメという鳥の美しい姿と春の到来とを結びつけた表現として生まれたのでしょう。
ツバメは春になると他の場所からやってきますが、その飛来のタイミングが春の訪れと重なることから、「春燕」という言葉が生まれたのかもしれません。古くから日本人は春になるとツバメの飛来を喜び、その姿を詩や歌に詠み込んできました。
「春燕」という言葉の歴史
「春燕」という言葉は、日本の古典文学や俳句、和歌などでよく見られる表現です。その歴史は古く、平安時代から詠み込まれることがありました。
ツバメは春の象徴とされ、春の到来を告げる存在として大切にされてきました。そのため、春の季節になると「春燕」という言葉が多く使用されるようになりました。今でも、日本人の心に春の訪れを伝える言葉として、多くの人々に愛され続けています。
「春燕」という言葉についてまとめ
「春燕」という言葉は、春に飛来するツバメを指し、春の到来や新しい始まりを象徴する言葉です。日本の古典文学や詩歌に頻繁に登場し、その美しい響きが文学作品に彩りを与えています。
ツバメのように自由に空を舞う姿は、春の訪れや新たな始まり、希望を感じさせます。「春燕」の言葉は、そんな明るい気持ちを表現するために使われ、多くの人々に親しまれています。