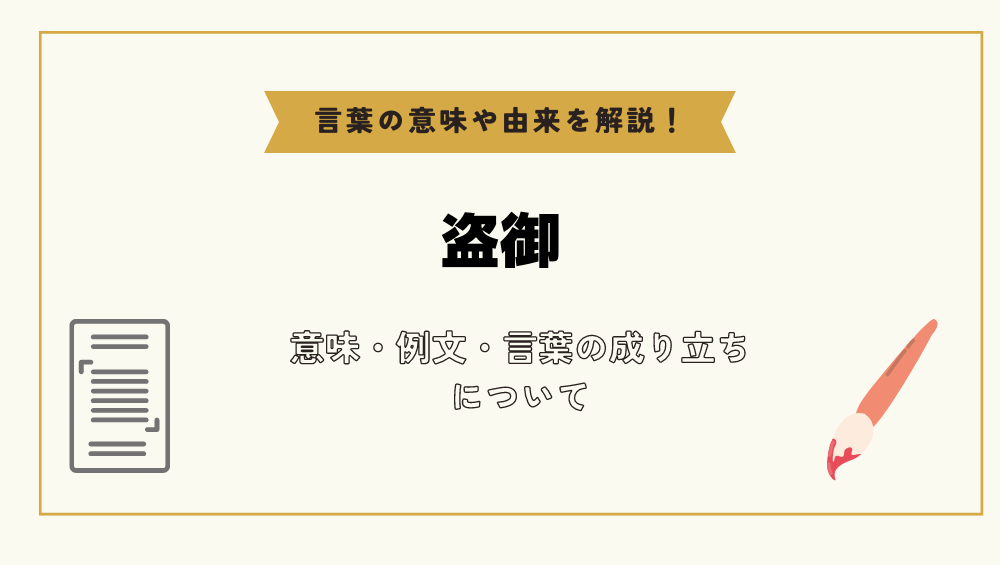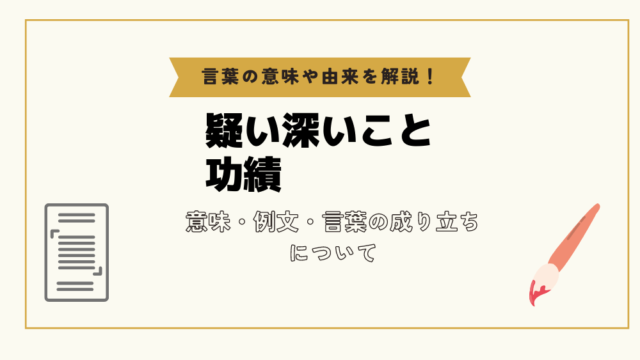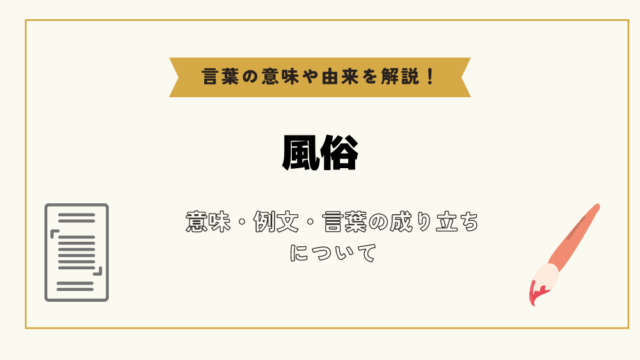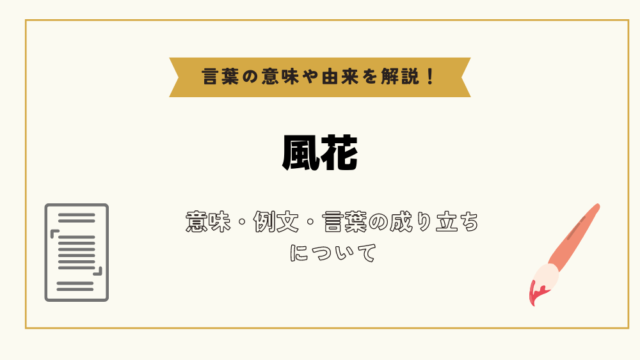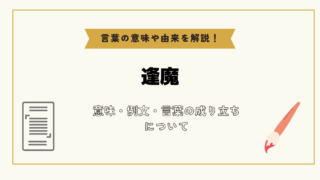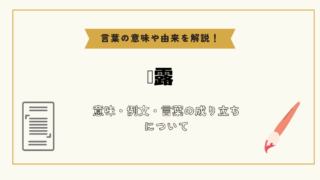Contents
「盗御」という言葉の意味を解説!
「盗御(とうぎょ)」という言葉は、日本語において「盗みのしょうじょう」「盗みの行為」を指す表現です。
これは、他人の財産を不正に持ち去る行為を意味しています。
「盗御」という言葉の読み方はなんと読む?
「盗御」という言葉は、「とうぎょ」と読みます。
漢字の「盗」は「ぬすむ」と読むことから、「とう」という読み方が一般的です。
「御」は「ご」と読むことが一般的ですが、「盗御」の場合は「ぎょ」と読まれます。
「盗御」という言葉の使い方や例文を解説!
「盗御」という言葉は、犯罪的な意味合いを持つため、日常会話ではあまり使用されません。
しかしながら、警察や司法関係者、法律に関係する専門家などが使用することがあります。
例えば、「彼は盗御の容疑で逮捕された」というように使われることがあります。
「盗御」という言葉の成り立ちや由来について解説
「盗御」という言葉の成り立ちは、漢字の組み合わせによって形成されています。
「盗」は「ぬすむ」という意味で、不正な行為である「盗み」を表します。
「御」は丁寧な言葉遣いを示す接頭辞であり、敬意を表す目的でも使われます。
これにより、「盗御」という言葉は他人の財産を不正に持ち去る行為に対する厳重な非難や警戒感を含みます。
「盗御」という言葉の歴史
「盗御」という言葉の歴史は古く、日本の文学作品や史書にも見受けられます。
贅沢や不正の象徴として描かれることが多く、盗みに対する社会的な非難や罪悪感を表現する言葉として使われてきました。
現代においても、「盗御」という言葉は非行行為として忌避され、厳しく罰せられるべきであるとされています。
「盗御」という言葉についてまとめ
「盗御」という言葉は、他人の財産を不正に持ち去る行為を指し、犯罪的な意味合いを持ちます。
読み方は「とうぎょ」であり、一般的な日常会話ではあまり使用されません。
その成り立ちは「盗」と「御」の組み合わせによっており、日本の文学や史書にも古くから存在しています。
現代でも非行行為として忌避され、厳しく罰せられるべきだとされています。