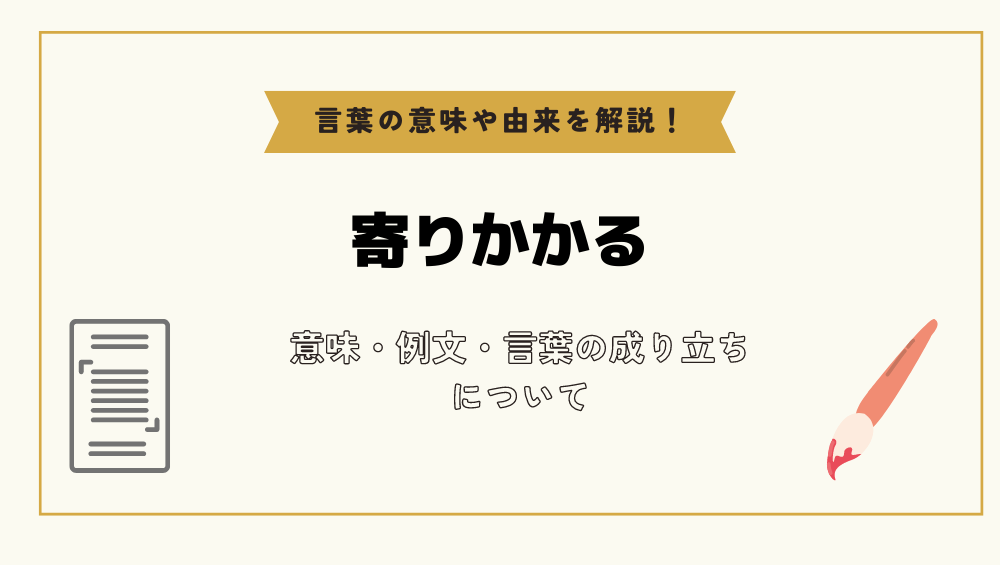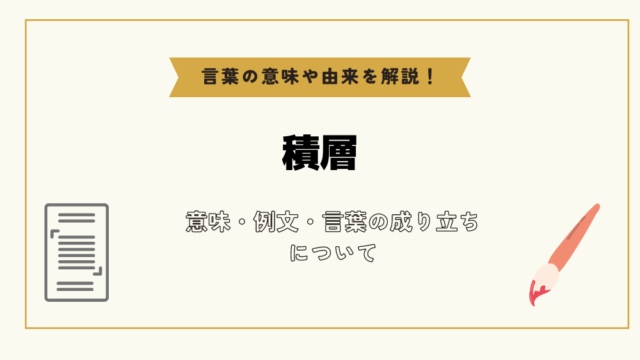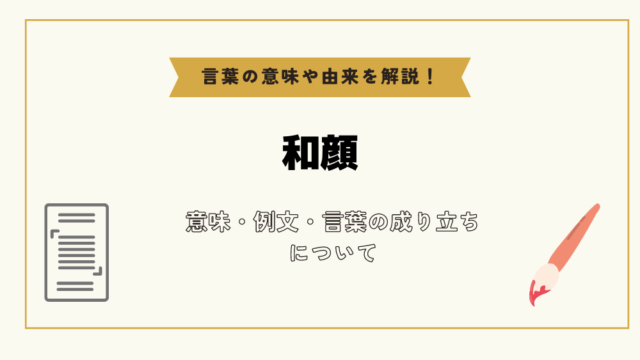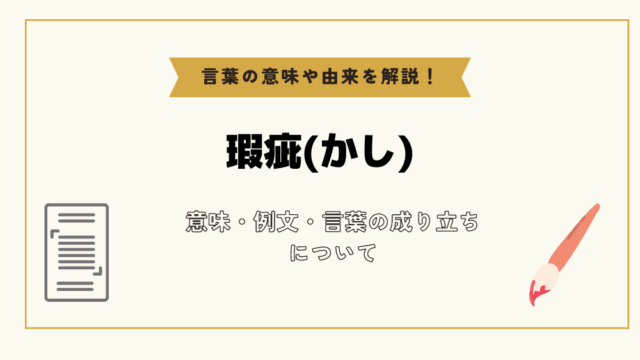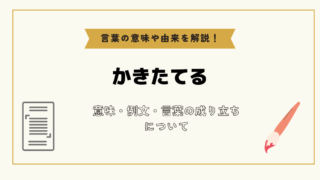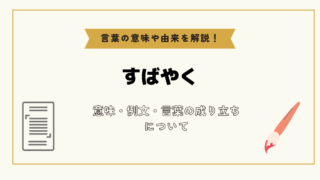Contents
「寄りかかる」という言葉の意味を解説!
「寄りかかる」とは、体を他の物に頼ませ、それに倒れるような状態になることを指します。
支えとなるものに身を委ね、安心感や安定感を得ることができます。
また、他人や物事に依存することで、心の支えになることもあります。
例えば、疲れた体を壁に寄りかけると、身体が安定しリラックスできるでしょう。
「寄りかかる」は身体的な意味だけでなく、心理的な意味も含まれます。
相手のサポートを受け、助けを求めることも「寄りかかる」の一つの形です。
「寄りかかる」という言葉の読み方はなんと読む?
「寄りかかる」は、読み方は「よりかかる」となります。
日本語の読み方である「よ」、「り」、「か」、「か」、「る」の音で表現します。
「寄りかかる」という言葉の使い方や例文を解説!
「寄りかかる」は、主に身体を他のものに頼ませる状態を表現する際に使用されます。
例えば、疲れている際に壁や椅子に寄りかかることで安心感や疲労回復を得ることができます。
また、心の中で他人や物事に頼る感情を表現する場合にも使用されます。
例えば、「あの人に相談してみようかな」と考えた場合、他人の力に寄りかかることで解決策を見つけることができるかもしれません。
「寄りかかる」という言葉の成り立ちや由来について解説
「寄りかかる」は、江戸時代に生まれた言葉として知られています。
当時、神社や寺院などで修行を積んでいた人々が、疲れた体を柱や壁に頼り、支えてもらうことで安心感を得ていました。
これが転じて、身体的な意味だけでなく、心の中でも他人や物事に頼るという意味に広がっていきました。
人間の本能的な欲求や安心感を表す言葉として、現代でも使われています。
「寄りかかる」という言葉の歴史
「寄りかかる」という言葉の由来は、江戸時代にさかのぼります。
当時は修行を積む人々が、疲れた身体を神社や寺院などの建物に頼り、支えられることで安心感を得ていました。
この意味が転じて、支えに頼ることや他人のサポートを求めることを表す言葉として使用されるようになりました。
時代とともに「寄りかかる」という言葉は広がり、現代の日本語においても使用され続けています。
「寄りかかる」という言葉についてまとめ
「寄りかかる」とは、他のものに頼り、身体や心を支えてもらうことを指します。
身体的な安定感や心の安心感を得ることができる表現であり、他人や物事に対して頼ることで問題解決や助けを求めることもあります。
「寄りかかる」という言葉は、江戸時代から日本語に存在している言葉であり、人間の本能的な欲求や安心感を表す重要な言葉として知られています。
現代の日本語においても幅広く使用されています。