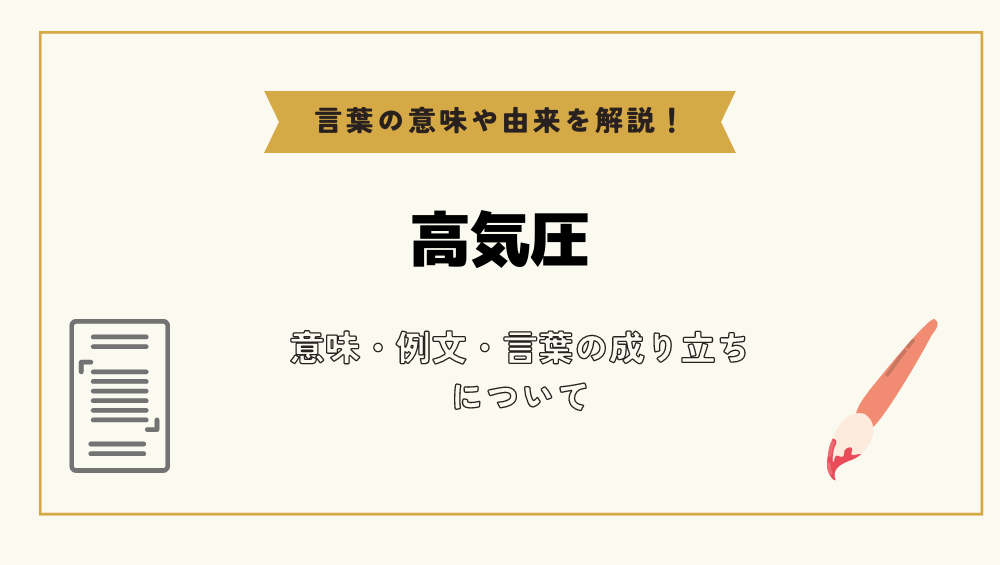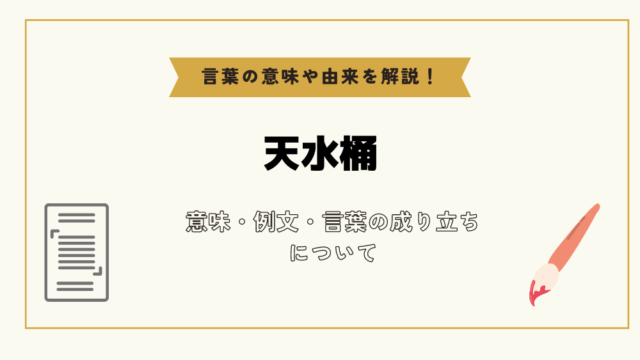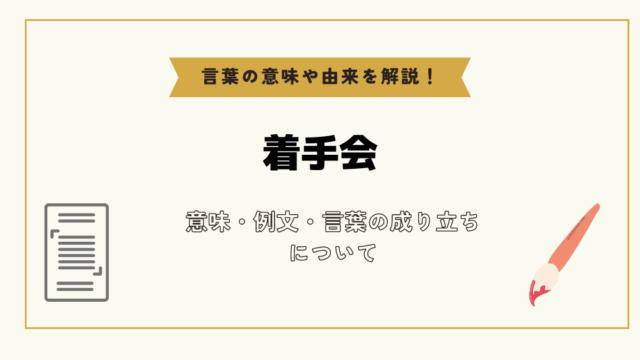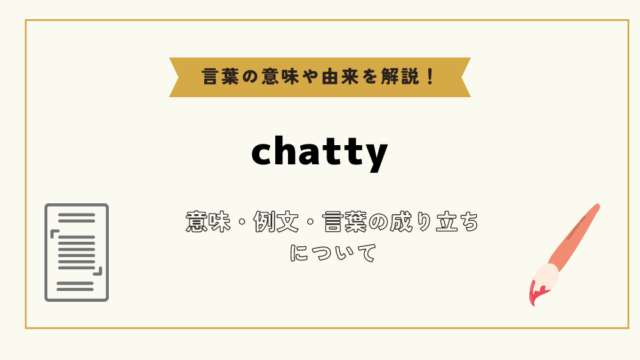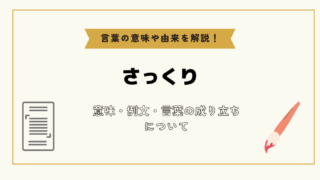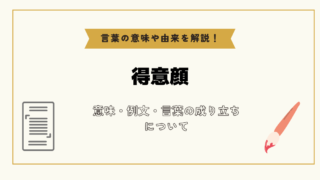Contents
「高気圧」という言葉の意味を解説!
「高気圧」という言葉は、大気の中で特定の地域において、周辺よりも気圧が高い状態を指します。大気の重さによって生じる気圧の違いにより、高気圧や低気圧などの気象現象が発生します。「高気圧」はその中でも気圧が高い状態を表し、周辺よりも空気が下方に圧力をかけている状態です。この高気圧の特徴は、晴れた天候や静穏な風の状態が多いことです。一般的には天気予報などで「高気圧が接近しています」という表現を聞くことがありますね。
「高気圧」という言葉の読み方はなんと読む?
「高気圧」という言葉は、日本語の「こうきあつ」と読みます。漢字の「高」と「気圧」を組み合わせた言葉で、そのまま読むことができます。読み方は難しくありませんので、覚えておくと便利ですね。
「高気圧」という言葉の使い方や例文を解説!
「高気圧」という言葉は、日本の気象予報や天気に関する話題でよく使われます。例えば、「今日は高気圧が流れ込んでおり、晴れた快晴の天気となるでしょう」や「週末は高気圧に覆われ、安定した天気が続く予想です」といった使い方があります。また、狭義では気象に関連した言葉ですが、広義では圧力や大きな力を意味する言葉としても使われることがあります。
「高気圧」という言葉の成り立ちや由来について解説
「高気圧」という言葉の成り立ちは、漢字の「高」や「気圧」という字面から理解することができます。気象学や気圧の概念自体は、古代ギリシャから研究が進められ、時代とともに発展してきました。日本語における「高気圧」という言葉自体も、西洋の気象学や学術の影響を受けて広まった言葉です。
「高気圧」という言葉の歴史
「高気圧」という言葉は、日本の気象学の歴史とも深く関わっています。気象庁や各地の気象台による観測データや予報が集約され、国民の生活や農業、交通などに役立つ情報として提供されてきました。例えば、夏の梅雨明けや秋の台風の発生時など、高気圧の変動が重要な要素となる場面もあります。また、航空や船舶などの運航業務においても、高気圧の予測や対策が大切な要素です。
「高気圧」という言葉についてまとめ
「高気圧」という言葉は、大気の中で気圧が高い状態を指す言葉です。晴れた天気や静穏な風が特徴であり、日本の気象予報や天気情報などでよく使われる言葉です。その成り立ちや由来は、気象学の発展や西洋の学術の影響を受けて広まったものです。高気圧の予測や対策は、私たちの日常生活や様々な産業において重要な要素となっています。