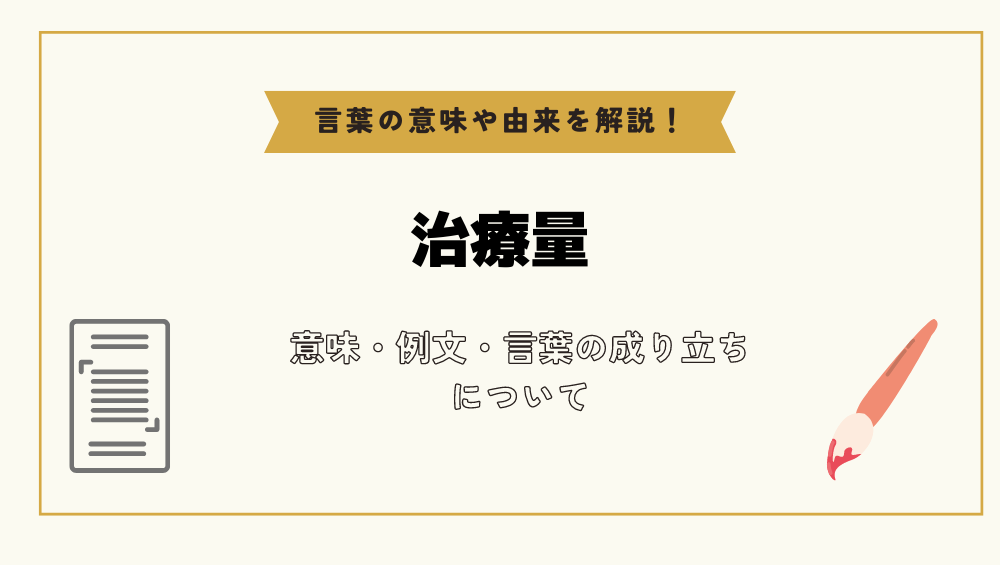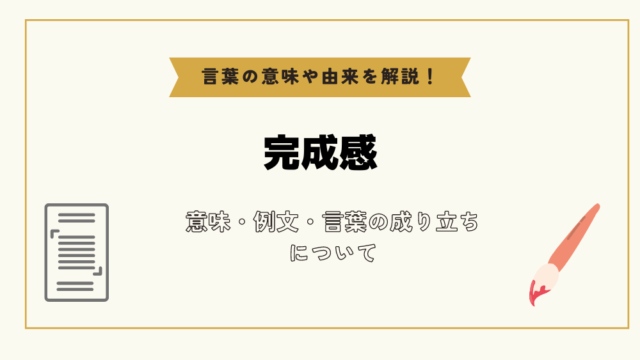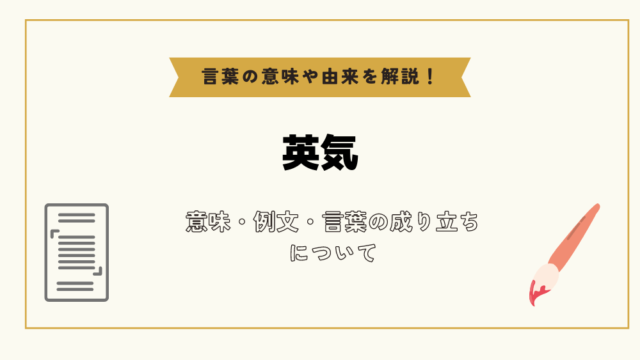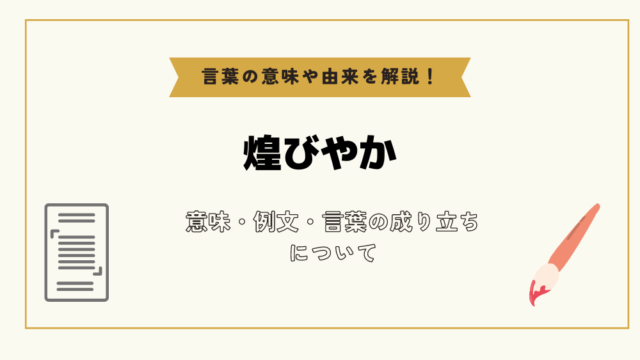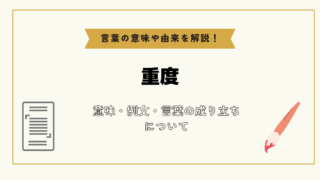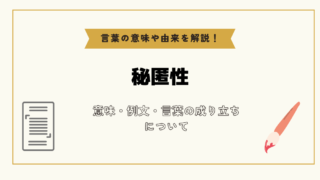Contents
「治療量」という言葉の意味を解説!
「治療量」という言葉は、医療や治療において使用される重要な概念です。
病気や疾患の治療に必要な薬剤や医療行為の総量を指す言葉であり、適切な量を使用することで効果的な治療が行われます。
治療量は、患者の状態や病状によって個別に定められます。
医師や薬剤師との相談の元、患者に最適な量が選ばれます。
例えば、抗生物質の場合、適切な治療量を使用しないと、病原菌の耐性が生じる可能性があります。
一方で、過剰な量を使用すると、患者に副作用や中毒症状が出る可能性があります。
「治療量」という言葉の読み方はなんと読む?
「治療量」という言葉は、「ちりょうりょう」と読みます。
読み方はシンプルで覚えやすいですね。
「治療量」という言葉の使い方や例文を解説!
「治療量」という言葉は、医療現場や薬剤師、患者とのコミュニケーションで頻繁に使用される言葉です。
具体的な使い方について解説します。
例文1:この薬の治療量は、1日3回飲んでください。
。
例文2:患者の体重や年齢に応じて、適切な治療量を調節します。
。
例文3:治療量を守らずに薬を使用すると、効果が出にくいことがあります。
「治療量」という言葉の成り立ちや由来について解説
「治療量」という言葉は、日本語で医療や治療を意味する「治療」と、量を表す「量」という単語から成り立っています。
医療分野では、どの程度の薬剤や医療行為が必要なのかを量的に評価することが重要です。
それが治療量として定着していったのです。
「治療量」という言葉の歴史
「治療量」という言葉は、医療の歴史と共に発展してきました。
昔の医療では、経験や感覚に基づいて薬剤や医療行為の量が決められることが多かったのですが、現代では科学的な根拠に基づいた治療量が求められています。
「治療量」という言葉についてまとめ
「治療量」という言葉は、医療現場や患者とのコミュニケーションで重要な役割を果たします。
正確な量を使用することで、効果的な治療が行われます。
治療量は、個別の患者の状態に合わせて定められ、医師や薬剤師との協力が必要です。
適切な治療量の使用は、患者の回復に大きく寄与します。
患者自身も正しく理解し、指示に従うことが重要です。