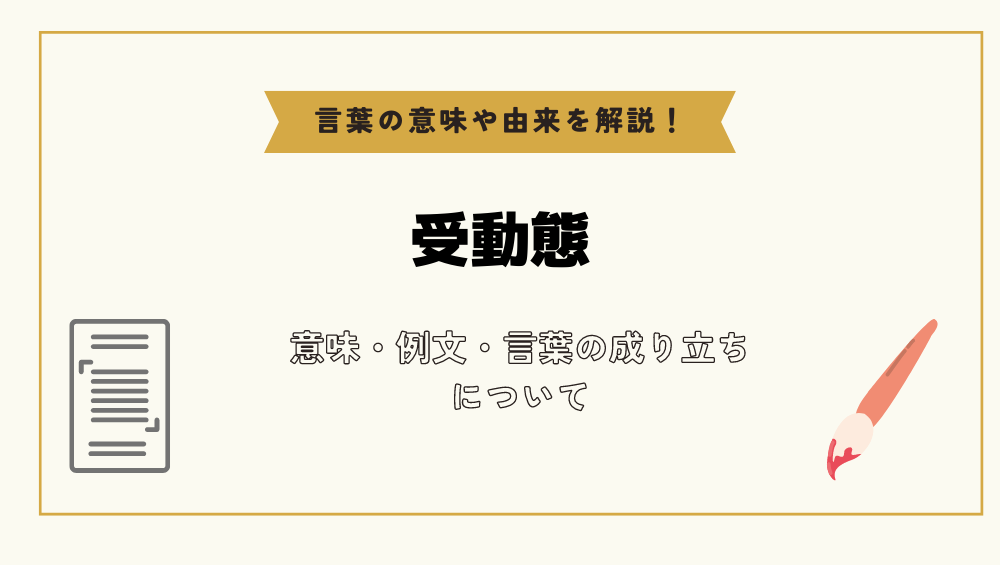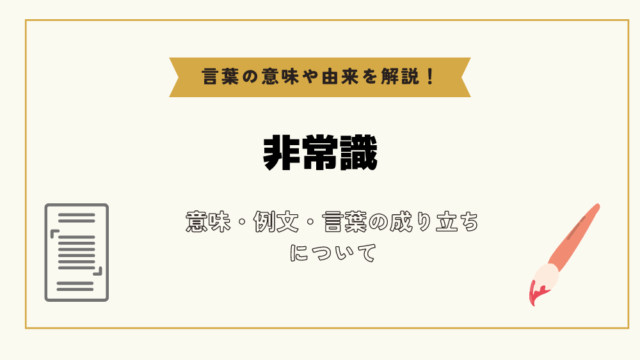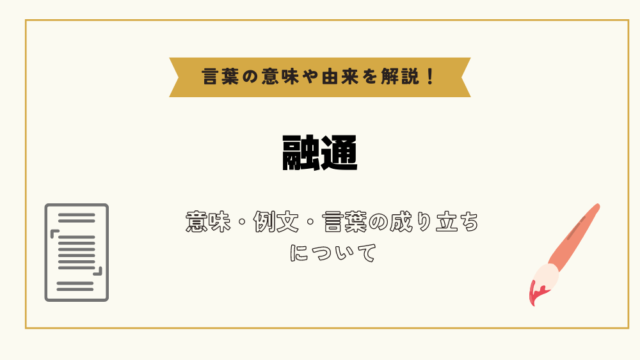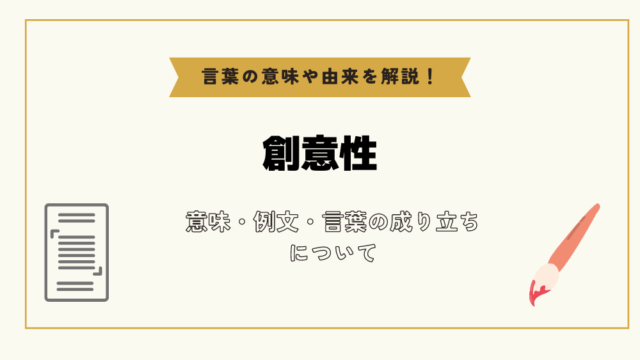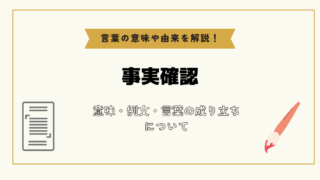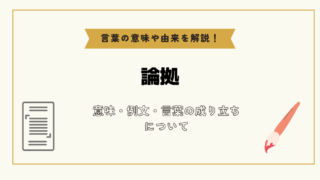「受動態」という言葉の意味を解説!
受動態とは「文の主語が動作の主体ではなく、動作を受ける立場に置かれる形」を指す文法上の用語です。この概念は英語・日本語をはじめ多くの言語に存在し、主語への注目度を高めたり、行為者をあえてぼかしたりする際に重宝されます。英語なら “be+過去分詞”、日本語なら「〜れる/〜られる」の形で示されるのが一般的です。能動態と対になることで、文章の視点を柔軟に切り替える役割を担います。
受動態は単に「行為者が省かれる形」ではありません。行為者(by+人、〜に)を明示した受動文も存在し、情報の焦点を「何が受けたか」に移すことが主目的です。「主語=被害者」というイメージだけでなく、中立的な客観報告や丁寧表現としても機能します。
日本語では尊敬表現と重なる場合があるため、受動態=被害・迷惑という誤解が根強いです。しかし実際には「発見される」「評価される」など肯定的な文脈でも広く使われます。言語ごとの制度は異なりますが、〈動作の方向性〉を主語へ向けるという核心は共通しています。
文章を書く際に受動態を適切に用いると、情報を客観的に提示したり、行為者をぼかして配慮したりできるため、ビジネス文書や学術論文では欠かせません。一方で多用すると主語が曖昧になり冗長になるので、能動態とのバランスを取ることが重要です。
「受動態」の読み方はなんと読む?
「受動態」は「じゅどうたい」と読みます。「受」は“受ける”、「動」は“動作”、「態」は“状態・様態”を意味し、三字で概念を端的に示しています。日常会話では「受動形(じゅどうけい)」とも呼ばれますが、学術書や教科書では「受動態」が一般的です。
英語教育の現場でも “passive voice” の訳語として「受動態」が定着しており、辞書や参考書にも必ず載る基本語です。かなで書く場合は「じゅどうたい」とひらがな表記しても問題ありませんが、正式原稿や学術論文では漢字表記が推奨されます。
読み方自体は難しくありませんが、「じゅうどうたい」と伸ばして発音する誤りが散見されます。中学校の文法授業で初めて耳にするケースが多いため、正しいアクセントとともに覚えておくと会話でもスムーズです。
また「受動的」という形容詞と混同しやすい点に注意しましょう。受動態=文法用語、受動的=性格・態度を表す一般語と区別しておくと誤解を避けられます。
「じゅどうたい」は音読みが続くため語感が硬めですが、文章解説では頻出するため発音・表記ともに迷わないようにしましょう。
「受動態」という言葉の使い方や例文を解説!
受動態の使い方は「主語が行為を受けた事実」を前面に出したいときに有効です。たとえば研究結果や事件報道、製品紹介など事実を客観的に示す文章で重宝されます。能動態に比べて主語位置が変わるため、旧情報→新情報の流れを整えやすい利点もあります。
日本語では助動詞「れる・られる」を付けるだけで受動文が作れるため、語順を大きく変えずに情報の焦点を移動できます。英語の場合は “be動詞+過去分詞” が必須で、時制や数に応じてbe動詞が変化する点に注意が必要です。
以下に日本語と英語の両方で典型的な使い方を示します。
【例文1】この研究は多くの専門家に評価されている
【例文2】The novel was translated into twenty languages。
【例文3】新製品は世界中で愛用されている
【例文4】The meeting has been postponed due to the storm。
これらの例では、行為者を特定しないことで「評価の高さ」「翻訳事実」など結果を際立たせています。受動態を使わず能動態にすると「多くの専門家がこの研究を評価している」「The publisher translated the novel…」のように行為者が前面に出ます。伝えたい焦点が「研究」や「小説」であれば受動態が適切です。
ただし公文書や契約書では行為者を明示しないと責任の所在が曖昧になるため、受動態の多用は避けるというガイドラインも存在します。目的に応じて使い分けましょう。
「受動態」という言葉の成り立ちや由来について解説
「受動態」は漢字三字で構成され、それぞれの語源が意味を補強しています。「受」は古代中国語で“うけとめる”、「動」は“動き・作用”、「態」は“形・ありさま”を指し、三つ合わせて「作用を受ける形」を示す造語です。日本の文法学者が漢文の語形成法を踏襲し19世紀末に翻訳語として定着させました。
英語の “passive voice” を直訳せず、すでにあった「能動態(active voice)」に対応させるため「受動」の二字が選ばれたと考えられています。この翻訳作業には学者の山田孝雄らが関わった記録があり、明治時代の『廣文典』にはすでに「受動態」が登場します。
「態」という字は中国古典の文法分類「助動詞の態」などに使われていたため、文法用語としての馴染みがありました。そのため「受動体」ではなく「受動態」という表記が広まり、以後ほぼ揺れることなく今日に至っています。
また「passive」の語源はラテン語 “passivus”(受け身の)で、“patior”=「苦しむ・経験する」から派生しています。日本語の「受ける」とも通底する概念であり、東西の言語概念が類似の比喩で結びついた点が興味深いところです。
こうした翻訳語の成立は、近代日本が西洋文法を取り入れる中で生まれた知的資産と言えるでしょう。
「受動態」という言葉の歴史
受動態そのものは古代語にも存在しますが、用語としての歴史は近代に始まります。江戸末期から明治にかけて、蘭学の影響で西洋文法が紹介されると「能動」「受動」の区別が提案されました。当初は「被動形」「受身形」など複数の呼称が乱立していました。
1870年代の英語教科書『比俗英和対話』では “passive” に「レセルカタチ」と読み仮名が振られ、受動概念が周知され始めます。その後、山田孝雄や大槻文彦らの辞書編纂を経て「受動態」が標準化され、中学校英語科のカリキュラムにも採用されました。
戦後の学習指導要領(1947年版)で受動態が必修範囲に定められると、国民全体へ急速に浸透します。テレビや新聞も英語教育を扱うことで、一般層にとってもおなじみの用語となりました。
同時に日本語学でも「受身文研究」が活発化し、能動・受動の対立だけでは説明できない尊敬受動・自発受動など独自の分析枠が提案されました。これにより「受動態=単なる受け身」という理解が再考され、今日では多義的な現象として扱われています。
現在ではAI翻訳や言語学研究の場面でも欠かせないキーワードとなり、言語教育・情報処理の双方で重要度を増しています。
「受動態」の類語・同義語・言い換え表現
「受動態」の代表的な言い換えは「受身形」「パッシブボイス」です。日本語教育では「受身形(うけみけい)」が多用され、助動詞「れる・られる」の学習と結びつけられます。英語学習向け資料ではカタカナで「パッシブボイス」と表記されることもあります。
また「被動態(ひどうたい)」という中国語由来の表現もあり、漢文訓読の影響が見られます。ただし現代日本語では学術書に限定されるため一般的とは言えません。「受動形」「受動文」もほぼ同義で、後者は“文(sentence)”に焦点を当てた語です。
プログラミングの世界では「パッシブ構文」や「パッシブセンテンス」が用いられることがあります。これらはいずれも「受動態」と置き換えて差し支えありませんが、対象分野の慣例に合わせるのが望ましいです。
要するに「受動態」という言葉を別の語に言い換えても、核心は“主語が動作を受ける文の仕組み”という一点に集約されます。
「受動態」の対義語・反対語
受動態の最も明確な対義語は「能動態(のうどうたい/active voice)」です。能動態では主語が行為者となり、動作を“する”立場にあります。この対立は情報の提示順序と焦点を変えるため、文章構成に大きな影響を及ぼします。
英語学習では「能動→受動」の書き換え問題が定番で、双方の構造を理解することが語順感覚を養う近道とされています。日本語でも「田中さんがケーキを食べた」(能動)と「ケーキが田中さんに食べられた」(受動)の対比で示されるように、同じ出来事でも視点が変わることが実感できます。
なお「自動詞文」は対義語ではなく、能動・受動とは別軸の分類です。自動詞・他動詞の区別と混同しがちなため、学習時には留意しましょう。
文章を書き分ける際は「主体を際立たせたい=能動態」「結果や影響を際立たせたい=受動態」という目安を持つと便利です。
「受動態」と関連する言葉・専門用語
受動態に関連する主要専門用語として「被動文」「中間態」「再帰態」「自発受身」などが挙げられます。これらは言語学の態(voice)研究で頻繁に用いられる概念で、受動態の拡張版や隣接領域を示します。
たとえば「中間態」は能動・受動の中間的性質を持ち、英語の “The book sells well.” のように行為者を明示せず販促効果を示す文を説明します。また「再帰態」は主語と目的語が同一となる状況で、“He washed himself.” のような文が例です。
日本語固有の概念として「尊敬受動」「迷惑受動」「可能受動」があり、「先生に褒められる」「雨に降られる」「この薬は飲まれる」のように意味役割が細分化されます。これらを総合的に理解すると、受動表現の多様性を捉えやすくなります。
言語処理の分野では「受動化(passivization)」という操作があり、能動文を受動文へ機械的に変換して係り受け解析を行います。自然言語処理のアルゴリズム開発でも必須の手順です。
このように受動態は単独の用語に留まらず、幅広い専門概念と連動しながら発展してきました。
「受動態」に関する豆知識・トリビア
受動態の英文はシェイクスピアの作品でも数多く見られ、一説では全セリフの約20%が受動形だと分析されています。劇中で犯人や行為者を伏せる演出に役立っていると指摘されています。
ドイツ語では受動を表す助動詞 “werden” が「〜になる」という本来の意味を持つため、受動文を直訳すると「何かになった」というニュアンスが混じる独特の味わいがあります。一方、タイ語には明示的な受動形が乏しく、語順や助詞で意味を補うのが一般的です。言語によって「受け身」の概念の捉え方が多彩だとわかります。
英語学習者が頻繁に間違えるのは「進行形+受動態」の組み合わせで、“is being built” のようにbe動詞が二重に登場します。日本語には相当形が少ないため感覚的にピンと来ないケースが多いですが、実務文書ではよく使われるので要チェックです。
またSNSでは「It is said that…」の定型文が“憶測ツイート”を和らげる表現として利用されることがあります。受動態にすることで主語を曖昧にして責任をぼかす効果を狙った例です。
日本語の「生まれる」は歴史的に自発の受動形が独立した語になったもので、受動態と語形成の関わりを示す好例とされています。
「受動態」という言葉についてまとめ
- 「受動態」は主語が動作を受ける形を示す文法用語で、多くの言語に存在します。
- 読み方は「じゅどうたい」で、英語の “passive voice” に相当します。
- 明治期に西洋文法を翻訳する過程で生まれ、能動態との対比で定着しました。
- 客観的記述に便利ですが、多用すると主体が曖昧になるため使い分けが重要です。
受動態は「誰が行ったか」より「何が行われたか」を強調したいときに欠かせない道具です。読み方は「じゅどうたい」、英語なら“passive voice”と覚えておけば、国語・英語の両方で活用できます。
明治時代の学者たちが西洋文法を翻訳した際に作られた言葉で、能動態とペアを成し今日まで使われ続けています。客観報告や配慮表現、そして情報の焦点を移すための技法として、今後も文章作成において重要性は変わらないでしょう。