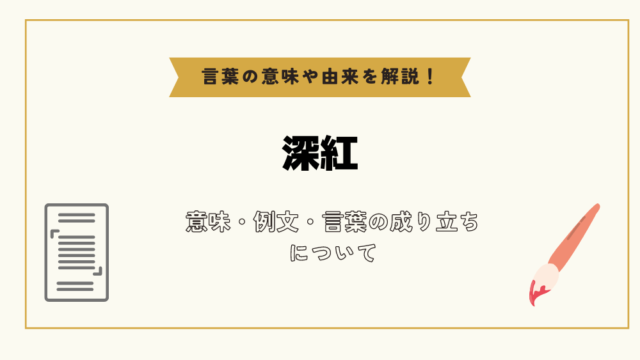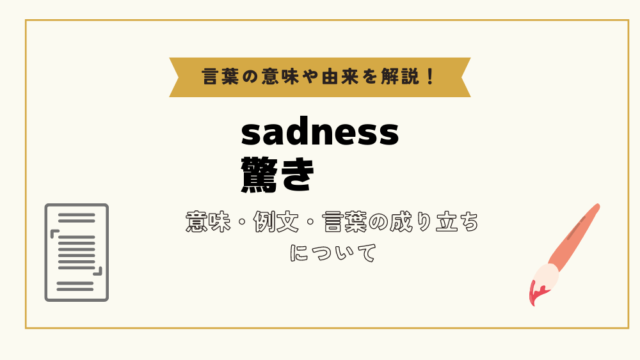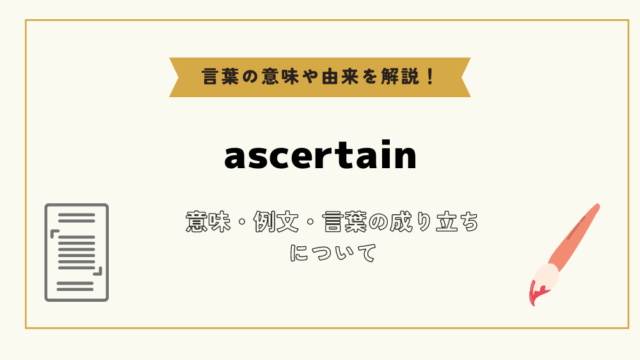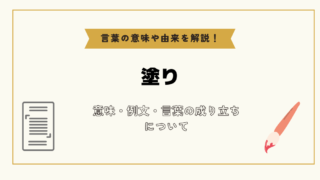Contents
「掲示」という言葉の意味を解説!
「掲示」とは、情報や告知などを人々に知らせるために、公共の場に書き出したり、張り出したりすることを指します。
日常生活の中でよく見かけるのが、学校の掲示板や駅の掲示物などです。
掲示は、人々が必要な情報を手軽に受け取ることができる便利な手段です。
「掲示」の読み方はなんと読む?
「掲示」は、読み方は「けいじ」となります。
漢字の「掲」と「示」の二つの文字からなります。
日本語の発音としては、やや硬く感じられるかもしれませんが、一度慣れてしまえば自然に口に出せるようになります。
「掲示」という言葉の使い方や例文を解説!
「掲示」は、あらゆる場面で広く使われる言葉です。
学校や会社、公共の場での告知や案内をはじめ、イベントのポスターや広告なども掲示物として扱われます。
例えば、「明日の会議の予定は掲示板に掲示されていますので、ご確認ください」といった使い方が一般的です。
掲示物は、人々にとっての重要な情報源となっています。
「掲示」という言葉の成り立ちや由来について解説
「掲示」は、漢字の「掲」と「示」という二つの文字で構成されています。
漢字の「掲」は、「手で抱える」という意味があり、また「掲げる」という意味も持ちます。
一方、「示」は、「見せる」という意味を持っています。
これらの意味を組み合わせることで、「手で見せる」という意味合いを表しています。
情報を手に取って人々に示すという行為から、「掲示」という言葉が生まれたと考えられています。
「掲示」という言葉の歴史
「掲示」という言葉の歴史は古く、日本での使用は奈良時代にまで遡ります。
当時は木簡や竹簡などに文字を刻んで掲示する方法が主流でした。
その後、紙や布などへの文字の書き付けや印刷技術の発展により、より効率的な掲示が可能となりました。
さらに、近代になると電子掲示板やインターネットの登場により、より広く情報が伝えられるようになりました。
「掲示」という言葉についてまとめ
「掲示」とは、情報や告知を人々に伝えるために公共の場や掲示板などに書き出したり、張り出したりする行為を指します。
学校や会社、公共の場などで日常的に目にすることができます。
その読み方は「けいじ」といいます。
また、「掲示」の由来は、手で見せるという行為に由来しており、日本での使用は古くまで遡ります。
現代では、過去に比べて技術の進歩により効率的な掲示が実現され、情報の伝達手段として重要な役割を果たしています。