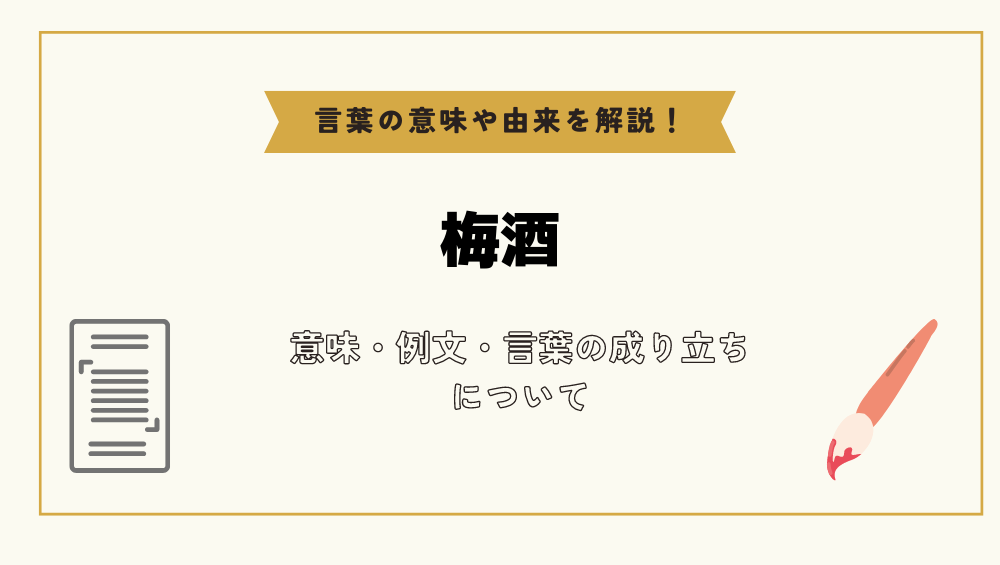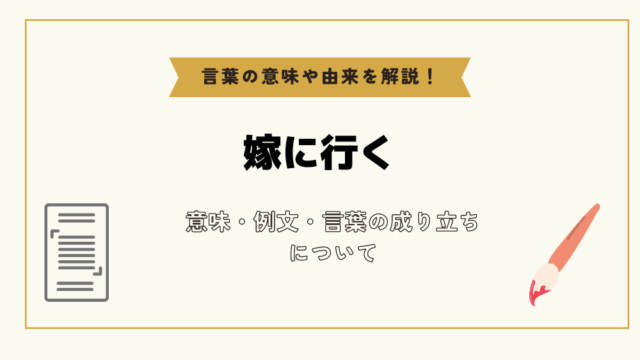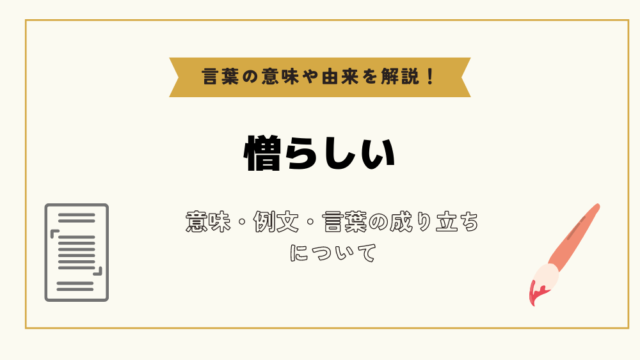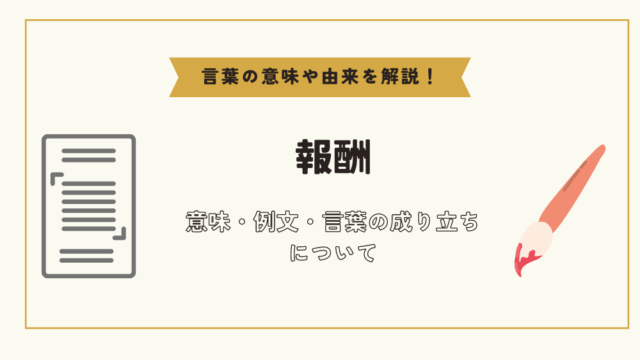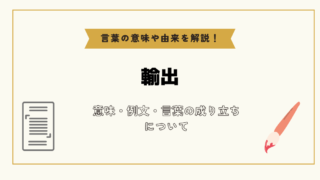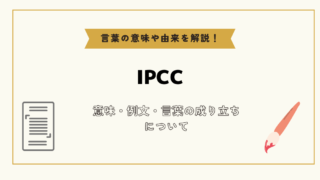Contents
「梅酒」という言葉の意味を解説!
梅酒とは、日本の伝統的なお酒の一つです。
梅の実とお酒を組み合わせて作られることが特徴で、爽やかな梅の香りと味わいが楽しめます。
梅の実をアルコールに漬け込んで作られるので、果実酒に分類されます。
一般的なアルコール度数は10〜20度程度で、甘酸っぱくて飲みやすい味わいが特徴です。
「梅酒」という言葉の読み方はなんと読む?
「梅酒」という言葉は、「うめしゅ」と読みます。
日本の伝統的なお酒なので、日本語の読み方になります。
飲み物の中でも比較的ポピュラーなので、多くの人がこの読み方を知っているでしょう。
「梅酒」という言葉の使い方や例文を解説!
「梅酒」という言葉は、一般的にはお酒の種類を指す言葉です。
「梅酒を飲みたい」という風に使います。
また、「梅酒を作る」という場合は、自家製で作ることもあります。
例えば、「友達と一緒に梅酒を作って楽しんだ」というように使うことができます。
また、「梅酒が大好きで毎晩飲んでいる」というような使い方もできます。
「梅酒」という言葉の成り立ちや由来について解説
「梅酒」という言葉は、そのまま「梅」の実のお酒を意味しています。
日本では古くから梅の実を漬け込んでお酒を作る習慣があり、それが「梅酒」として広まったとされています。
梅は日本の国花でもあり、盛夏に美しい花を咲かせます。
その花を楽しみながら梅の実を漬け込んだお酒が、日本独特の文化として愛されてきました。
「梅酒」という言葉の歴史
梅酒の歴史は古く、日本古来の飲み物として存在しています。
梅の実は収穫時期に合わせて漬け込むことが一般的で、その後数ヶ月〜数年間、梅の味がアルコールに染み出すまで待ちます。
昔から家族や友人と一緒に楽しむ機会も多く、季節の香りとともに楽しめるお酒として広まっていきました。
「梅酒」という言葉についてまとめ
梅酒は日本の伝統的なお酒であり、梅の実をアルコールに漬け込むことで作られます。
主に甘酸っぱい味わいが特徴で、さわやかな香りも楽しめます。
梅酒は日本の文化として広まっており、季節の変化とともに楽しむこともできます。
自家製で作ることもあり、家族や友人との交流の場としても愛されています。
梅酒は飲みやすく、幅広い人々に人気のあるお酒です。