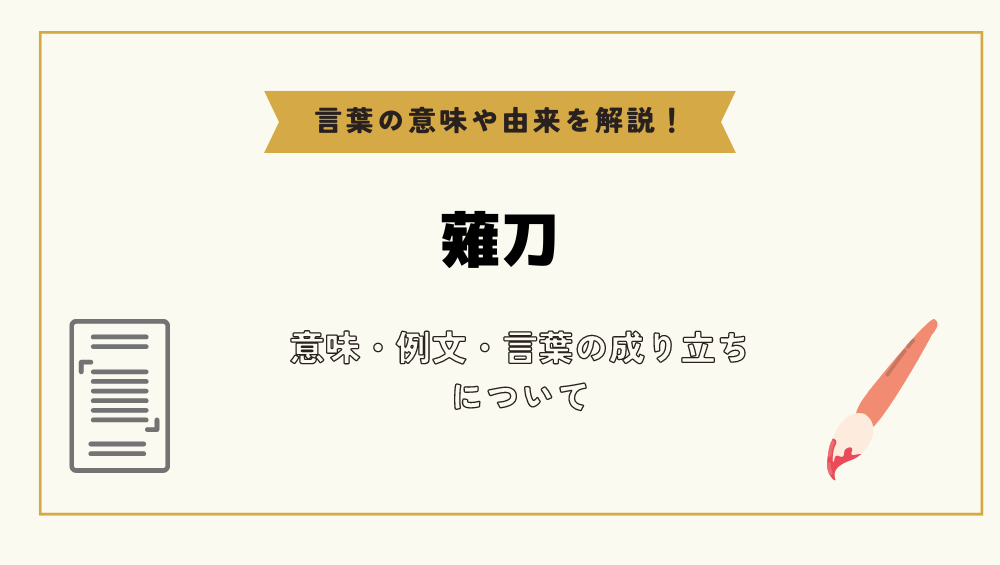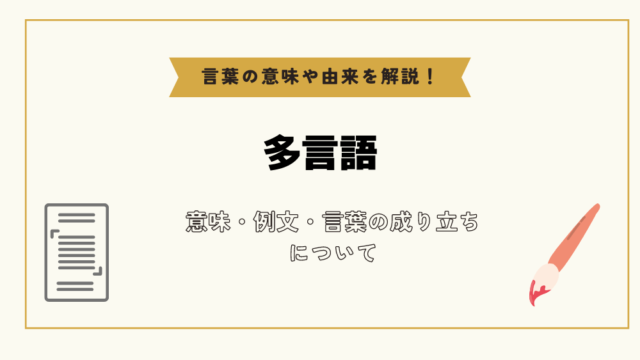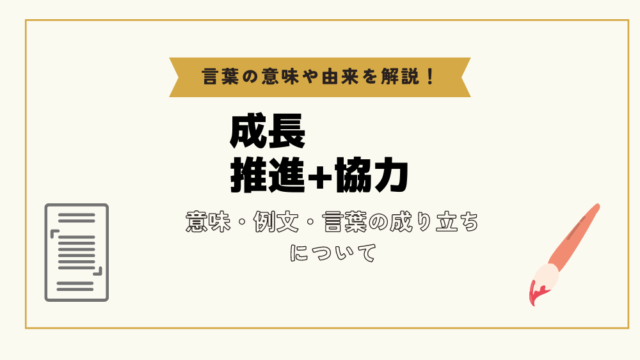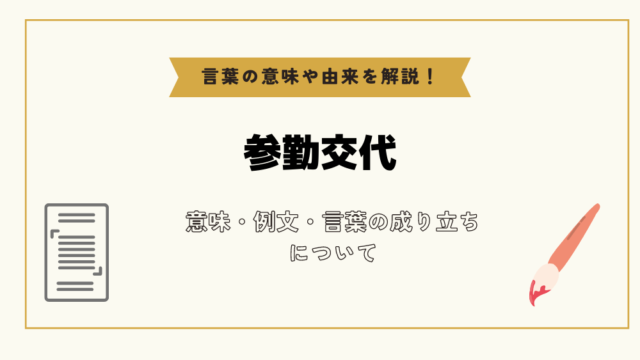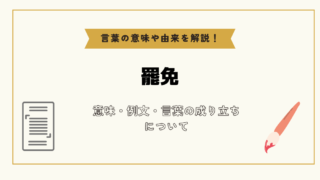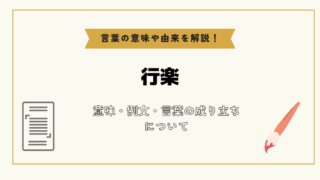Contents
「薙刀」という言葉の意味を解説!
「薙刀」とは、日本の武器の一つで、長い柄に刀身がついた武器です。
主に戦場で使用され、敵を斬りつけるために使われました。
薙刀には鉄砲撃ちを防ぐための金具もついており、防御にも使用されました。
「薙刀」という言葉の読み方はなんと読む?
「薙刀」は、「なぎなた」と読みます。
漢字の「薙」は、「草を刈る」という意味を持ち、「刀」は「武器」という意味を持ちます。
この読み方で、日本古来の戦闘技術を思い浮かべることができます。
「薙刀」という言葉の使い方や例文を解説!
「薙刀」という言葉は、一般的な会話ではあまり使用されませんが、柔道や武道といった特定の分野で使われることがあります。
例えば、「彼は薙刀の達人です」というように使います。
薙刀は古来からの武器ですが、現代ではスポーツや武道の一環として継承されています。
「薙刀」という言葉の成り立ちや由来について解説
「薙刀」という言葉の成り立ちは、薙(な)という字が 草の刈り取りを意味し、刀(なた)という字が刀のことを指しています。
薙刀は、別名「会津流」とも言われ、会津地方で独自に発展しました。
会津地方は武士の地であり、武芸が発展していたため、薙刀の技術も発達したとされています。
「薙刀」という言葉の歴史
薙刀は、古くは13世紀ごろから使われていたと言われています。
主に武士や戦国時代の兵士が使用しており、戦場での戦闘において重要な役割を果たしていました。
江戸時代には、薙刀術が武士たちの修行や武道の一環として重要視され、継承されました。
現代では、古武道やスポーツとしての薙刀があります。
「薙刀」という言葉についてまとめ
「薙刀」という言葉は、長い柄に刀身がついた武器を指し、日本の武器文化の一部となっています。
読み方は「なぎなた」といいます。
現代では一般的な会話では使用されないことが多いですが、武道やスポーツにおいてはその技術が継承されています。
歴史的な背景や成り立ちも興味深い点です。