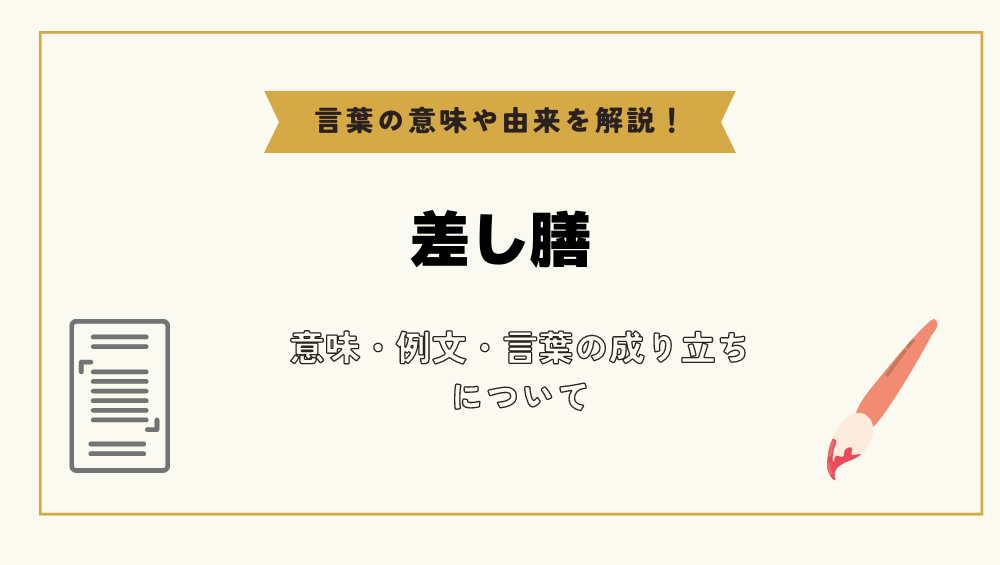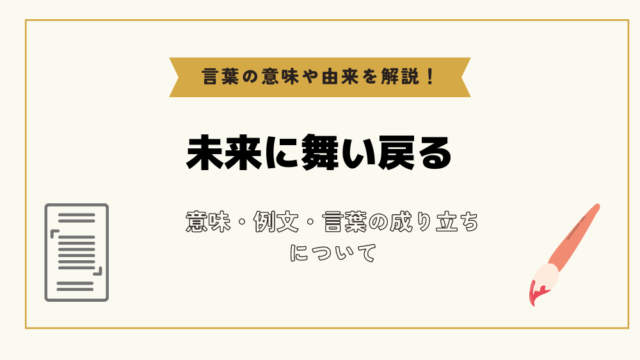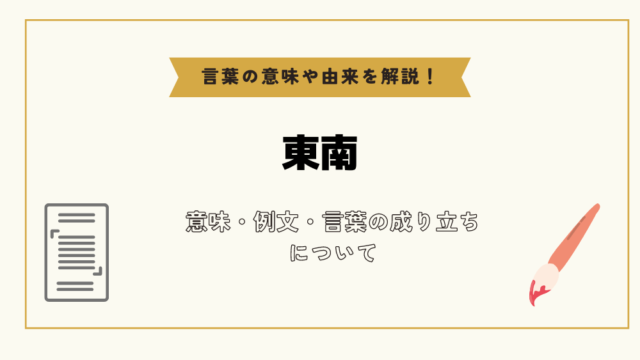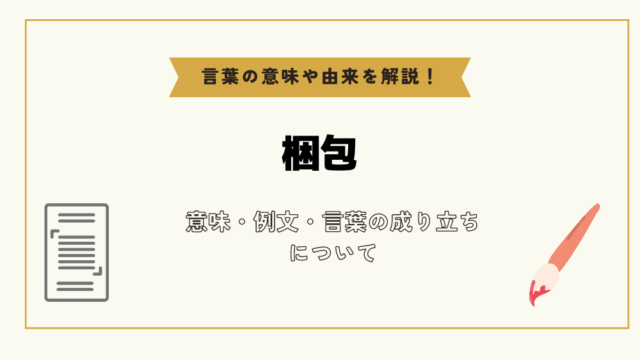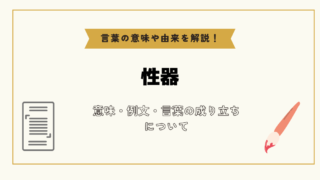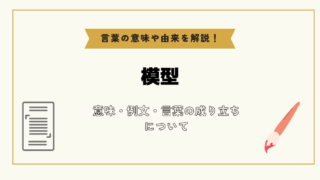Contents
「差し膳」という言葉の意味を解説!
「差し膳」とは、日本の伝統的な食事文化において、料理が盛り付けられた膳を机に差し出すことを指す言葉です。
差し膳は、一人ひとりに料理が個別に盛られており、豪華な食事の象徴としても知られています。
「差し膳」の読み方はなんと読む?
「差し膳」は、読み方としては「さしの」です。
膳(ぜん)は、食事を盛り付けるための置物であり、心地よい食事の場を作るために大切なアイテムとして用いられています。
「差し膳」という言葉の使い方や例文を解説!
「差し膳」は、特に料理や食事に関連する文脈で使用されることが多いです。
例えば、「おめでたい日には、家族全員に差し膳を出して特別な食事を楽しむことがある」というように使われます。
「差し膳」という言葉の成り立ちや由来について解説
「差し膳」の成り立ちは、食事を提供する際に膳を机に差し出すことからきています。
日本の食事文化では、膳を大切な客人に差し出すことが礼儀とされ、おもてなしの心を表すものとされてきました。
「差し膳」という言葉の歴史
「差し膳」の歴史は古く、奈良時代から存在していました。
当時は、豪華で美しい彩りの膳が贈られることが一般的でした。
江戸時代になると、差し膳の文化は一般家庭にも広まり、重要な行事やお祝いの席などで利用されました。
「差し膳」という言葉についてまとめ
「差し膳」とは、料理が盛り付けられた膳を机に差し出すことを指す言葉であり、日本の食事文化において重要な役割を担っています。
豪華な食事やおもてなしの心を表す象徴とされる「差し膳」は、日本独自の文化の一つとして大切にされています。