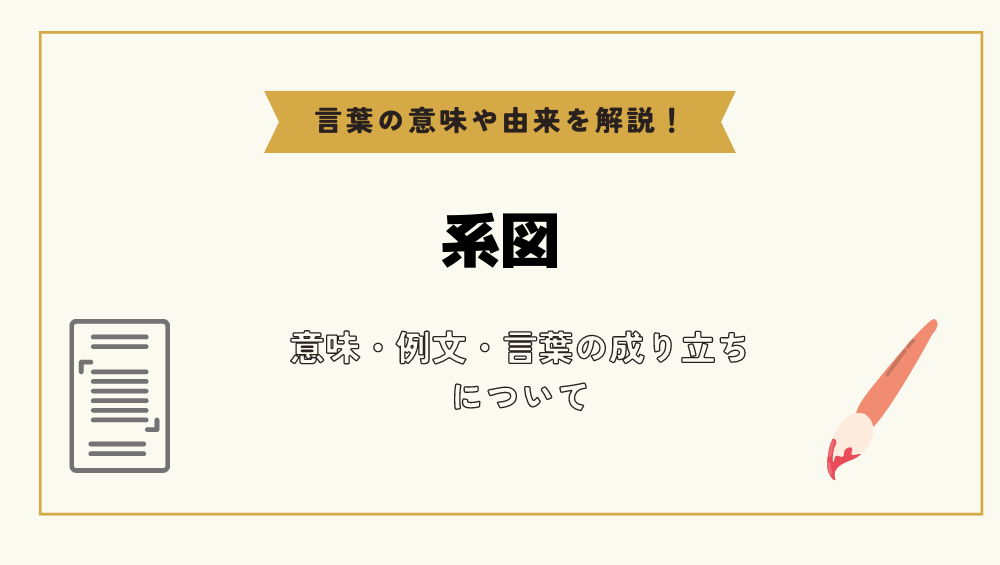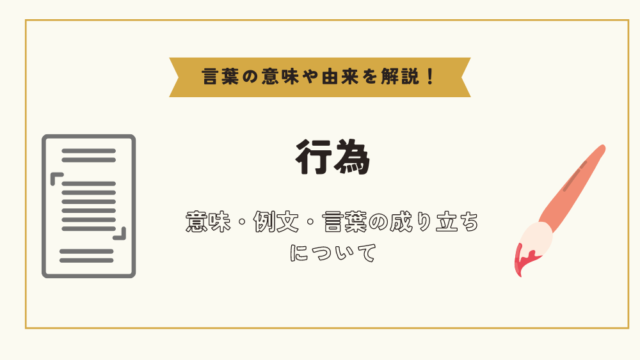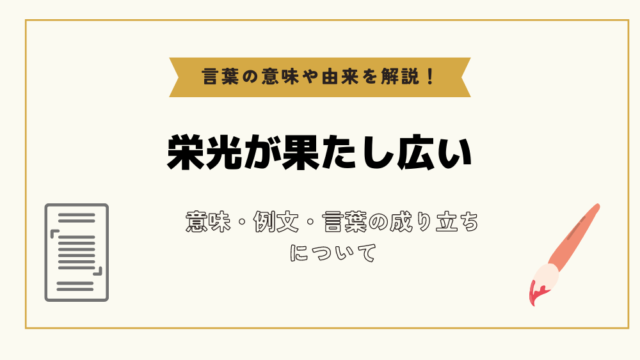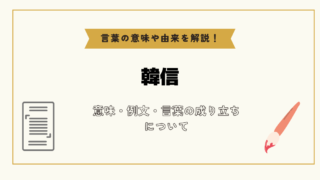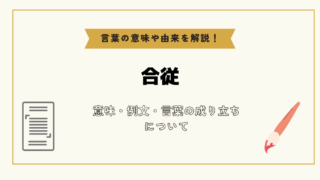Contents
「系図」という言葉の意味を解説!
「系図」という言葉は、家族や血縁関係を示す図表のことを指します。
一般的には家系や血統の歴史を可視化するために使用されます。
系図は、祖先や子孫、兄弟姉妹などの関係性を分かりやすく表現するために利用され、家族の繋がりや起源を理解するのに役立ちます。
「系図」という言葉の読み方はなんと読む?
「系図」の読み方は「けいず」となります。
この読み方は、一般的に使われているものです。
もちろん、地方によって若干の発音の違いがあるかもしれませんが、基本的には「けいず」と読むことで通じるでしょう。
「系図」という言葉の使い方や例文を解説!
「系図」という言葉は多くの場面で使用されます。
例えば、自身の家族について人に説明する際には「私の家族は系図で表すとこうなります」と言うことができます。
また、歴史研究や祖先の起源探求においても「系図を調べる」といった表現が一般的です。
「系図」という言葉の成り立ちや由来について解説
「系図」という言葉は、日本の歴史や文化に深く関わっています。
その由来は、日本の古代にまで遡ることができます。
当時、王族や貴族などの家系や血統を正確に伝えるために記録された図表が系図の起源とされています。
その後、地方の氏族や一般の人々の家族関係を記録するためにも使用されるようになりました。
「系図」という言葉の歴史
「系図」という言葉の歴史は、古代から現代まで続いています。
特に日本の歴史においては、武士や大名などが系図を作成し、家族や家系の繋がりや権力関係を示すために使用されました。
また、明治時代以降も系図は法的な親族関係の証明や家族の起源確認のために利用され続けています。
「系図」という言葉についてまとめ
「系図」という言葉は、家族の繋がりや血縁関係を示すために使用される図表のことを指します。
また、「けいず」と読みます。
「系図」の使い方は日常会話や歴史研究で頻繁に利用されます。
日本の歴史や文化においては、王族や貴族の家系や血統を正確に伝えるために作成された記録が起源とされ、現代でもその役割は重要です。