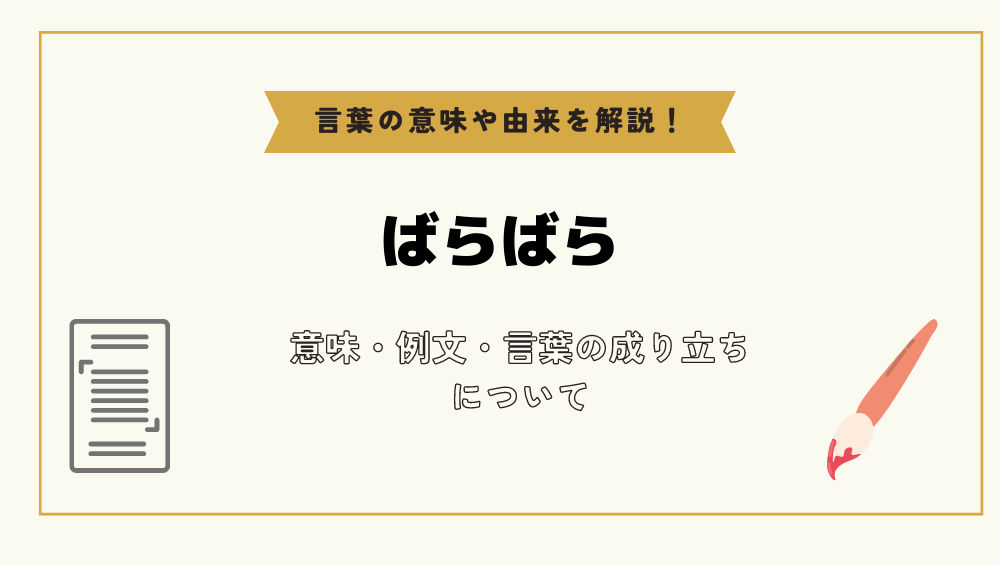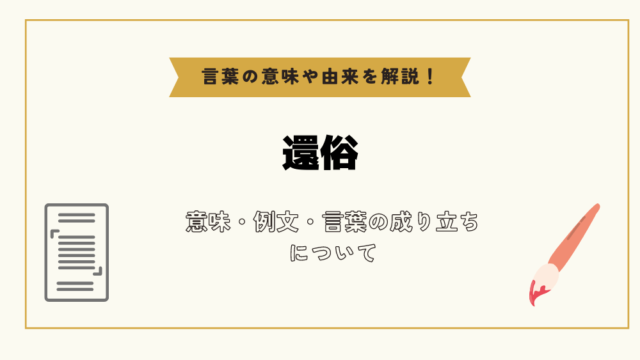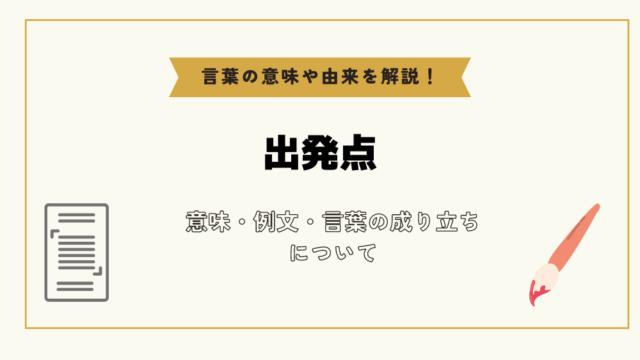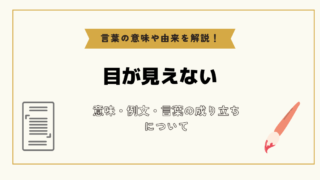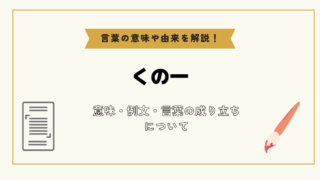Contents
「ばらばら」という言葉の意味を解説!
「ばらばら」という言葉は、何かがバラバラに分かれたり散らばったりしている状態を表す言葉です。
例えば、ばらばらになったパズルのピースやばらばらに散らばった砂などが該当します。
「ばらばら」は、一つのものがまとまっていた状態から、分散・散在する状態を表す言葉です。
。
「ばらばら」の読み方はなんと読む?
「ばらばら」は、ふったんごと読みます。
バラとバラの「バラ」と、動詞「ふる」の「ふ」が重なり合っています。
音の響きから、ばらばらに分かれたものがばら撒かれる様子をイメージできますね。
「ばらばら」という言葉の使い方や例文を解説!
「ばらばら」という言葉は、副詞としても形容詞としても使うことができます。
例えば、「集まっていた人々がみんなばらばらに帰ってしまった」といった使い方があります。
また、「ばらばらになった意見が多くて結論が出せない」といった場合は、形容詞としての使い方になります。
「ばらばら」という言葉の成り立ちや由来について解説
「ばらばら」という言葉の成り立ちは、元々は「バラの花びらが散らばる様子」を表現していました。
そこから、物事が分かれて散らばる様子を指す一般的な表現となりました。
由来は明確ではありませんが、日本語の豊かな表現力によって自然に生まれた言葉のひとつと言えます。
「ばらばら」という言葉の歴史
「ばらばら」という言葉の歴史は古く、古典的な日本文学や俳句などでも頻繁に使用されてきました。
江戸時代には、「ばらばらになって散る桜の花」という風景が詠まれたりもしました。
現代においても、日常会話や文学作品などで広く使用されています。
「ばらばら」という言葉についてまとめ
「ばらばら」という言葉は、一つのものが分かれて散らばる様子を表現する言葉です。
その由来は古く、日本語の魅力的な表現力によって生まれた言葉です。
日常会話から文学作品まで幅広く使われるため、覚えておくと便利です。