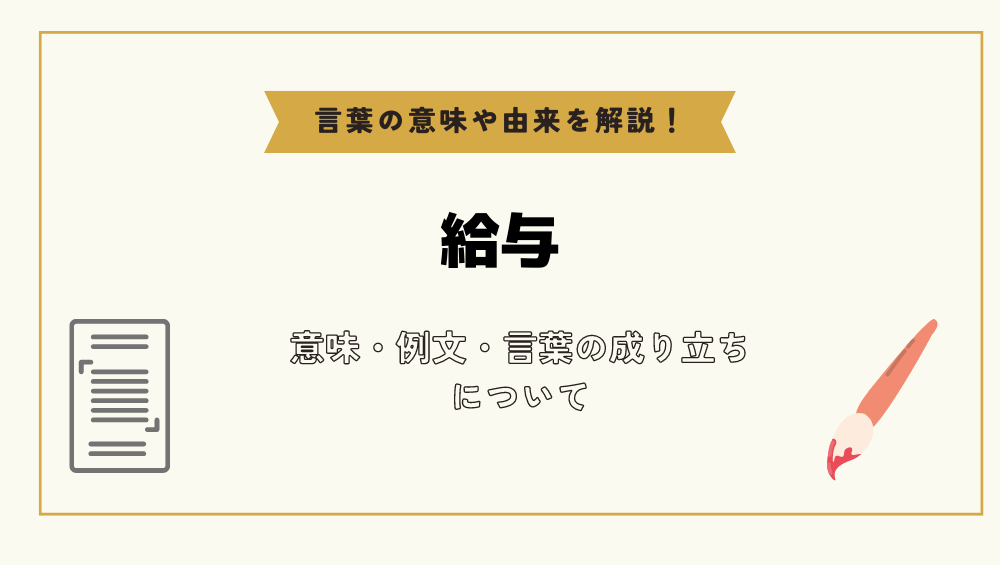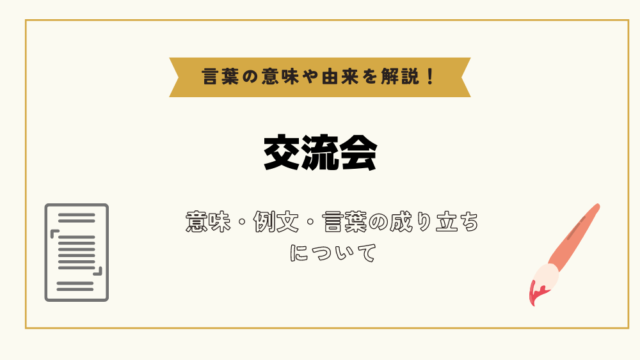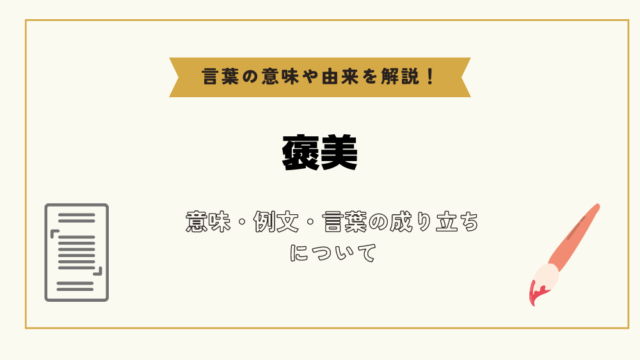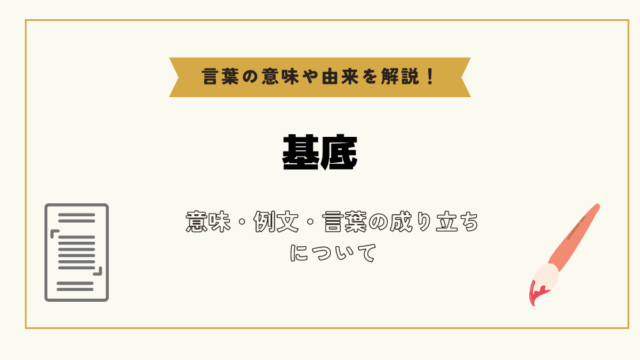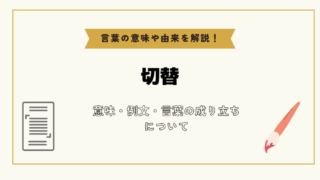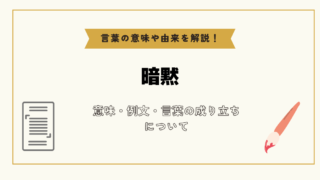「給与」という言葉の意味を解説!
「給与」とは、労働者が労働の対価として企業や組織から受け取る金銭報酬の総称です。日本の労働基準法24条では「賃金」として定義され、賃金・給料・手当・賞与など名称を問わず、労働に対して支払われるすべての金銭が含まれます。一般的には月ごとに決められた基本給に諸手当を加えた額を指す場合が多く、「年収」と区別して用いられます。
「給与」は現金主義が原則であり、通貨または本人指定の銀行口座への振込で支払われるのが日本の法制度上の基本です。税金(所得税・住民税)や社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険など)は天引きされ、残った金額を「手取り給与」と呼びます。額面と手取りの違いを把握しておくことは、家計管理やライフプランを立てるうえで必須の知識です。さらに、通勤手当や住宅手当など課税・非課税の違いもあり、年末調整や確定申告に影響します。
近年は働き方改革や賃金デジタル払いの解禁など、「給与」を取り巻く環境が大きく変化しています。企業は法令順守と従業員エンゲージメント向上を両立させるため、賃金体系の透明化や評価制度の見直しを進めています。働く側もインフレ率、最低賃金、転職市場など外部環境を踏まえ、自身の給与水準を客観的にチェックする姿勢が求められます。
「給与」の読み方はなんと読む?
「給与」は音読みで「きゅうよ」と読みます。「給」は「与える」「配る」を意味し、「与」は「あたえる」の意を持つ漢字で、両者が組み合わさり“与えて配るお金”というニュアンスを形成します。
一方で「給金(きゅうきん)」や「給料(きゅうりょう)」と混同しやすいですが、読み方と意味に微妙な差があります。給金は時給や日給など短期の支払いを想起させる語で、給料は月給を指すことが多い表現です。
ビジネス文書では「給与支給明細書」「給与改定通知」など堅い場面で用いられることが一般的です。また、口語では「お給料」「給料」と言い換えるケースが多く、求人広告でも「給与:月給〇円〜」と表示されます。正しい読みと漢字を理解しておけば、文書作成や面接時に信頼感を与えられます。
「給与」という言葉の使い方や例文を解説!
給与は主にビジネスシーンで用いられますが、家計やライフイベントの話題でも頻出します。金額や支払方法、増減の理由を説明するとき、「給与」という語を用いると正式かつ明確な印象を与えられます。特に公的書類や契約書では「給料」よりも「給与」を使うことで法的概念と整合するため誤解を防げます。
【例文1】当社は来月から基本給を5%引き上げ、給与テーブルを改訂します。
【例文2】給与の振込日は毎月25日ですが、金融機関休業日の場合は前営業日となります。
日常会話で「給料」と言う場合も、フォーマル文書では「給与」に書き換えると良いでしょう。
「給与」という言葉の成り立ちや由来について解説
「給」と「与」はいずれも「与える」を表す語で、古代中国の律令制において官吏へ米や絹を配った制度が語源とされています。日本では奈良時代の養老律令に「給田」「給布」の記載があり、朝廷が官人に支給した米や布を指していました。物品中心の支給が時代を経て貨幣支払いへ変化する過程で、「給与」という言葉も“財貨を与える行為”から“賃金を支払う行為”へ意味を拡張しました。
明治期に欧米の賃金制度が導入されると、官公庁の公文書で「給与」が賃金全般を意味する語として定着します。大正から昭和にかけて企業法務でも使用が広がり、戦後の労働基準法制定で法的な定義が確立しました。
「給与」という言葉の歴史
奈良時代の「禄(ろく)」や「俸(ほう)」が中世を通じて武士や僧侶に与えられる扶持米へと発展し、江戸時代には石高制による知行給与が一般化しました。貨幣経済の浸透と共に現物支給から金銭支給へシフトし、明治以降の近代化で月給制が標準となったことが現在の給与体系の礎です。
戦後は高度経済成長に伴い年功序列・終身雇用の下で「定期昇給」「ボーナス」文化が根付き、平成以降は成果主義やジョブ型賃金など多様なスタイルが併存する時代へ移行しました。2020年代にはリモートワーク普及により地域間の給与格差是正や職務給導入が議論されています。
「給与」の類語・同義語・言い換え表現
給与の類語には「賃金」「給料」「報酬」「サラリー」「コンペンセーション(compensation)」などがあります。それぞれニュアンスに違いがあり、「賃金」は法律用語で時給・日給を含む最も広い概念、「給料」は月給の俗称、「報酬」は成果や役務への対価を強調します。
ビジネス英語では「base salary(基本給)」と「total compensation(総報酬)」を区別するのが一般的です。また、「月給」「年俸」「歩合給」「賞与」などは給与構成要素を示す言い換え表現として活用されます。場面や対象に合った語を選べば、コミュニケーションの精度が高まります。
「給与」の対義語・反対語
給与の対義語として明確に定義された単語は少ないものの、概念的には「支出」「費用」「納付」「課税」など“お金を払う側”の行為を指す語が反対の意味合いを持ちます。
労使関係に着目すると、企業にとって給与は「人件費」であり、従業員にとっては「所得」という点が対照的です。また、労働に対価が発生しない「ボランティア」「無償奉仕」も広義の対義概念として挙げられます。
「給与」を日常生活で活用する方法
給与明細を毎月確認し、控除項目と支給項目の内訳を把握することは家計管理の第一歩です。手取り額を元に50・30・20ルール(生活費50%、変動費30%、貯蓄20%)などの予算管理を行うと無理なく貯蓄目標を達成できます。
給与天引きで財形貯蓄や企業型DC(確定拠出年金)に拠出する方法は、先取り貯蓄として効率的です。副業を行う場合は、年間20万円超の所得があれば確定申告が必要になる点に注意しましょう。昇給・転職の際には求人票や労働条件通知書を確認し、額面だけでなく福利厚生や残業代の計算方法も比較することが重要です。
「給与」についてよくある誤解と正しい理解
「給与=手取り額」と思い込む人が多いですが、実際には額面から各種控除を差し引いた後の金額が手取りになります。社会保険料や税金は法定控除であり、会社が勝手に差し引いているわけではない点を理解しましょう。
また、「残業代は固定残業手当があれば追加で払われない」との誤解がありますが、固定残業代が実際の残業時間を超えた場合は差額を支払う義務があります。給与の締日と支払日は法律上同一月でなくても構いませんが、遅延や未払いは労働基準法違反となるため注意が必要です。
「給与」という言葉についてまとめ
- 「給与」とは労働の対価として支払われる金銭報酬の総称。
- 読み方は「きゅうよ」で、公的・ビジネス文書で用いられる正式表記。
- 古代の現物支給から貨幣支給への変遷を経て定着した言葉。
- 額面と手取りの違い、控除項目の確認が現代生活で不可欠。
給与は、働くすべての人にとって最も身近な経済活動のキーワードです。法律上の定義や歴史を押さえることで、求人票や雇用契約書の内容を正確に読み解けるようになります。
また、読み方・書き方を正しく理解し、類語や対義語を使い分けることで、ビジネス文書の精度が向上します。家計管理やキャリアプランを考える際には、額面と手取りの差、社会保険料の仕組み、昇給・賞与の条件を把握し、ライフステージに応じた計画を立てましょう。