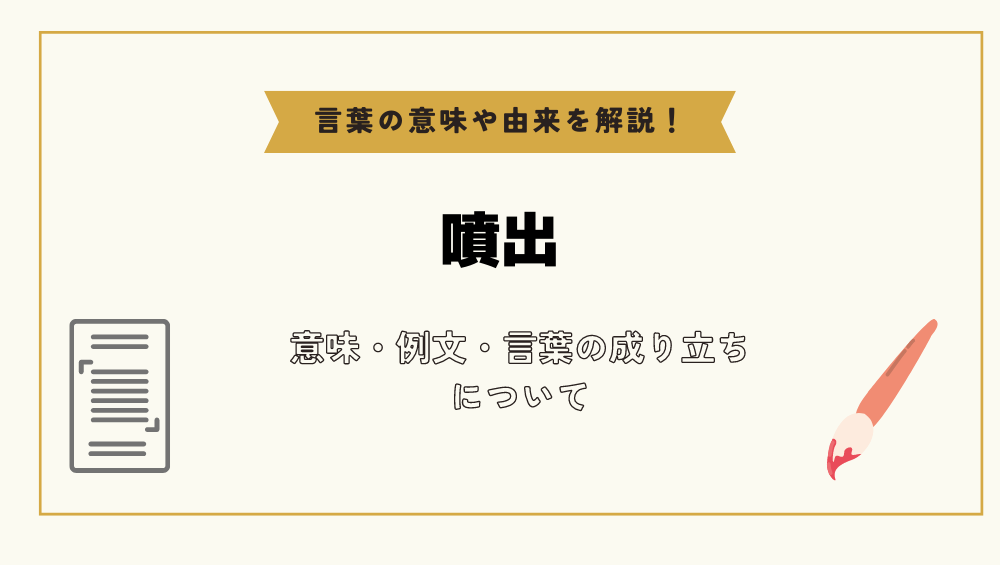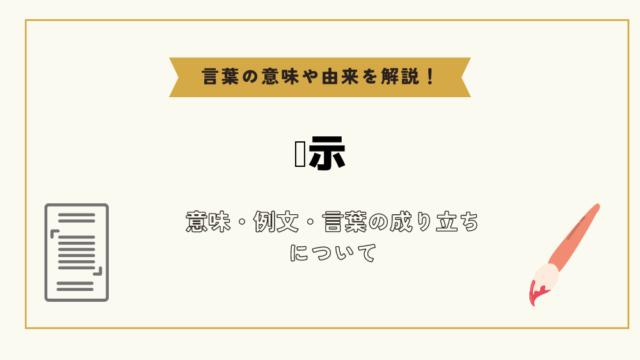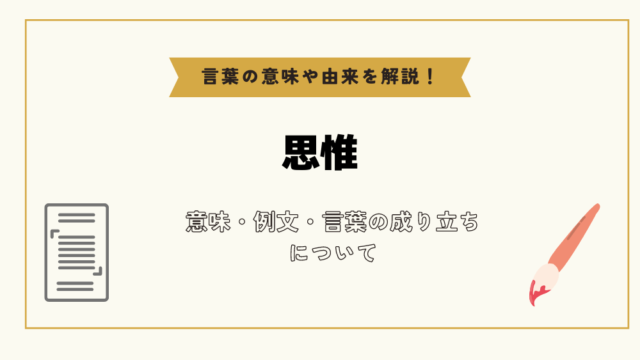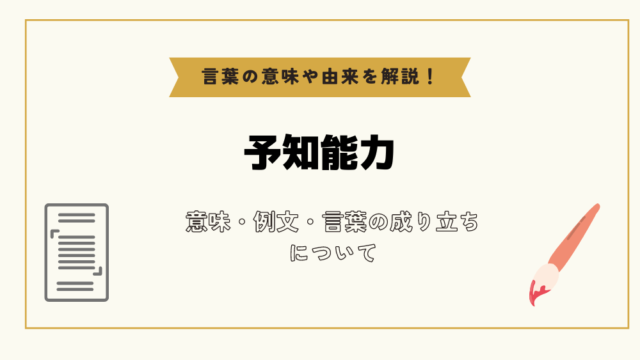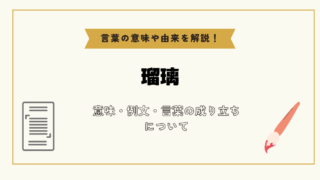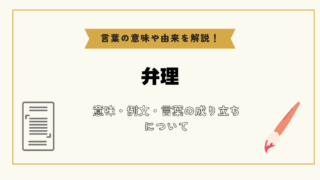Contents
「噴出」という言葉の意味を解説!
「噴出」とは、物や気体が勢いよく吹き出すことを指す言葉です。
例えば、火山から溶岩が勢いよく噴き出す様子や、噴水が水を高く吹き上げる様子が「噴出」と呼ばれます。
噴出は、一瞬にして大量のものが勢いよく放出されるイメージがあり、人々の目を引きます。
噴出という言葉は、どんなものの勢いよく吹き出す様子を表現するために使用されます。
噴火や噴水、噴水師が水を吹き上げる様子など、自然や日常生活の中で噴出現象が起こる場面で用いられることが多いです。
「噴出」という言葉の読み方はなんと読む?
「噴出」という言葉は、「ふんしゅつ」と読まれます。
この読み方は、現代の日本語において一般的なものであり、噴出現象を表すために使用されます。
例えば、山の頂上から溶岩が噴出した場合、その様子は「ふんしゅつ」されます。
また、噴火や噴水の水を放出する際にも、「ふんしゅつ」の読み方が一般的です。
「噴出」という言葉の使い方や例文を解説!
噴出という言葉は、日常生活や科学的な文脈で広く使われることがあります。
例えば、「火山から溶岩が噴出した」という表現は、その火山が大量の溶岩を勢いよく放出したことを意味します。
他にも、「噴水が水を噴出」という表現は、噴水が水を高く吹き上げる様子を示します。
また、ガスや水蒸気が勢いよく噴き出す場合にも「噴出」という表現が用いられます。
「噴出」という言葉の成り立ちや由来について解説
「噴出」という言葉は、漢字表記された「噴出」が常用漢字として認められています。
漢字の組み合わせによって、「ふん」と「しゅつ」という読み方が決まっています。
この漢字表記の成り立ちは、物や気体が勢いよく放出される様子をイメージしています。
噴出現象は、自然や生活の中で見られることがあり、その様子を表す言葉として使われるようになりました。
「噴出」という言葉の歴史
「噴出」という言葉の歴史は古く、日本の古典文献や歌謡曲にも見られます。
火山の噴火や泉の水が噴き出す様子が詠まれ、日本の文化や風俗にも密接に結びついています。
また、近年では科学技術の進歩により、噴出現象に関する研究や観察も進んでいます。
火山学や地質学の分野で、「噴出」という言葉がさまざまな現象を指して使われるようになりました。
「噴出」という言葉についてまとめ
「噴出」という言葉は、物や気体が勢いよく放出される様子を表現する言葉です。
火山の噴火や噴水の水が高く吹き上げる様子など、様々な現象で用いられます。
また、「噴出」は日本の歴史や文化にも深く関わっており、古典文献や歌謡曲で詠まれたり、科学技術の進歩によって研究が進んでいます。
「噴出」という言葉は、その力強さや迫力を表現するのに適した単語であり、日常生活や学問の中で幅広く使われています。