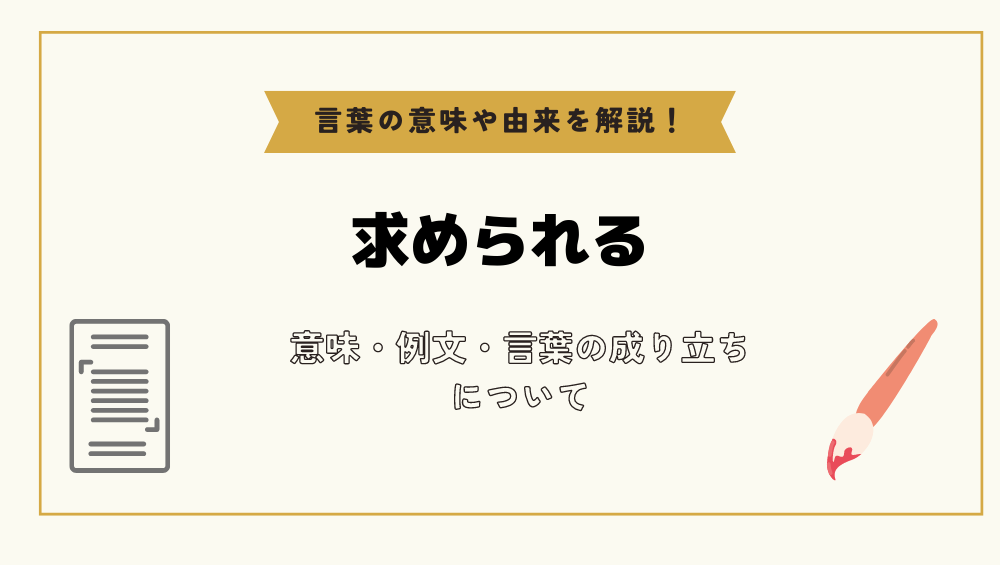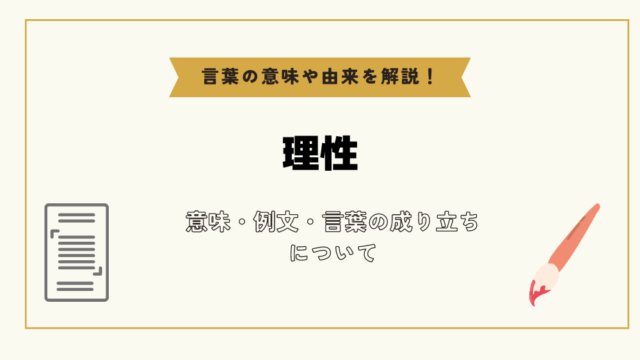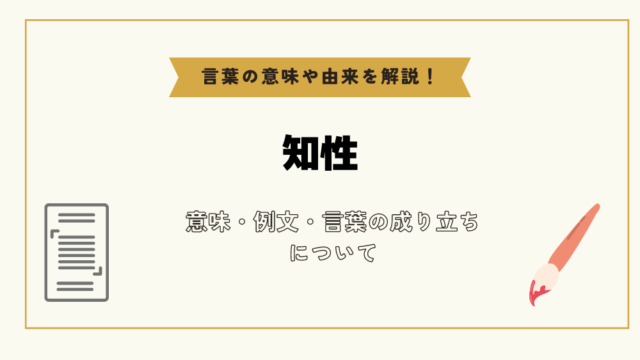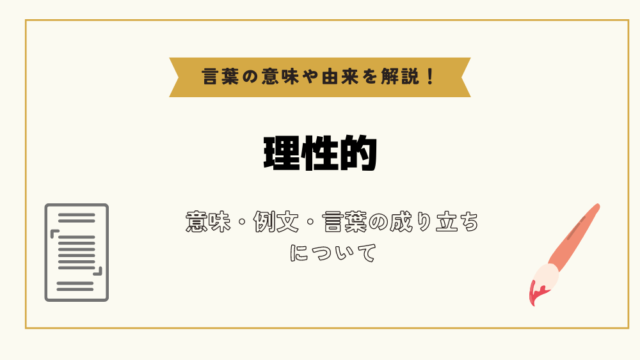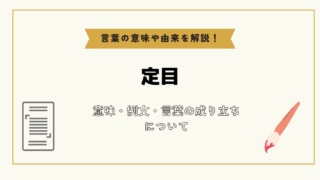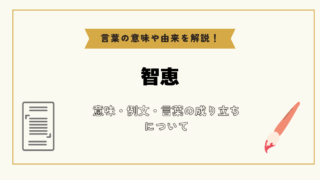「求められる」という言葉の意味を解説!
「求められる」とは、だれかが望んだり必要としたりして対象となる人・物・行動に対して要求が寄せられる状態を示す言葉です。この語は他動詞「求める」の受け身形であり、「〜される」を付けることで「要求を受ける」「期待を受ける」というニュアンスが強調されます。ビジネス文脈では「高い品質が求められる」、生活場面では「整理整頓が求められる」など、相手側の意思によって必要性が提示される状況を示します。
「必要」「要望」「期待」といった類似概念と異なる点は、外部からの積極的な働きかけが含まれることです。必要は状況が自然に生む必須条件ですが、求められるは人や組織が意思を持って要求している点に違いがあります。結果として、達成できたかどうかが評価されやすい言葉でもあります。
また、「求められる」は評価対象が無生物でも成立する特徴があります。たとえば「この装置にはさらなる安全性が求められる」のように、人に限らず物事全般に当てはめられる汎用性があります。
最後に、心理的プレッシャーや社会的プレッシャーを伴う場面で用いられるケースが多い点にも注目です。そのため、「求められる」は単なる説明ではなく、目標設定や基準提示のニュアンスを帯びる語として理解することが大切です。
「求められる」の読み方はなんと読む?
「求められる」の正しい読み方は「もとめられる」です。平仮名では「もとめられる」、漢字を含む表記では「求められる」となります。音読みと訓読みが混在する漢字語が多い中、「求める」は純粋な訓読み「もとめる」が用いられるため、読み違いが起きにくい単語です。
ただし「もとめられる」は五段活用動詞「求める」の未然形+受け身助動詞「れる」で構成されるため、アクセントが変化します。辞書式アクセントは「モトメラレ↓ル」と中高型ですが、地域やイントネーションによっては「モトメラ→レル」と語尾下がりになる例もあります。
声に出して読むときは、一語としてスムーズに発音するよりも、「もとめ|られる」と軽く区切ると聞き手に意味が伝わりやすくなります。公的なスピーチでは語尾が曖昧になると印象が弱くなるため、最後の「れる」を明瞭に発音するのがコツです。
「求められる」という言葉の使い方や例文を解説!
「求められる」は主語を立てずに「〜が求められる」と述語的に使われることが多く、説明的な文章に最適です。ビジネスメールや報告書で条件や基準を提示する際に頻出します。動詞の受け身形なので、行為主体(誰が求めているのか)を明示すると、文全体の透明性が高まります。
【例文1】来年度からはより厳格な個人情報管理が求められる。
【例文2】顧客満足度を高めるために迅速な対応が求められる。
上記のように、名詞+「が求められる」の語順が基本です。口語では「〜が求められている」と進行形を用いると、今まさに期待されている過程を強調できます。
さらに、「誰に」「何を」を加えて具体化する方法もあります。例として「学生には主体的な学びの姿勢が求められる」「自治体には迅速な災害対応が求められる」のように、主体と対象を含めると責任の所在が明確になります。文章を書く際は、求める主体と求められる対象を整理して配置することで、読み手の理解を助けます。
「求められる」という言葉の成り立ちや由来について解説
「求められる」は、動詞「求む(もとむ)」が平安期に派生し、やがて中世日本語で「求める」という五段活用形に定着したことに始まります。漢字の「求」は、手の象形と糸の象形を合わせた会意文字で「探し求めて手繰り寄せる」さまを示すとされ、語源的に「探して手に入れる」動作を含みます。
「求む」は古語で「欲する・請う」という意味を持ち、律令制度下においては役所が人や物を「召し求む」際に多用されました。鎌倉時代には「〜を求め候ふ」といった武家文書でも確認でき、需要や請願を表す語として機能していました。
江戸後期に入ると「求め」は庶民層の商取引や書簡にも広がり、明治期の近代法令で「買い受ける」「請求する」の公用語として整備されました。これに伴い受け身形「求めらる」が文語で用いられ、現代口語の「求められる」へと移行しました。
したがって、「求められる」は日本語史の中で公的・法的場面を支える語として発展し、今もなお要求や要請を端的に示す重要語となっています。
「求められる」という言葉の歴史
平安時代の漢文訓読資料には「求ムル所」といった記述が残り、当時は主に官吏の上申文で使用されていました。鎌倉〜室町期の武家関係文書では「求め候ふ」が頻出し、領地返還や兵糧供出の要請文で重要な機能を担っています。
江戸時代に入ると、町触れや覚書で「町人ニ於テハ年貢納入ヲ求メラルル事」といった表現が登場し、幕府から庶民へ要請が伝わる手段として確立しました。明治政府が公布した布告・達で「免許ヲ要スル者ハ之ヲ求メラルヘシ」と規定されたことで、法律用語としての定着が決定的になりました。
戦後、行政文書の簡素化運動を経て「〜が求められる」は一般向け文書にも広がり、新聞・雑誌・教育現場へ浸透しました。現在はビジネス書からSNSまで幅広い媒体で使用され、「社会が求める人材」「市場が求める機能」など、マクロ視点の需要を伝えるキー語となっています。
この変遷を振り返ると、「求められる」が常に権力構造と密接に関わってきたことがわかります。そのため、言葉の背景にある主体・目的を意識する視点が、歴史を踏まえた適切な運用には欠かせません。
「求められる」の類語・同義語・言い換え表現
「求められる」を別の表現に置き換えると、文章のトーンやニュアンスを細かく調整できます。最も近い類語は「要求される」「要請される」「期待される」です。いずれも受け身形で用い、外部からの必要性を示しますが、強制力の度合いが異なります。「要求」は義務的で強め、「要請」は丁寧だが公式、「期待」はややソフトな印象となります。
他に「必要とされる」「望まれる」「欠かせない」「マストである」といった語も使われます。これらは求める主体がはっきりしない場合に便利です。
技術系の文章では「スペックが求められる」の代わりに「スペックが要件となる」「スペックが必須となる」と置き換えると、より具体的に条件提示できます。言い換えを選ぶ際は、義務なのか期待なのか、相手の立場を考慮して語の強さを調整することが重要です。
「求められる」を日常生活で活用する方法
「求められる」を日常会話に取り入れると、要求や期待をやわらかく提示できます。たとえば家庭内で「食後は食器洗いが求められる」というと、義務を伝えつつも穏やかな響きになります。職場でも「今月は報告書の精度が求められる」と言えば、改善の必要性を示しながら相手に配慮した言い方になります。
ポイントは、相手を責める代わりに状況やルールを主語にすることで、押し付け感を和らげられる点です。さらに、自分事として言う場合は「私にはより柔軟な発想が求められているようです」と受動表現を使い、課題意識と意欲を同時に示せます。
ビジネスマナーでは、会議資料や議事録に「次回までに整理が求められる事項」のように項目化すると、ToDoリストを客観的に示せます。教育現場では「主体的な学習が求められる時代」と掲示することで学生のモチベーションを喚起できます。
このように、「求められる」は直接的に命令せずに期待値を伝える万能フレーズです。ただし多用すると責任の所在が曖昧になるため、主体を補足して誤解を防ぐことが大切です。
「求められる」についてよくある誤解と正しい理解
「求められる」と「必ずしなければならない」は同義と誤解されることがあります。しかし「求められる」はあくまで要求・期待を示す語で、法的義務や強制を必ず伴うわけではありません。たとえば「マスク着用が求められる」は推奨レベルの場合も多く、罰則を伴う「義務」とは異なります。
次に、受け身形だから主体が不要という誤解も見受けられます。主体が不明確な文章は責任の所在がぼやけるため、公式文書では「行政が」「学校が」のように明示するのが望ましいです。
また、「求められる」を多用すると硬すぎる印象になるという声もあります。確かにカジュアルな会話ではやや堅苦しく聞こえるため、「お願いしたい」「してほしい」と使い分けると自然です。
正しい理解には、場面と目的に応じて他の表現と併用し、情報の強さを調整する視点が不可欠です。
「求められる」という言葉についてまとめ
- 「求められる」は外部からの要求や期待を受ける状態を示す受け身表現。
- 読み方は「もとめられる」で、漢字と平仮名の併用が一般的。
- 平安期の「求む」から派生し、公的文書で発展した歴史を持つ。
- 主体・強さを意識しながら、多様な場面で柔軟に活用する必要がある。
「求められる」は単に「必要とされる」だけでなく、要求主体の意思や社会的背景までを含んで示す多層的な言葉です。ビジネスから日常会話まで幅広い場面で使われるため、誰が何をどの程度求めているのかを示す補足情報を添えることで、誤解のないコミュニケーションが実現します。
読み方や歴史を踏まえると、言葉の重みや正式度を適切に把握できます。受け身形ゆえに責任の所在が曖昧になりがちですが、主体を示したり、類語と使い分けたりすることで、文章の透明性と説得力を高められます。本記事を参考に、状況や相手に合わせた「求められる」のスマートな活用を目指してみてください。