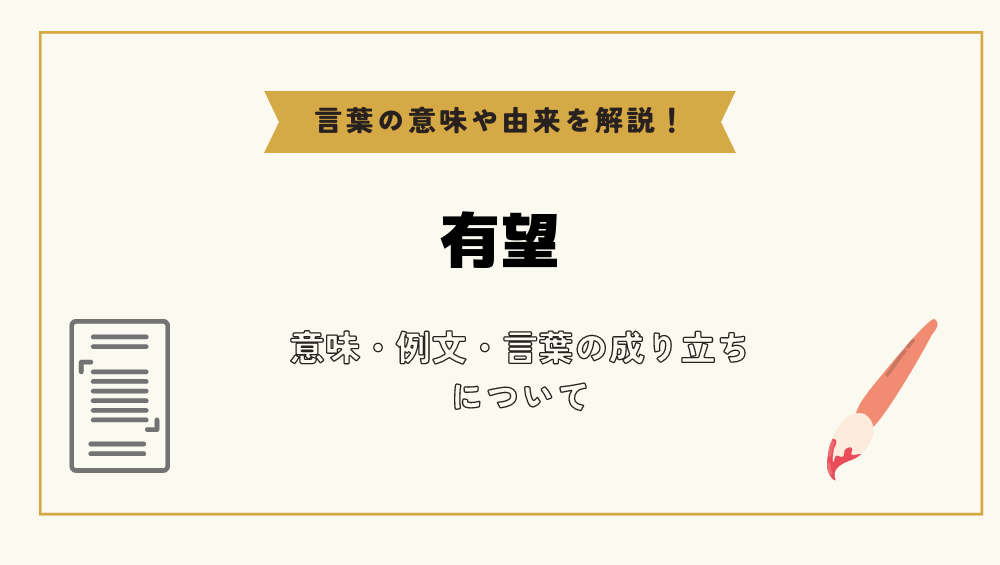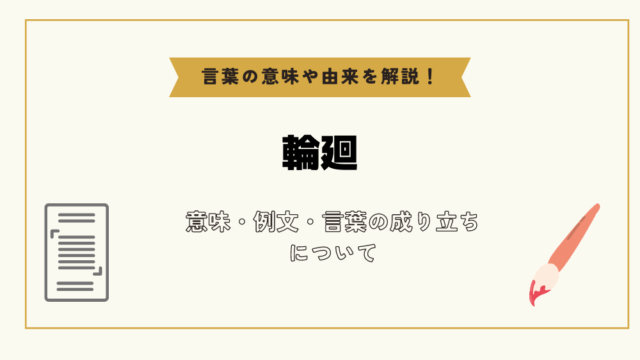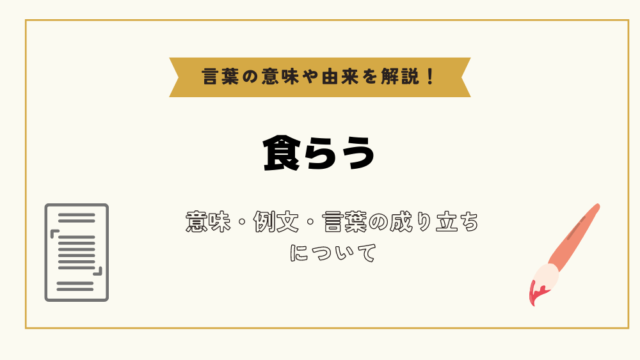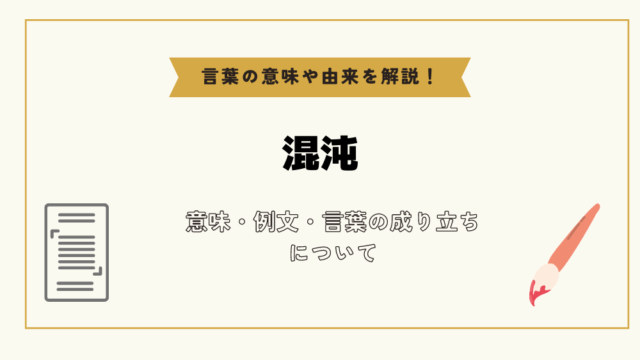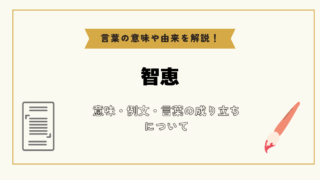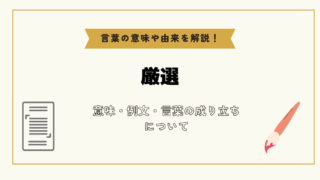「有望」という言葉の意味を解説!
「有望」とは、未来において成功や発展の可能性が高いさま、またはその見込みがある人・物・事柄を示す言葉です。この言葉には「望みを有する」という漢字そのままのニュアンスがあり、単にポジティブな評価というより、「根拠ある期待」を含む点が特徴です。たとえば若手社員が優れた成果を上げ続けている状況や、研究分野で新技術の実用化が近いケースなど、裏付けやデータがある場合に用いられます。
「将来性がある」「伸びしろが大きい」と言い換えられることも多く、客観的評価と主観的期待がほどよく混ざった言葉といえるでしょう。
もう一点重要なのは、「有望」は必ずしも現在の実績を示す言葉ではなく、あくまで“今後”に焦点を当てている点です。そのため目下の実績が十分でなくても、環境や潜在能力が評価対象となり得ます。場面によっては過度な期待をかけてプレッシャーになる場合もあるため、使い手の慎重さも求められる語です。
「有望」の読み方はなんと読む?
「有望」は音読みで「ゆうぼう」と読みます。多くの日本語学習者が混同しやすいのが「有望視(ゆうぼうし)」や「有望株(ゆうぼうかぶ)」などの複合語ですが、どれも「ゆうぼう」の読みに続く形で発音されます。
訓読みを交えた「あるのぞみ」という読み方は存在せず、常に音読みで統一されている点がポイントです。読み間違え例として「ありのぞみ」「ゆうもう」などが挙げられますが、これらは誤読です。
漢字構成を確認すると、「有」は「持っている」「存在する」を示し、「望」は「のぞむ」「希望」を示します。このため、「希望を持っている」→「将来に期待できる」という意味へ自然に派生しました。
発音上の注意として、アクセントは「ゆ↘うぼー↗」とゆるやかな下降上昇型(東京式アクセント)が一般的ですが、地域差はほとんどなく、どの地域でも「ゆうぼう」と伸ばす母音を明瞭に発音すれば誤解されることはありません。
「有望」という言葉の使い方や例文を解説!
最も一般的な用法は、人物や計画に対してポジティブな将来性を示す場面です。多くの場合、現在の評価だけでなく「今後の伸び」を示す文脈が必要になるため、根拠となる実績やデータを併記すると説得力が増します。またビジネス・スポーツ・学術研究など、目標が明確な分野で頻繁に登場します。
【例文1】この新人エンジニアは問題解決能力が高く、将来的にも有望だ。
【例文2】電気自動車市場は今後10年間、特に有望と見込まれている。
会話での使用時は相手にプレッシャーを与えないよう注意が必要です。「あなたは有望だから期待している」と言われる側が重荷に感じる場合もあります。評価対象が若年層なら、努力を労いながら具体的な支援策を添えると好意的に伝わります。
就職活動では「有望株」のように投資的比喩として使うことがありますが、金融業界では実際の株式と混同しやすいため、文脈を明確にしましょう。
「有望」という言葉の成り立ちや由来について解説
「有望」は、中国古典由来の熟語ではなく、日本で独自に派生した和製漢語とされています。「有」を前置し、所有や存在を示したあと「望」で未来への希望を表すという構造は、明治期以降に数多くつくられた近代漢語のパターンと一致します。
明治30年代の新聞記事に「有望の青年」といった表現が見られ、この頃には既に一般語として定着していたことが確認できます。同時期の教育・産業政策の文書にも多用されており、近代化の中で「人材育成」や「産業の将来性」を語る上で重宝された語だと推察されます。
また「有」が述語として「…がある」を示す漢文法の影響も受けています。「有志」「有識」「有能」などと同じ系統で、ポジティブな評価語を後置することで明確な意味を与える造語法です。よって「望みがある→有望」と自然に定着しました。
「有望」という言葉の歴史
近世以前の文献には「有望」がほとんど登場しません。江戸後期‐明治初頭の漢籍翻訳運動で「望有(ぼうゆう)」など中国語表現を逆順に再構成した結果、明治期に「有望」が成立したと考えられています。
1920年代には経済雑誌で「有望産業」「有望株」という語が頻出し、昭和期を通じてビジネス用語としての地位を確立しました。戦後の高度成長期には、技術革新や輸出産業を語る際の定番表現となり、1970年代の新聞データベースでも使用件数が急増しています。
現代に至るまで意味の大幅な変化はなく、「将来性」に関連する語として安定的に用いられてきました。ただしバブル崩壊後は、裏付けのない過度な期待を戒める文脈で「有望視されていたが…」と逆接的に使われるケースも増えています。
「有望」の類語・同義語・言い換え表現
「有望」と近い意味を持つ語には「将来有望」「前途洋々」「期待大」「伸びしろがある」「潜在力が高い」などがあります。これらの語は細かなニュアンスが異なり、「前途洋々」はより大きなスケール感、「伸びしろ」は数値化しにくい能力面を強調する傾向があります。
企業評価の文脈では「成長余地が大きい」「高成長ポテンシャル」など英語由来のカタカナ表現が登場することもありますが、日常会話では「見込みがある」で十分置き換えられます。ビジネスレポートでは「有望市場」「有望セグメント」と複合語化して使うと情報が簡潔にまとまります。
類語選択時は対象と時期を具体的に示すのがコツです。「今後3年で有望」「短期的には期待薄だが長期的には有望」など期間を限定すると、過度な一般論を避けられます。
「有望」の対義語・反対語
「有望」の対義語として最も一般的なのは「悲観的」「望み薄」「先行き不透明」などです。反対語を使う場合は、評価基準が主観に偏りやすいので、必ず数値や事実を添えて客観性を補強することが重要です。
【例文1】資金調達が難航しているため、この計画は現状では望み薄と判断される。
【例文2】市場規模の縮小が続いており、長期的にみても先行き不透明だ。
否定形で「有望ではない」と表現する場合もありますが、相手を必要以上に落胆させたり士気を下げたりしないよう配慮が求められます。くれぐれも人に向けて直接「あなたは有望ではない」と言うのは避け、改善策や代替案を示すことが大切です。
「有望」を日常生活で活用する方法
「有望」はビジネス文書だけでなく、家庭や教育現場でも役立つ言葉です。子どもの将来や趣味の成果を語る際に「有望」という言葉を選ぶと、適度にポジティブかつ具体的な期待を示せます。
ただし褒め言葉として使う場合は、具体的な長所や成果を必ず併記し、空虚な励ましにならないよう注意しましょう。
【例文1】数学コンテストで上位入賞したので、この分野で有望だと思う。
【例文2】マラソン大会で記録を更新し続けており、将来の選手として有望だ。
家計や投資の判断でも「有望」は便利です。「このNISA銘柄は安定配当で有望」「この副業プラットフォームは利用者数が伸びていて有望」など、比較的ライトな評価語として重宝します。言葉の重さを調整するには、「非常に」「かなり」「まずまず」など副詞でトーンを変えると良いでしょう。
「有望」という言葉についてまとめ
- 「有望」とは、将来の成功や発展が見込まれる状態を示す言葉。
- 読み方は「ゆうぼう」で、音読みで統一される。
- 明治期に定着した和製漢語で、「望みを有する」が語源。
- 裏付けある期待を示すため、使う際は根拠や期間を明示する必要がある。
「有望」は、ポジティブな未来像を端的に示せる便利な言葉ですが、濫用すると空疎な誉め言葉になりかねません。使用時は対象の実績やデータ、具体的な期間を添えて、根拠ある期待を示すことが大切です。
読み方は「ゆうぼう」とシンプルながら誤読もあるため、ビジネス文書やプレゼンでは発音にも注意しましょう。由来や歴史を踏まえると、近代日本の「人と産業の将来性」を語る中で生まれ育った語である点も理解できます。
最後に、プラス評価の言葉には責任が伴います。相手のモチベーションを引き出すためにも、具体的な支援やフィードバックをセットにして活用する姿勢が望まれます。