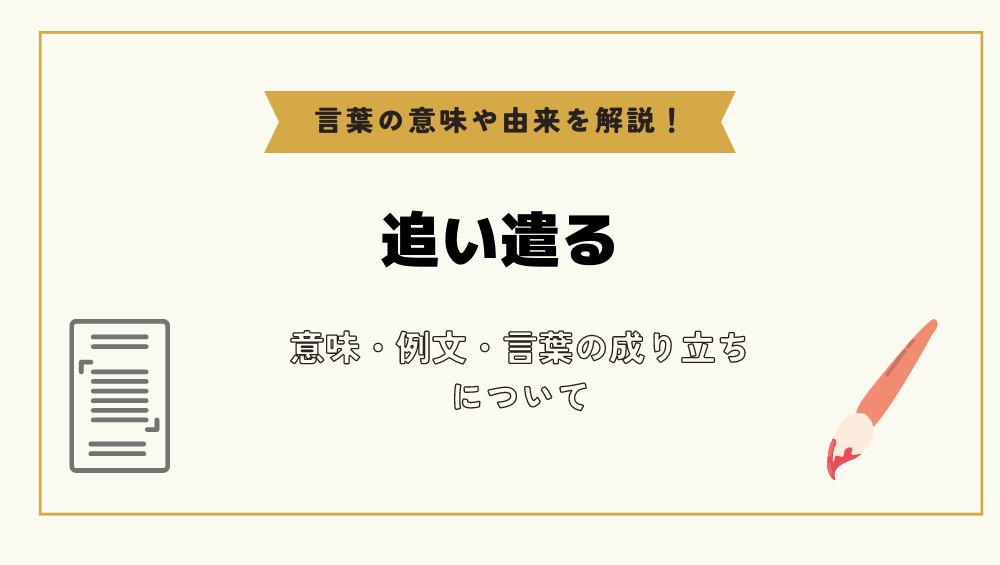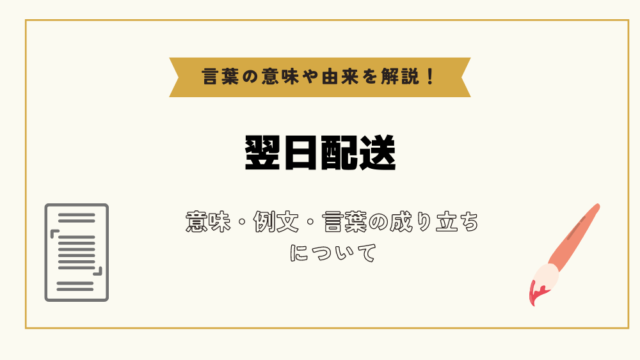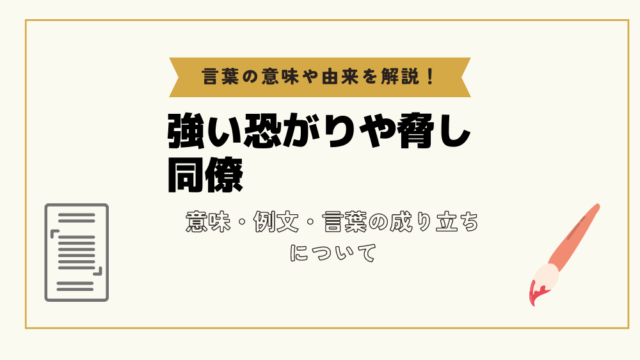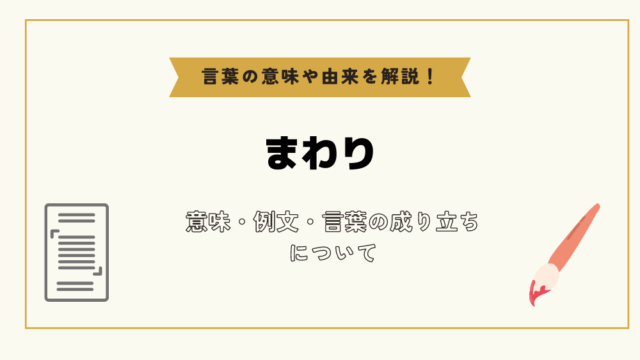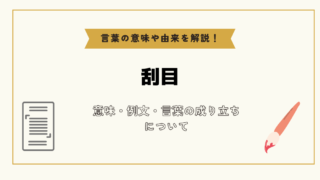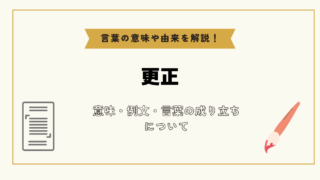Contents
「追い遣る」という言葉の意味を解説!
「追い遣る」という言葉は、相手を追い立てる、強制する、催促するといった意味を持ちます。
何かを早めにやらせたり、ある行動を起こさせるために、相手に圧力をかけることを指す言葉です。
例えば、上司がプロジェクトの締め切りを追い遣るとは、メンバーに対して早急な進捗報告や作業の追い込みを要求することを意味します。
「追い遣る」という言葉は、ポジティブな意味合いではなく、やや強引なイメージがあります。
相手を追い立てることで、なんとか目標を達成しようとするときに使われることが多いです。
追い遣るとは、人に圧力をかけて、ある行動を起こさせることを意味する言葉です。
。
「追い遣る」の読み方はなんと読む?
「追い遣る」は、「おいやる」と読みます。
音読みの「ついせん」という読み方もありますが、一般的には「おいやる」がよく使われています。
日本語には、漢字一文字で表わされる言葉が多いですが、「追い遣る」は二文字の漢字で表される特殊な言葉です。
そのため、読む際に戸惑う人もいるかもしれませんが、正しくは「おいやる」と発音します。
「追い遣る」は、「おいやる」と読みます。
。
「追い遣る」という言葉の使い方や例文を解説!
「追い遣る」は、人に圧力をかけて行動を起こさせるという意味の言葉です。
下記に使い方や例文を解説します。
・上司が部下を追い遣る。
。
上司が部下に対してプロジェクトの進捗状況報告を強く要求することで、スピードアップを図ります。
・販売促進のためにお客様を追い遣る。
。
営業担当者がお客様に対して特別なキャンペーンの案内や割引の情報を強くアピールし、購買意欲を高めることで、販売数を増やせるようにします。
・成績向上のために選手を追い遣る。
。
コーチが選手に対して厳しい練習スケジュールを課したり、パフォーマンスの向上を目指すための限界までの挑戦を促したりします。
「追い遣る」は、目標達成や成果向上のために圧力をかけることを指します。
上司が部下を追い遣る、営業担当者がお客様を追い遣るなど、様々な場面で使用されます。
。
「追い遣る」という言葉の成り立ちや由来について解説
「追い遣る」という言葉は、平安時代の漢文の文献に初めて登場しました。
元々は、仏教用語として使われ、魔除けの呪文として利用されていました。
また、室町時代になると、幕府や武士団体で用いられるようになり、相手を追い立てて行動させるという意味に変化していきました。
「追い遣る」は、明治時代以降、広く一般の日本語として使用されるようになりました。
現代では、ビジネスシーンや日常会話などで用いられることが一般的です。
「追い遣る」は、元々は仏教用語として使われていましたが、室町時代に使われ方が変化し、現代ではビジネスなど様々な場面で使用されるようになりました。
。
「追い遣る」という言葉の歴史
「追い遣る」という言葉は、古代の日本では使われていなかったと考えられています。
言葉の由来や成り立ちは、平安時代から室町時代にかけて形成されたと考えられています。
恐らく、インドや中国から伝わった仏教の教えや文献に由来していると考えられます。
仏教の呪文や修行法において、「追い遣る」という言葉が使われたことが、言葉の起源と考えられています。
時代の変化とともに、武士団体や政治組織などで使われるようになり、その後、広く一般の日本語として使用されるようになりました。
「追い遣る」という言葉は、古代の日本では使われていなかったと考えられており、平安時代から室町時代にかけて形成され、現代のビジネスシーンなどでよく用いられるようになりました。
。
「追い遣る」という言葉についてまとめ
今回は、「追い遣る」という言葉について解説しました。
「追い遣る」は、相手を追い立てて行動を起こさせるために圧力をかけるという意味を持つ言葉です。
上司が部下を追い遣る、営業担当者がお客様を追い遣るなど、目標達成や成果向上のために使われることが多いです。
また、「追い遣る」という言葉は、平安時代から室町時代にかけて形成され、現代の日本語に至るまで使用されるようになりました。
「追い遣る」という言葉は、相手を追い立てるために圧力をかけることで目標達成を目指すときに使われる言葉です。
また、古代から現代までの日本語の歴史の中で形成されました。
。