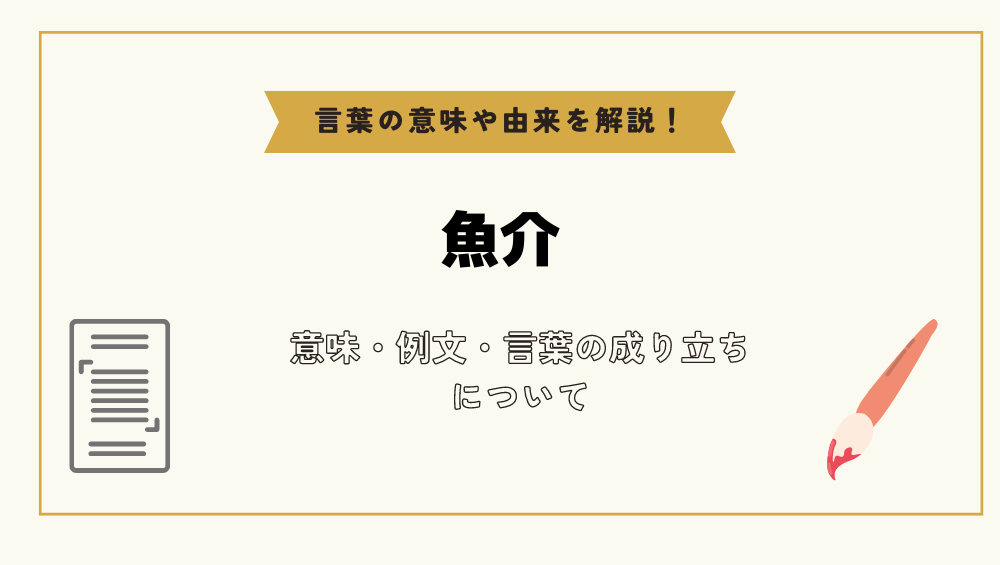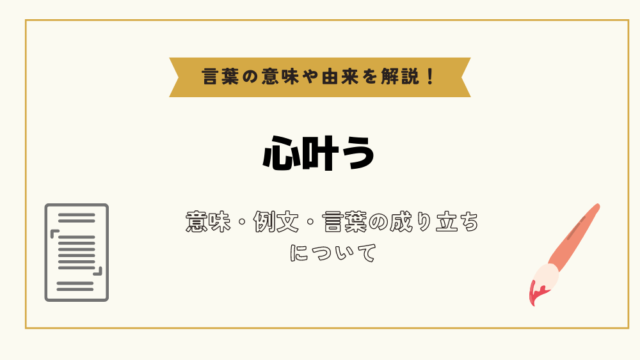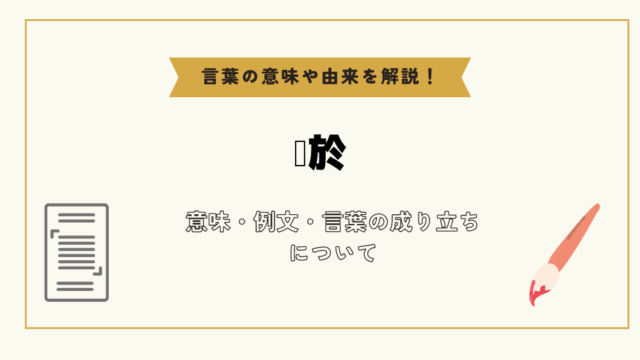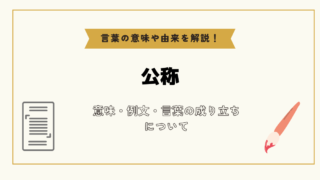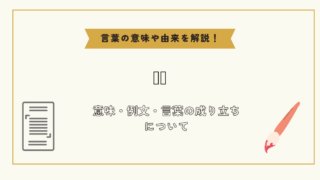Contents
「魚介」という言葉の意味を解説!
「魚介」とは、魚や海産物を指す言葉です。
海産物のうち、特に魚を中心にした食材を指すことが多いです。
新鮮な魚介類は栄養価が高く、美味しく食べられることから、日本料理やお寿司などでよく使われます。
また、魚介の中には貝やエビ、カニなども含まれており、その種類はさまざまです。
「魚介」という言葉の読み方はなんと読む?
「魚介」は、「ぎょかい」と読みます。
この読み方は漢字の音読みになります。
音読みは、漢字が表す意味や概念を表現するために中国語や漢語の音を取り入れたものです。
それによって、漢字を使っている言葉でも理解しやすくなります。
「魚介」という言葉の使い方や例文を解説!
「魚介」という言葉は、主に食材に関する文脈で使われます。
たとえば、「今晩のディナーには、新鮮な魚介を使ったお料理を作りたい」というように使われます。
また、「このレストランでは、地元の魚介を使った料理が人気です」というように、特定の地域で水産業が盛んな場合にもよく使われます。
「魚介」という言葉の成り立ちや由来について解説
「魚介」という言葉は、漢字の「魚」と「介」から成り立っています。
「魚」は、魚を意味し、「介」は、中間や仲介を意味します。
つまり、「魚介」とは、魚や海産物が中心となって仲介されるという意味になります。
この言葉は、日本の食文化において、魚介類が重要な役割を果たすことを表しています。
「魚介」という言葉の歴史
「魚介」という言葉の歴史は古く、日本の伝統的な料理や食文化に深く関わっています。
日本人は昔から海に恵まれており、魚介類を利用した料理は古くから存在していました。
江戸時代には、鮮魚や魚の「ひもの」が人々の食卓に並び、魚介を楽しむ文化が発展しました。
現代でも、市場やレストランなどで魚介類の新鮮な姿を見ることができます。
「魚介」という言葉についてまとめ
「魚介」という言葉は、魚や海産物を指す言葉で、日本料理やお寿司などでよく使われます。
読み方は「ぎょかい」であり、主に食材に関する文脈で使われます。
この言葉は、魚や海産物が中心となって仲介されることを表し、日本の食文化に深く関わっています。
歴史的にも古く、日本の伝統的な料理において重要な役割を果たしてきました。