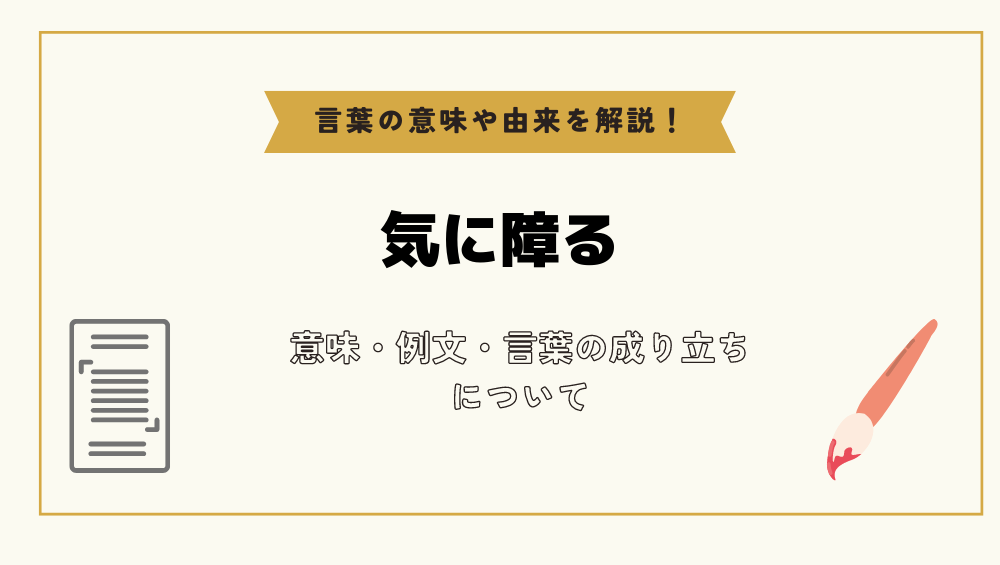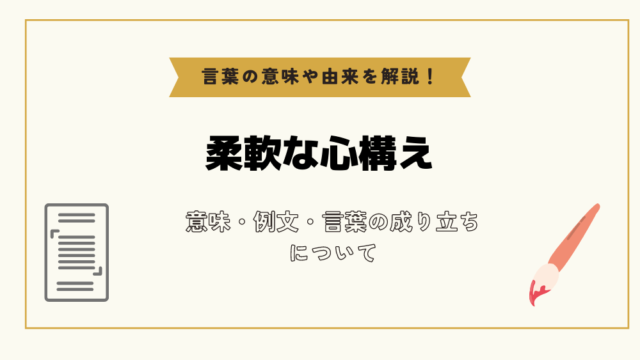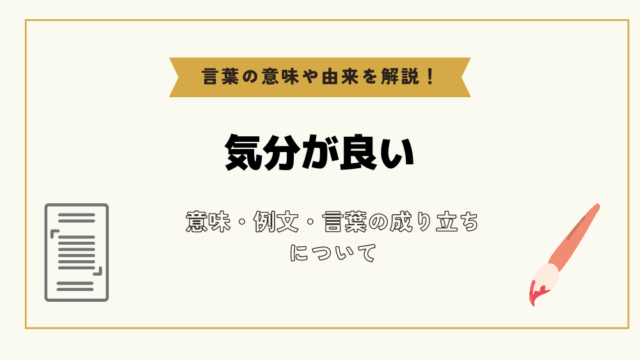Contents
「気に障る」という言葉の意味を解説!
「気に障る」という表現、一体どのような意味を持っているのでしょうか。
「気に障る」とは、他人の態度や発言、行動などが自分の気持ちに対して不快感を与えることを指します。
つまり、何かしらの原因で心のバランスが崩れたり、不快な感情が生まれたりすることを表現しています。
例えば、友人があなたの意見を否定したり、嫌なジョークを言ったりすると、「気に障る」と感じることがあります。
このような場合、他人の言動によって自分の心が傷ついてしまう感覚が生じるのです。
「気に障る」という表現は、他の人々とのコミュニケーションがある生活上では避けて通れないものです。
しかし、人それぞれ感じ方や敏感さが異なるため、誰かが「気に障る」と感じたことが他の人にとってはさほど問題ではない場合もあるのです。
「気に障る」の読み方はなんと読む?
「気に障る」という言葉は、そのまま「きにさわる」と読みます。
この表現は、意味に合わせて読んでいきます。
日本語には様々な読み方がある単語もありますが、「気に障る」はそういった変則的な読み方ではありません。
「きにさわる」と発音することで、他人の行動や言葉が自分に対して不快感を引き起こす現象をわかりやすく表現しています。
言葉にも響きがあり、聞いた人の心に訴える効果も秘めているのです。
「気に障る」という言葉の使い方や例文を解説!
「気に障る」という表現の使い方にはいくつかのパターンがあります。
例えば、「あの発言は私の気に障ってしまった」という表現があります。
このように、他人の言動が自分の心に不快感を与える場合や、心に傷を負った場合に「気に障る」という表現を用いることができます。
また、具体的な例文としては、「彼の冗談は私の気に障った」というように使用することができます。
このように、「気に障る」は主に他人との関係性やコミュニケーションの中で使用され、相手の行動や発言に対して感じる不快感を表現する際に使われるのです。
「気に障る」という言葉の成り立ちや由来について解説
「気に障る」という言葉は、古くから日本語に存在する表現です。
この言葉は主に江戸時代から使われ始め、現代まで受け継がれてきました。
「気に障る」という表現の成り立ちは、心のバランスや安定した状態を表す「気」に、何かしらの障害が生じることを意味する「障る」という言葉が組み合わさることによって生まれました。
つまり、心が傷ついたり、不快感を感じることが「気に障る」となるのです。
「気に障る」という言葉の歴史
「気に障る」という表現の歴史は、古くからさかのぼることができます。
江戸時代には既に使用され、文献や書物にも記録されていたことがわかっています。
当時は、人々が繁華街や飲み屋などに集まり、騒々しく遊んだり、議論を交わしたりする機会が多かったため、他人の言葉や行動による不快感を感じることが頻繁にありました。
このような状況から、「気に障る」という表現が人々の口語として広まり、日常的に使用されるようになったのです。
「気に障る」という言葉についてまとめ
「気に障る」という表現は、自分の気持ちに対して他人の態度や発言が不快感を与えることを指します。
他人との関係性やコミュニケーションの中で使用され、自分の心が傷つく状況を表現する際に使われる言葉です。
この表現の歴史は古く、江戸時代から使用されてきました。
人々が遊びなどで集まる中で他人の言動による不快感を感じる機会が多かったため、口語として広まりました。
今日でも日常会話や文章で一般的に使用される表現です。