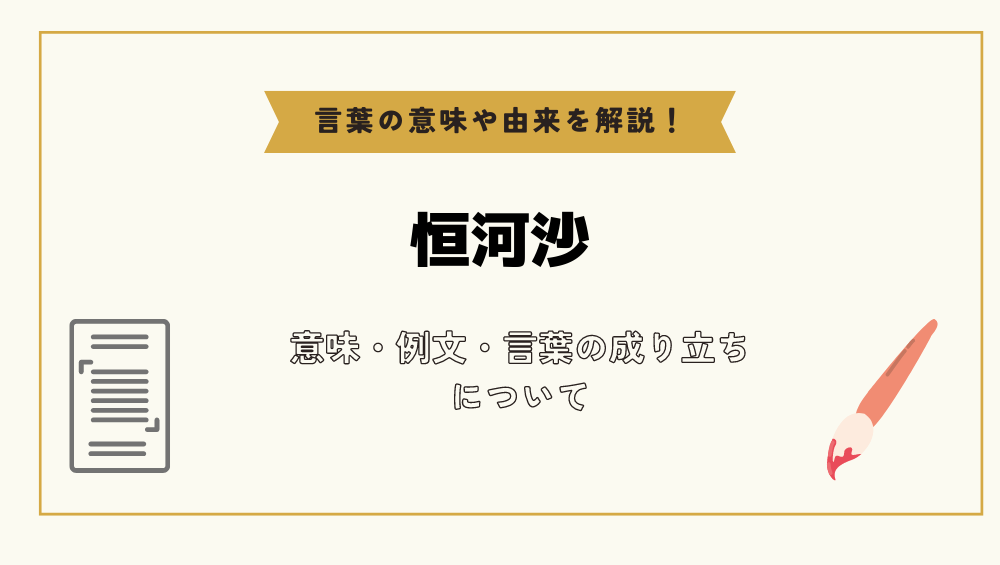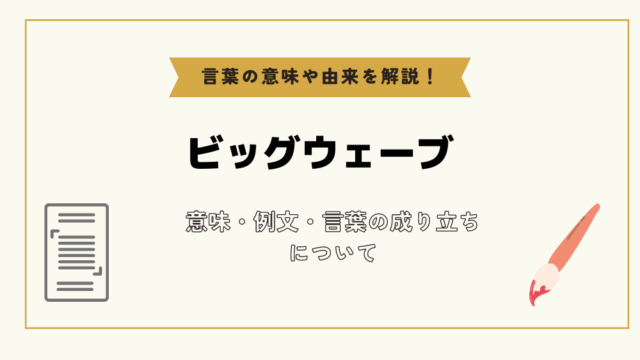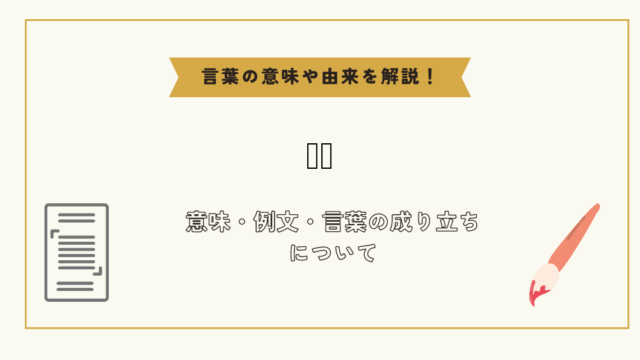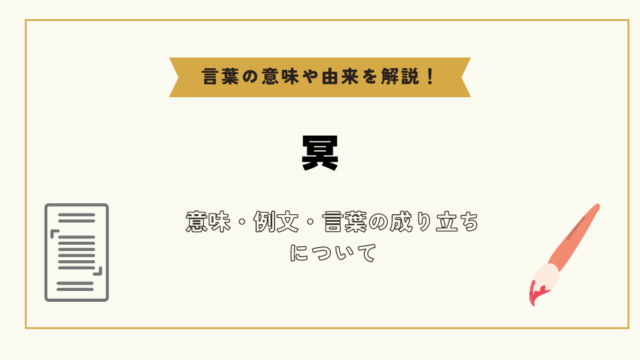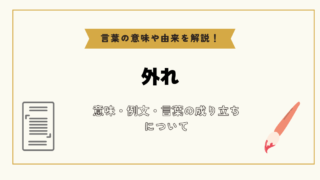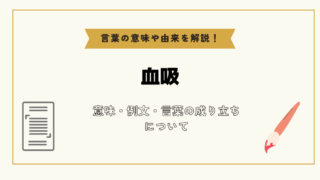Contents
「恒河沙」という言葉の意味を解説!
「恒河沙」は、仏教の教えに関連した言葉で、桁数の多さを表す単位の一つです。
具体的には、1の後に10 の68乗の桁が続くほどの大きな数を指します。
この数の大きさは、人の想像を超えるほどであり、あり得ないような大きな数の計算に使用されます。
「恒河沙」という言葉の読み方はなんと読む?
「恒河沙」の読み方は「ごうがしゃ」となります。
この読み方は、明治時代以降に生まれたものであり、それ以前の読み方は「こうがしゃ」でした。
仏教の教えは歴史が深く、時代によって読み方が変化することもあるのです。
「恒河沙」という言葉の使い方や例文を解説!
「恒河沙」という言葉は、一般的な日常会話ではあまり使われませんが、数学や物理学、統計学の分野で使用されることがあります。
「これは恒河沙よりももっと大きな数です」というように、他の数と比較する場合に使用されます。
また、「この問題は恒河沙の計算を必要とします」といったように、計算の規模が非常に大きいことを表現するためにも使われます。
「恒河沙」という言葉の成り立ちや由来について解説
「恒河沙」の成り立ちや由来については、古代インドのゴータマ・シッダールタ(仏教の開祖、釈迦牟尼)の教えに基づいています。
恒河沙は、ゴータマ・シッダールタが座禅を組んでいる間に、その前にあった恒河の砂粒が数え切れないほど統一されているさまを見て、数えきれないほど多いことを表現したのが由来です。
「恒河沙」という言葉の歴史
「恒河沙」の単位は、中国の数学書や仏教の経典に初めて登場しました。
中国では、恒河沙が数え切れないほどの多さを表す最大の単位とされています。
その後、この単位は仏教の教えが広まるにつれて、東アジア全体に広まっていきました。
現代でも、科学や技術の分野で使用されています。
「恒河沙」という言葉についてまとめ
「恒河沙」という言葉は、桁数の多さを表す数の単位であり、仏教の教えに由来しています。
その成り立ちや歴史にも古代の教えや中国の数学書が関わっています。
現代の科学や技術の分野で使用されることがあり、計算の規模が非常に大きいことを表現するために使われます。