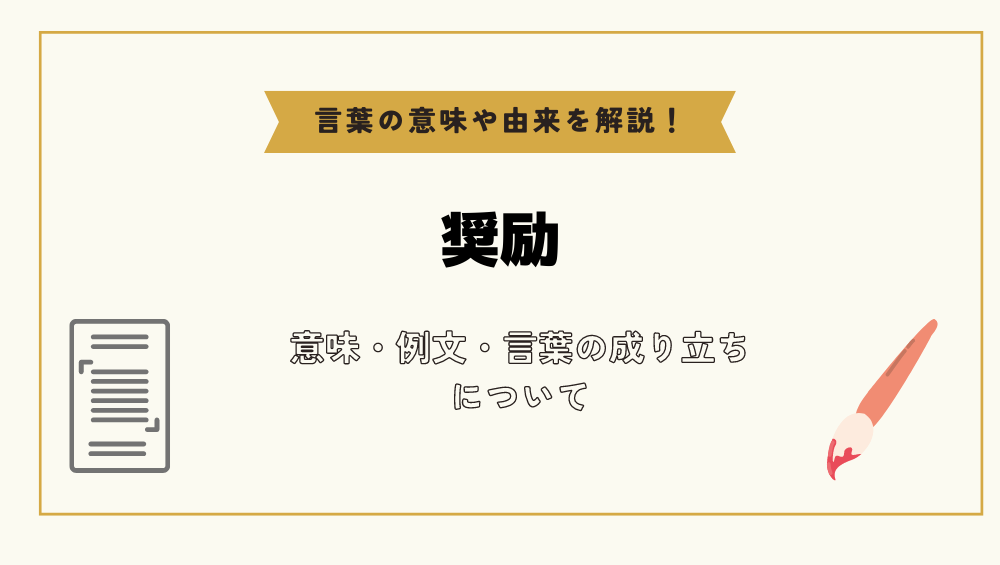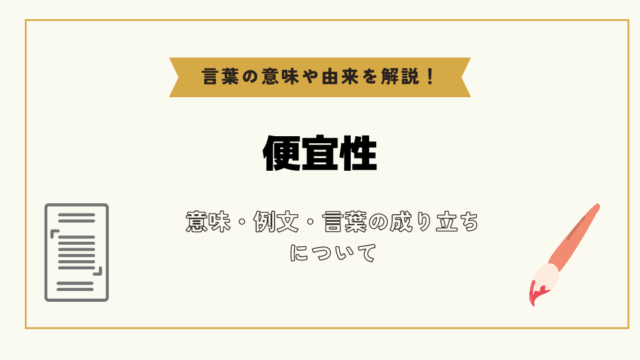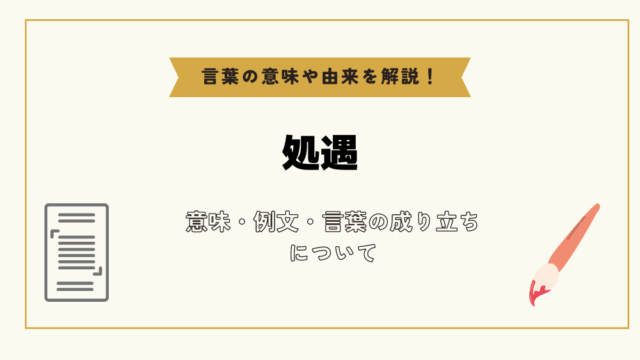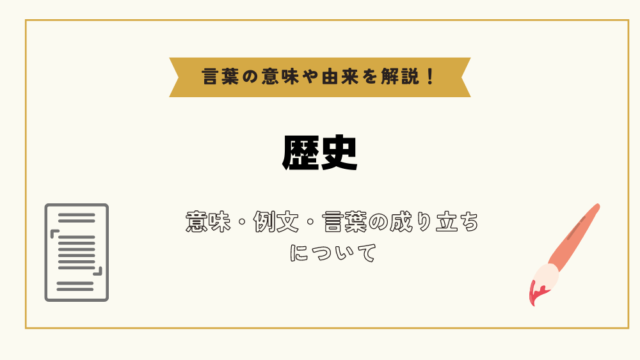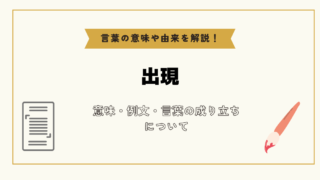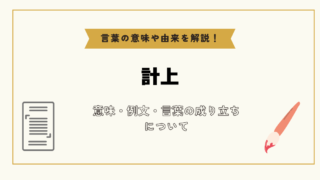「奨励」という言葉の意味を解説!
「奨励」とは、望ましい行動や態度、取り組みを積極的にすすめて励ますことを意味する日本語です。この語は、相手に対して「その方向で進んでほしい」「もっとやってみよう」と背中を押すニュアンスを含みます。具体的には、学習の促進、健康管理の推奨、技術革新の支援など、目的達成に向けた意欲を高める場面で使われます。似た言葉に「推奨」「促進」がありますが、「奨励」は励ましの気持ちが強く込められている点が特徴です。行政文書や学術論文から、ビジネスメール、日常会話まで幅広く用いられる言葉と言えるでしょう。
奨励の目的は大きく二つに整理できます。一つ目は「個人の行動変容」を促すこと。例えば自治体が住民に運動を奨励する場合、健康増進が狙いです。二つ目は「社会的課題の解決」を図ること。企業の環境対策を奨励する制度などが典型例です。目的達成のためには、言葉だけでなく報奨金や表彰制度を組み合わせるケースも多く見られます。
「奨励」の読み方はなんと読む?
「奨励」は音読みで「しょうれい」と読みます。「奨」の字は「すすめる」「助ける」を表し、「励」の字は「つとめる」「はげます」を意味します。読み方としては「しょう」と「れい」を区切らず一息で発音するのが自然です。日常会話では口語的に「奨励する」という動詞形で用いることが多く、敬語表現では「奨励いたします」と変化します。
読み間違いとして「しょうれ」や「しょうれえ」と語尾が伸びる例が見られますが、正しくは「しょうれい」と明瞭に発音してください。ビジネスシーンで誤読すると信頼性に関わるため注意が必要です。なお、英語に訳す際は「encourage」「promote」など状況に応じた単語を選びます。
「奨励」という言葉の使い方や例文を解説!
「奨励」は動詞「奨励する」「奨励している」の形で使い、対象となる行為や政策を後ろに取るのが基本です。ビジネス文書では「社員の資格取得を奨励する」、行政文書では「ごみの分別を奨励しています」のように用います。話し言葉では「もっと勉強を奨励されたよ」など柔らかい表現も可能です。
【例文1】自治体は住民に自転車通勤を奨励している。
【例文2】上司はメンバーの自主的な提案を奨励したい。
これらの例文に共通するポイントは、「誰が」「何を」奨励しているかを明確に示すことです。また、対象が抽象的な概念でも「環境保護活動の奨励」のように名詞化して使えます。補助金や表彰制度を組み合わせる場合は「奨励金」「奨励賞」という派生語も頻出です。
「奨励」という言葉の成り立ちや由来について解説
「奨励」は漢字「奨」と「励」を組み合わせた熟語で、いずれも古代中国の律令制度下で使用された歴史をもちます。「奨」は「将」に「人を引き連れる」の意が派生し、唐代には「推挙する」「助力する」意義が確立しました。「励」は「石を磨くさま」を象る象形文字に由来し、「力を尽くす」という意味が発展したとされます。
日本へは奈良時代の漢籍伝来と共に伝わり、律令制文書で「農民を奨励して耕作を増やす」などの表現が確認されています。つまり、当初から政策的ニュアンスで用いられていたのが特徴です。その後、近世の寺子屋や藩校で「学問奨励」「武芸奨励」という言葉が普及し、明治以降の近代化政策で一般社会へ広がりました。
「奨励」という言葉の歴史
奨励は奈良時代から現代に至るまで「望ましい行為を後押しする言葉」として連綿と受け継がれてきました。古文献では『続日本紀』(8世紀)に「田租を減じて農を奨励す」との記述が見られ、当時すでに農業振興策として使われていたことがわかります。江戸期には藩単位で「殖産興業奨励書」が発布され、養蚕・製茶など地域産業の発展に寄与しました。
明治政府は富国強兵の一環として「勧農奨励」「工業奨励」を政策化し、これが現代の「奨励金」「奨励賞」の制度的源流となります。戦後は高度経済成長を支えるため、科学技術奨励や中小企業技術改善奨励など多様な分野へ拡大しました。つまり奨励は社会変革の節目で重要な役割を果たしてきた言葉なのです。
「奨励」の類語・同義語・言い換え表現
奨励の類語には「推奨」「促進」「奨励」とほぼ同義で使われる「奨励策」などがあります。「推奨」は良さを認めてすすめる意味が強く、プロダクトやサービスの推薦に適します。「促進」は行為を速めるニュアンスがあり、政策文書で「雇用促進」が代表例です。「激励」は精神的な支援に重きがあり、スポーツ選手を励ます場面など感情的な側面が際立ちます。
言い換えを行う際は、対象の性質と期待する効果を整理すると選択が容易です。「資金提供を伴う場合は奨励金を交付する」と書けば制度の存在が明確になり、「率先垂範を推奨する」と書けば模範行動を求める意図が伝わります。同義語の中でもニュアンスの違いに留意しましょう。
「奨励」の対義語・反対語
奨励の対義語として代表的なのは「抑制」「禁止」「制止」です。「抑制」は過度な行為を控えさせる意味で、環境負荷の抑制などネガティブな方向へ力をかける点が奨励と対照的です。「禁止」は法律や規則によって行為を完全に止めることを指し、奨励の「すすめる」と真逆の立場に位置します。「制止」は実力を用いて止めるニュアンスがあり、緊急性の高い状況で使われます。
用語選択を誤ると意図が正反対になるため注意が必要です。例えば「飲酒を奨励する」と書くと勧める意味になりますが、本来「飲酒を抑制する」としたいケースも多いでしょう。文章作成時は目的に沿った語を用いてください。
「奨励」を日常生活で活用する方法
日常生活で奨励を活用するコツは、自分や他人の行動をポジティブに変える「言葉+仕組み」をセットで設計することです。たとえば家族の読書習慣を奨励したい場合、読んだ冊数ごとに小さなご褒美を設定する「読書スタンプカード」を用意します。自分自身に対しては「1日10分の運動を奨励する」と目標を宣言し、達成度をアプリで記録すると実行率が上がります。
また、友人同士で新しい趣味を始める際に「互いに奨励し合う」ことで継続しやすくなります。言葉だけでは効果が薄れることがあるため、具体的な目標と評価基準、達成後のメリットを明示するのがポイントです。学校では先生が「質問することを奨励します」と促すだけで生徒の積極性が高まる例もあります。奨励は相手の自主性を尊重しながら背中を押す万能ツールと言えるでしょう。
「奨励」という言葉についてまとめ
- 「奨励」とは、望ましい行動を積極的にすすめて励ますこと。
- 読み方は「しょうれい」で、動詞形は「奨励する」。
- 奈良時代の律令制から現代の政策まで連綿と使われてきた。
- 用いる際は目的と手段を明確にし、対義語と混同しないよう注意。
奨励は古代から現代まで社会の方向性を示し、人々の行動を前向きに変えてきたキーワードです。読み方や由来を理解し、類語・対義語と区別して使うことで文章の説得力が高まります。
ビジネスでも日常でも「奨励」は相手を尊重しつつ背中を押す便利な表現です。目的を明確にし、仕組みや報酬を組み合わせれば、より実効性の高い奨励策を設計できます。