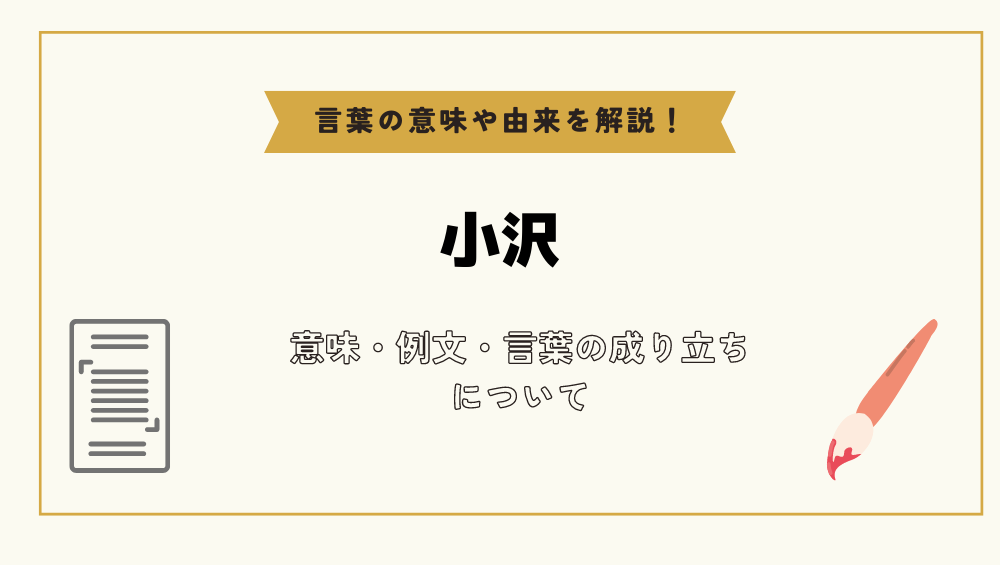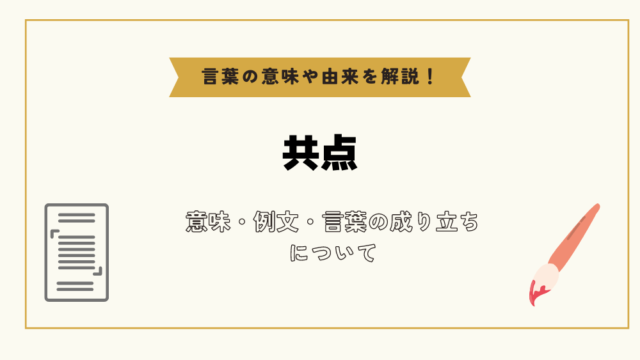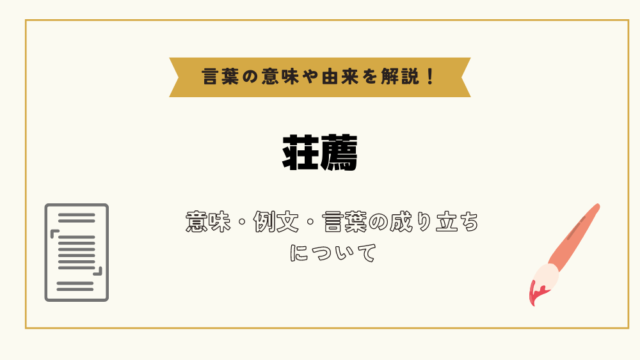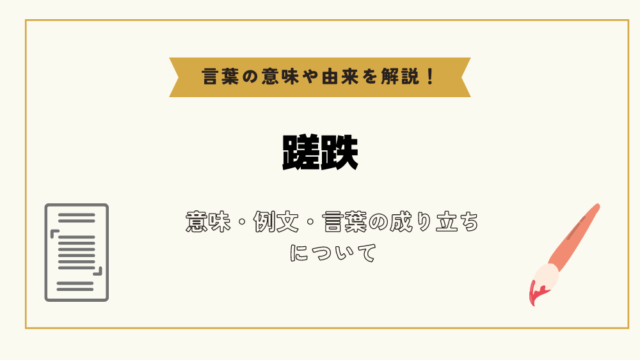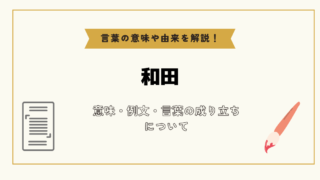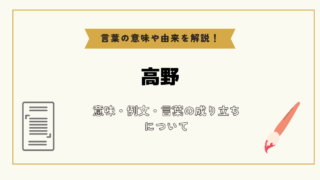Contents
「小沢」という言葉の意味を解説!
「小沢」という言葉は、「幼い川」という意味を持ちます。
その由来は、小さな川や小川を指していることが多く、川の小ささを強調するために「小」の字が冠されています。
日本には大小さまざまな川がありますが、そのなかでも特に小さな川を指して「小沢」と呼ぶことが多いです。
「小沢」の読み方はなんと読む?
「小沢」の読み方は「こざわ」と読みます。
漢字の「小」と「沢」をそれぞれ読んだものです。
「こ」は「小きい」や「小さな」という意味を表し、「ざわ」は「川」という意味を表しています。
このように「小沢」という言葉は、小さな川を示すために使われることが多いです。
「小沢」という言葉の使い方や例文を解説!
「小沢」という言葉は、主に小さな川を指し示すために使われます。
例えば、「散歩中に小沢を見つけた」というように、自然環境や風景の中で出会った小さな川を表現する際に使われます。
また、「小沢のせせらぎが心地よい」というように、小さな川の音が心地よいと感じる場面でも使用されます。
「小沢」という言葉の成り立ちや由来について解説
「小沢」という言葉の成り立ちや由来については、明確な情報はありません。
一般的に、「小」は「小さい」という意味を持ち、「沢」は「川」という意味を持つ漢字です。
そのため、小さな川を強調するために「小」の字が冠されて「小沢」という言葉が生まれたと考えられています。
「小沢」という言葉の歴史
「小沢」という言葉の歴史については、古くから存在していると考えられています。
日本は川の多い国であり、大小さまざまな川が存在します。
そのなかでも特に小さな川を指し示す際に「小沢」という言葉が使われるようになったのではないでしょうか。
古くから人々が自然環境を表現する中で用いられてきた言葉と言えます。
「小沢」という言葉についてまとめ
「小沢」という言葉は、小さな川を指し示すために使われる言葉です。
「こざわ」と読みます。
自然環境や風景の中で出会った小さな川を表現する際に使われることが多く、その音や風景が心地よいと感じる場面でも使用されます。
由来や成り立ちについては明確な情報はありませんが、日本の川の多さから自然に生まれた言葉と考えられています。