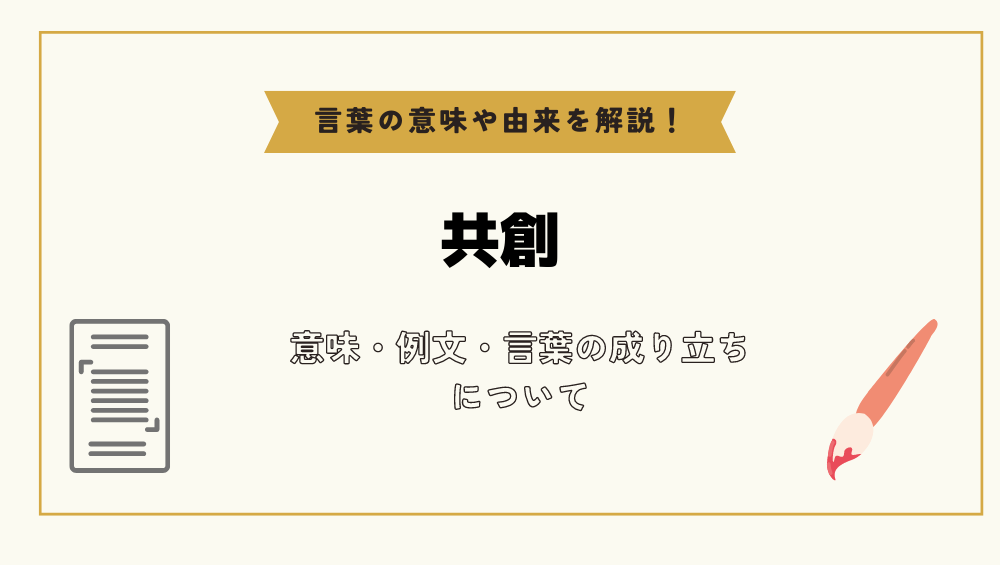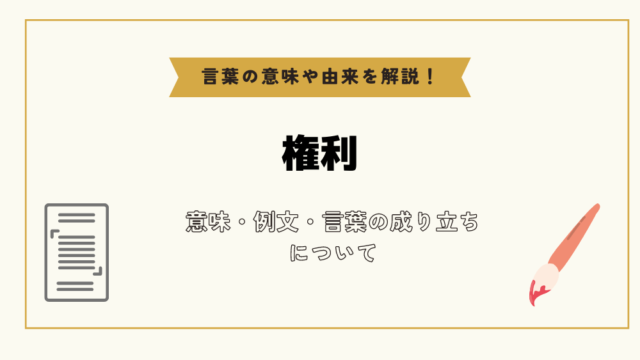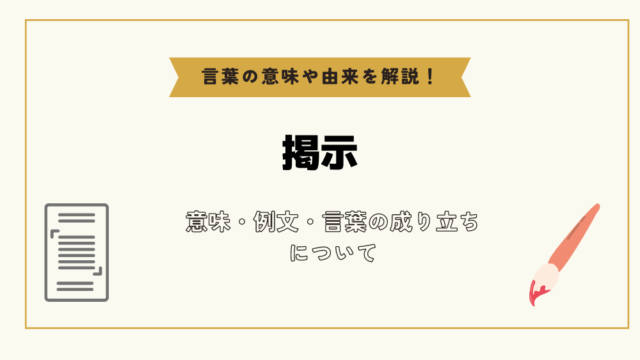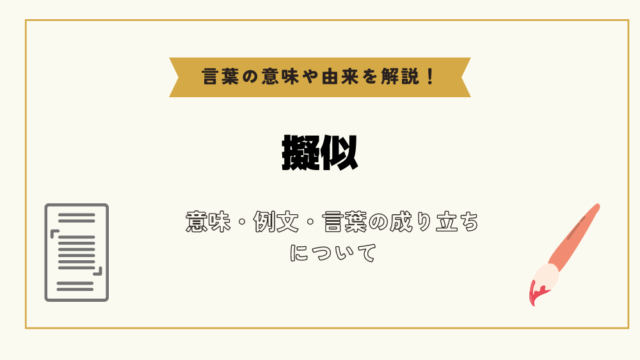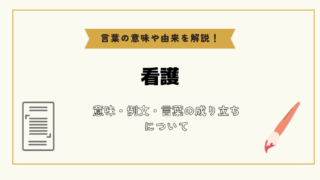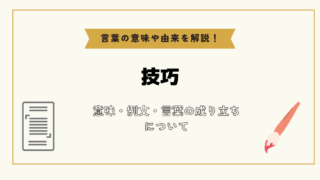「共創」という言葉の意味を解説!
共創とは、立場や組織を超えた複数の主体が互いの知識・資源を持ち寄り、新しい価値や解決策を一緒に生み出す行為を指します。この言葉の中核にあるのは「共同で創造する」という発想であり、単なる協力や分担とは異なり、成果物そのものが相互作用から生まれる点が特徴です。ビジネスだけでなく教育、まちづくり、芸術など幅広い分野で使われています。
共創には「対等性」と「相互補完性」が不可欠です。上下関係や発注‐受注の関係ではなく、お互いの立場や文化を尊重しながら補い合う姿勢が求められます。このため、ゴール設定も一緒に行うケースが多く見られます。
さらに、共創は「イノベーション創出の手段」として注目されています。ユーザーや市民、自治体を巻き込むことで、多面的な視点が取り入れられ、従来の組織単独の開発よりも質の高いアウトプットが期待できるとされています。
共創のプロセスは大きく「関係構築」「共通課題の発見」「アイデア共創」「試作・実装」の4段階に整理されることが一般的です。それぞれの段階で継続的な対話が行われることで、暗黙知の共有と信頼醸成が進みます。
つまり共創は、人と人、組織と組織の重なり合う部分を広げながら、新しい未来像を共に描き、実際に形にしていくプロセス全体を表す言葉なのです。
「共創」の読み方はなんと読む?
「共創」は一般的に「きょうそう」と読みます。漢字表記は「共に創る」と書くため、「ともづくり」と読まれることも稀にありますが標準的ではありません。経営学やデザイン学ではアルファベット表記で「Co-creation」と紹介される場面も増えました。
日本語の「共に」「創る」という熟語が組み合わさっているため、漢字のイメージからすんなり読みやすい単語です。ただしビジネス文書ではひらがなやカタカナを交えず、正式に「共創」とするのが一般的です。
読みを確認するときは「競争(きょうそう)」と混同しやすいため、発音時にアクセントを変えたり文脈で差を示したりする配慮が大切です。英語の「co-creation」と対比して説明すると誤解を減らせます。
「共創」という言葉の使い方や例文を解説!
共創はプロジェクト説明や提案書のほか、日常の会話でも使われます。使いどころは「共に価値を生む場面」であり、「協力」や「共同開発」では語り切れない深い協働ニュアンスを含みます。
【例文1】大学と地域企業が共創し、地元産品の新ブランドを立ち上げた。
【例文2】私たちはユーザーとの共創を通じてアプリを改善している。
【例文3】行政・民間・市民が共創するワークショップが開催された。
【例文4】共創の場では上下関係を持ち込まない姿勢が求められる。
例文に共通するのは「誰かと一緒に創る」という主体性の共有であり、結果だけでなく過程も価値とみなす点がポイントです。
ビジネスメールでは「◯◯社様と共創し、次期サービスを検討しております」のように丁寧語とあわせて使われます。レポートや論文では「顧客共創価値」や「エコシステム共創」という複合語も頻出です。
「共創」という言葉の成り立ちや由来について解説
「共創」はもともと日本語圏の学術・実務の中で生まれた比較的新しい造語です。1990年代の経営学で「顧客参加型価値創造」が議論される中、「Co-creation」の邦訳として「共創」が広まりました。
漢字の選定には「共」のもつ共同・共有のイメージと、「創」のもつゼロから形を成すイメージが合わさることが深く関与しています。協業や共同開発ではなく、価値そのものを新たに生み出す意味を強調するために「創」の字が選ばれました。
つまり、「共創」という漢字表記は英語の概念を輸入・再解釈し、日本文化に即してアレンジした結果生まれた言葉と言えます。翻訳語でありながら、日本固有の「和を尊ぶ」価値観と親和性が高く、定着が進みました。
「共創」という言葉の歴史
共創という言葉が文献に現れ始めたのは1990年代後半です。当時、P.コトラーらが提唱した「価値共創(Value Co-creation)」理論がマーケティング界で紹介され、日本企業の顧客参加型戦略に影響を与えました。
2000年代にはIT技術の発展によりオープンソース開発やクラウドソーシングが一般化し、共創は「オープンイノベーション」と並ぶキーワードとなりました。政府方針でも「産学官民の共創拠点整備」が盛り込まれ、公共政策にも浸透しています。
2020年代に入るとSDGsやESG経営が重視され、社会課題解決に向けたマルチステークホルダー連携の文脈で共創が一層脚光を浴びています。パンデミック下でオンライン協働が加速したことも追い風となりました。
「共創」の類語・同義語・言い換え表現
共創の近い表現には「協創」「協働」「共同開発」「共同創造」などがあります。英語では「Co-creation」の他に「Co-design」「Co-innovation」も使われ、設計や技術寄りのニュアンスが強まります。
類語はいずれも「複数主体による価値創出」を示すものの、役割分担の度合いや参加者の対等性が異なるため、文脈に応じて選択する必要があります。例えば「協働」は現場での作業連携を指す場合が多く、「共創」は戦略フェーズから深く関与するニュアンスがあります。
ビジネス文書で言い換える際は、企業文化や目的に合わせて「オープンイノベーション」「パートナーシップ開発」などの用語を併記すると誤解が少なくなります。
「共創」の対義語・反対語
共創の明確な対義語は定義上存在しませんが、概念的には「単独創造」「内製主義」「排他的開発」などが反対のベクトルを示します。これらは外部との連携を避け、自組織だけで価値を生む姿勢を強調します。
共創が「開かれた創造」なら、対義概念は「閉じた創造」と捉えると理解しやすいでしょう。ただし実務では両方を使い分ける場面も多く、共創と単独開発は相補的に存在しています。
「共創」と関連する言葉・専門用語
関連用語としては「エコシステム」「ユーザーイノベーション」「リビングラボ」「ソーシャルイノベーション」などがあります。いずれも利害関係者が集い、新しい価値を創出する枠組みを指しています。
専門分野では「サービスドミナントロジック(SDL)」が共創を理解する理論背景として知られています。SDLは「価値はサービスの利用過程で顧客と共に創られる」と定義し、従来のモノ売りモデルを再構築しました。
共創を推進する際は、これら関連概念を組み合わせることで、より実践的で再現性の高いプロジェクト設計が可能になります。
「共創」が使われる業界・分野
共創はIT、製造、医療、教育、都市計画、エンターテインメントなど多様な分野で活用されています。たとえば自動車業界ではサプライヤーやスタートアップと共創し、次世代モビリティを開発しています。
医療分野では患者、医師、製薬企業が共創し、治療アプリや新サービスを開発しています。また、地方創生プロジェクトでは自治体と市民団体、大学が共創し、地域課題の解決を図っています。
共創は「課題の複雑性が高く、一社だけでは解決できない領域」で特に威力を発揮するため、今後も対象業界は広がると予想されています。
「共創」という言葉についてまとめ
- 「共創」の意味は、複数主体が対等な関係で新たな価値を共に創り出すこと。
- 読み方は「きょうそう」で、英語ではCo-creationと表記する。
- 1990年代に英語圏の概念を邦訳し、日本文化に適合させた造語として広まった。
- ビジネスからまちづくりまで幅広く活用されるが、協力と競争を混同しない注意が必要。
共創は協業以上、競争未満の関係性を築きながら、参加者全員にメリットのある成果を創り上げるためのキーワードです。実践の場では対話と信頼構築が最重要であり、形だけの「一緒にやりましょう」では成果が生まれません。
今後、社会課題が複雑化するにつれて、共創の価値はさらに高まります。読者の皆さんも組織や立場を超えたパートナーを見つけ、共創的なアプローチで新しい未来を切り開いてみてください。