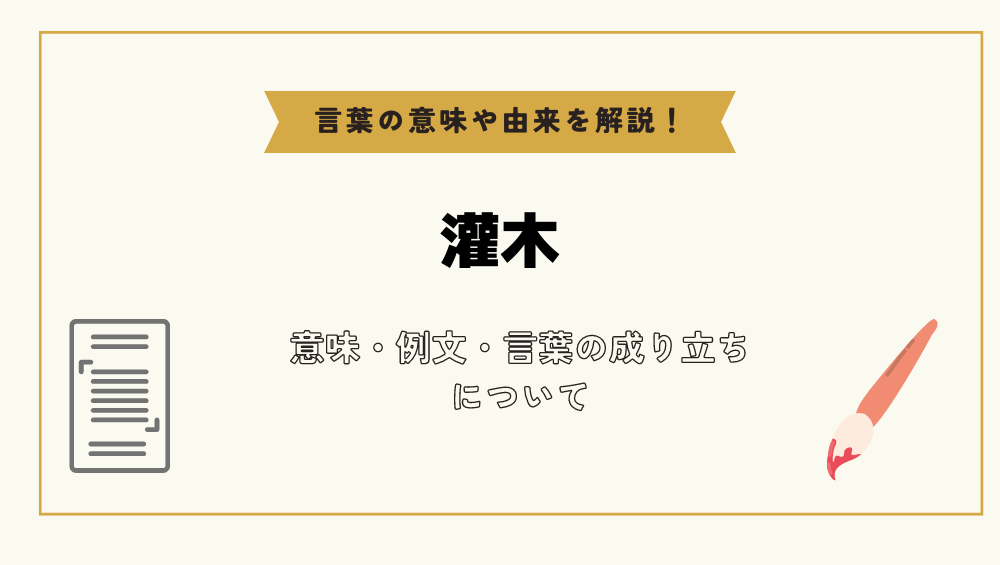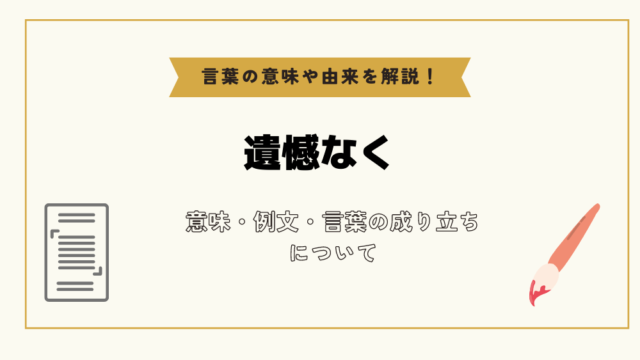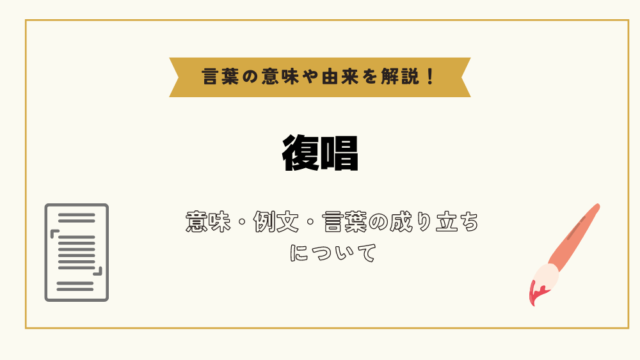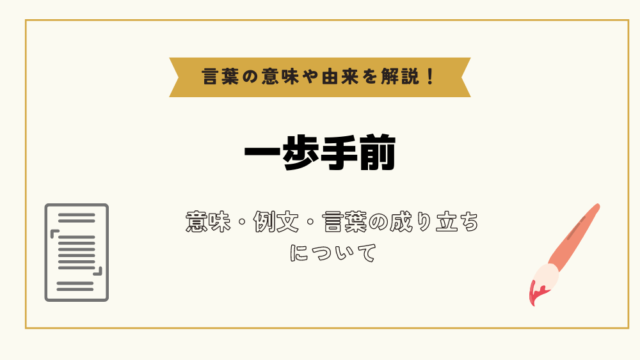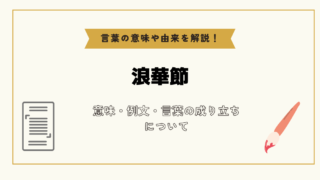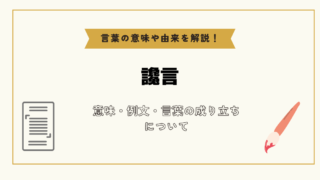Contents
「灌木」という言葉の意味を解説!
。
灌木(かんぼく)とは、木の一種で、大きさや形が小さく、多くの枝葉を持ち、背が低い特徴を持つ植物のことを指します。
灌木は一般に、樹木に比べて成長が早く、密生していることも多いです。
また、森林や庭園、公園などの緑地において、景観を彩る重要な役割を果たしています。
「灌木」という言葉の読み方はなんと読む?
。
「灌木」は、「かんぼく」と読みます。
この言葉は、漢字の「灌」が「流し込む」という意味で、「木」が「樹木」という意味を持つことから、水を一定の量をまるで川のように樹木に与えることで植物が育つという意味を表しています。
「灌木」という言葉の使い方や例文を解説!
。
「灌木」という言葉は、主に植物学や園芸などの専門分野で使用されますが、日常会話でも使われることがあります。
例えば、庭に灌木を植えると、緑のカーテンや目隠しになり、より美しい庭を演出することができます。
また、公園や道路沿いに灌木が植えられることで、景観の保全や騒音の軽減などの効果も期待されます。
「灌木」という言葉の成り立ちや由来について解説
。
「灌木」という言葉の由来については、詳しいことはわかっていませんが、漢字の「灌」が「流し込む」という意味を持つことから、水をまるで川のように樹木に与えて栽培することからこの言葉が使われるようになったと考えられています。
灌木には生命力が強く、どんな環境でも育つ能力があることから、人々にとって貴重な存在として扱われてきました。
「灌木」という言葉の歴史
。
「灌木」の言葉の歴史については、古くは日本の古典文学や古事記などにも登場しています。
これらの文献によると、灌木は神聖視され、森林の中にある神聖な存在として崇められていました。
また、仏教の影響を受け、庭園や寺院などにおいても灌木が植えられるようになり、美しい景観を楽しむための重要な要素となってきました。
「灌木」という言葉についてまとめ
。
「灌木」という言葉は、小さな木で多くの枝葉を持ち、背が低い植物を指します。
庭園や公園、緑地などでよく見かける灌木は、環境の保全や景観の演出に重要な役割を果たしています。
日本の古典文学や古事記にも登場し、神聖視されてきた灌木は、現代でも私たちの生活に彩りを与える存在です。