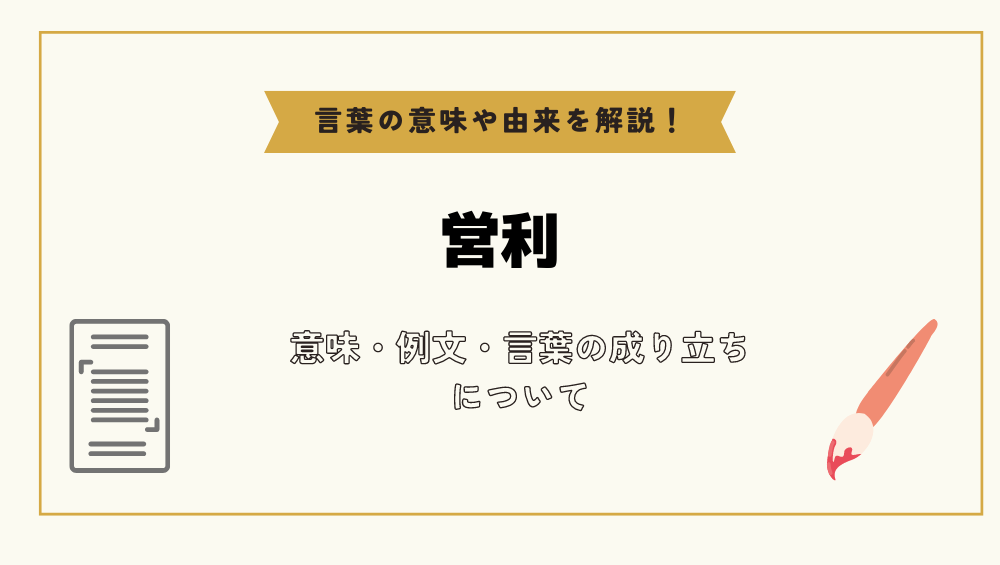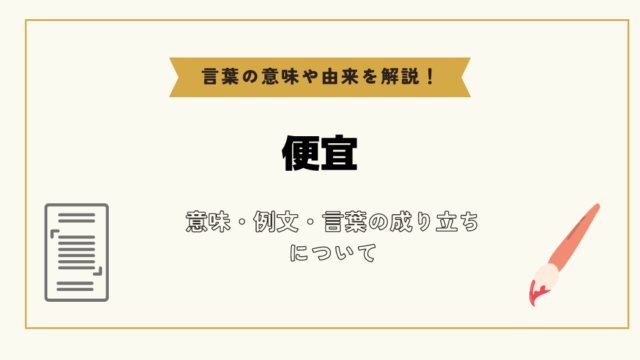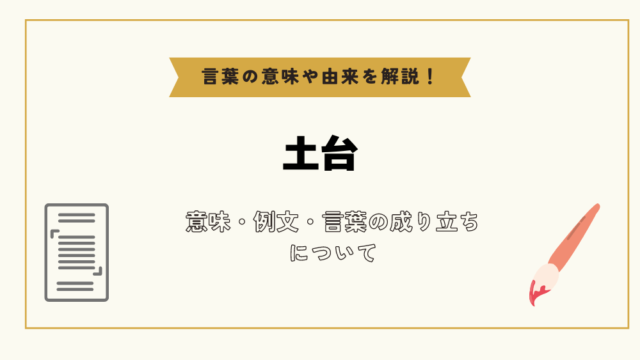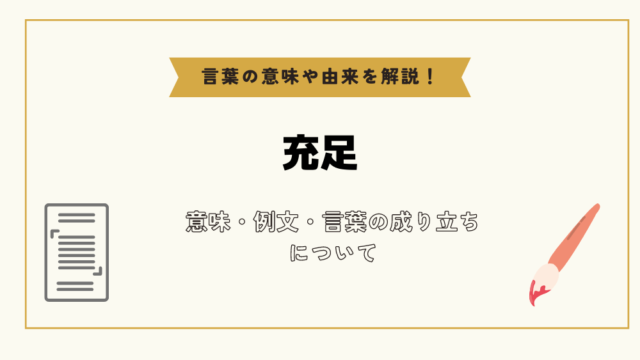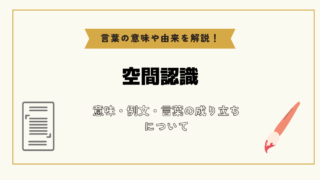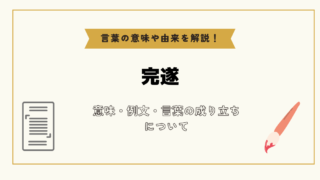「営利」という言葉の意味を解説!
「営利」とは、財貨やサービスを提供することで得られる利益を追求し、組織や個人の経済的な目的を達成しようとする行為や姿勢を指す言葉です。これには会社のような法人だけでなく、個人事業主や副業を行う個人も含まれます。収入を得るという点では共通していますが、営利活動は法律や社会規範の枠内で行う必要があります。
営利という概念は単に「お金もうけ」を意味するだけではありません。組織運営の持続可能性や、投資家・従業員・顧客といったステークホルダーの利益をどうバランスさせるか、という経営哲学の話にもつながります。特に株式会社の場合、株主への利益還元が主要な目的に位置づけられている点が特徴的です。
多くの国では、営利組織が社会的責任を果たすよう法規制が整備されています。日本でも会社法や消費者契約法、金融商品取引法などが営利活動の透明性や適正さを確保しています。このように営利は経済活動の中心にありながら、公共性との調和が常に求められている概念です。
「営利」の読み方はなんと読む?
「営利」は音読みで「えいり」と読みます。「営」は「営む(いとなむ)」の音読みで「えい」、「利」は「利益(りえき)」の音読みで「り」です。日常的に使われる言葉ですが、漢字表記のままだと読みづらいと感じる人も少なくありません。
類似の語に「利益(りえき)」や「収益(しゅうえき)」がありますが、「営利」は動詞的ニュアンスを含み、あくまで「利益を得ること」を目指す行為や活動を示します。そのため会話では「営利目的」「営利企業」のように用いられる場合が圧倒的に多いです。
一方で法律や行政文書では平仮名で「えいり」と書くことはほとんどなく、漢字表記が原則になっています。読みに迷ったときは、音読みをそのまま当てはめるのが確実です。
「営利」という言葉の使い方や例文を解説!
使い方のポイントは「営利目的かどうか」を明示し、活動の性質を区別するところにあります。例えばイベントやサービスが無料で提供されていたとしても、スポンサー料によって利益を得る場合は営利活動に該当します。
【例文1】この団体は営利目的ではなく、寄付金のみで運営している。
【例文2】新しいアプリは無料だが広告収入で営利を上げている。
メールや企画書では「営利目的のセミナー」「非営利的なプロジェクト」のように対比させて使うと分かりやすいです。ビジネス現場では、営利性の有無が税制や補助金の対象可否に直結するため、言葉の正確さが求められます。
またSNS投稿でも「これは個人の趣味であり営利目的ではありません」と明記することで、無用なトラブルを避けられます。法律的に微妙なラインの二次創作や中古販売では、営利かどうかが判断基準になるケースが多いので注意しましょう。
「営利」という言葉の成り立ちや由来について解説
「営利」は中国古典に由来する熟語で、古代中国の経済思想を示す文献にすでに登場しています。「営」は「営(いとな)む」、つまり事業を行う意で、「利」は利益や利得を示します。漢字二文字が合わさり「事業を営み利益を得る」という意味を凝縮しています。
日本には律令制の導入とともに漢籍がもたらされ、律令官職の中でも特に交易や税収に関わる部署で「営利」という概念が用いられました。江戸時代には商人階級の台頭によって、営利行為を肯定的に捉える商道徳が発達し、石田梅岩の『都鄙問答』などで議論されています。
明治以降は株式会社制度が導入され、「営利会社」という言い方が法律用語として定着しました。このように、中国由来の言葉が日本の経済制度の発展とともに再解釈されながら受け継がれてきた経緯があります。
「営利」という言葉の歴史
古代中国では「利」を求める行為がしばしば道徳的に問題視されました。孔子は「君子は義に喩り、小人は利に喩る」と説き、営利を低く見る傾向がありました。しかし戦国時代の商鞅や韓非子は統治の観点から利の追求を肯定的に捉え、国家財政を潤す手段としました。
日本では奈良・平安期の朝廷財政が米や絹を基盤としたため、営利は限定的でしたが、鎌倉末期から室町期にかけて座や港湾都市が発展し、商業活動とともに「営利」の語も広まりました。江戸時代の幕府は商人に対して公事方御定書で取引ルールを定め、営利を一定範囲で認可します。
近代になると「営利=資本主義の原動力」という見方が浸透し、戦後の高度経済成長期には国民的合意として営利企業が社会を豊かにするという価値観が形成されました。現在ではCSRやESG投資の文脈で、「営利」と「社会的価値」の両立が再び問い直されています。
「営利」の類語・同義語・言い換え表現
類語として最も一般的なのは「営収」「営業利益」「収益」など、財務諸表で使われる専門用語です。他にも「利潤」「利益追求」「ビジネス目的」「商業目的」など、多彩な言い換えが可能です。ニュアンスの違いを意識すれば、文章の説得力が高まります。
例えば「収益」は企業活動全体から得た総合的な金銭的成果を指し、「営業利益」は本業による利益を限定的に示します。「利潤」は経済学で用いられる語で、資本家が得る超過利益に焦点を当てています。
文脈に応じて使い分けると、専門性と親しみやすさを両立できます。金融機関向けの資料なら「収益性」、行政文書なら「利益確保」、一般向けのブログ記事なら「お金もうけ」と表現しても伝わりやすいでしょう。
「営利」の対義語・反対語
営利の対義語は「非営利(ひえいり)」が最も代表的です。非営利組織は利益を構成員で分配せず、社会的ミッションの実現に再投資する形態を指します。その他に「公益」「慈善」「無償」「ボランティア」なども反対概念として挙げられます。
非営利だからといって赤字で良いわけではなく、持続的に活動するためには黒字経営が求められる点に注意が必要です。営利か非営利かの違いは、利益の「分配先」によって区別されると覚えておくと便利です。
反対語を理解することで、営利の定義が一層クリアになります。ビジネスプランを作成するときは、自社が営利主体なのか、社会的企業としての側面が強いのかを明示すると、ステークホルダーの理解を得やすくなります。
「営利」を日常生活で活用する方法
日常生活ではフリマアプリやネットオークションで不要品を売ることがあります。このとき販売益が継続的かつ多額になると「営利目的」と見なされ、税務申告が必要になります。趣味の範囲なのか営利なのか、基準を意識するだけでトラブルを回避できます。
また町内会のバザーで手作り品を売る場合、売上を地域行事に再投資するなら非営利ですが、個人の収入になる場合は営利です。日常の小さな活動でも「営利かどうか」を意識すると、自分の立場が整理できます。
副業を始めるときは、開業届の提出タイミングや帳簿付けの方法を検討しましょう。領収書やレシートを保管し、年末に確定申告を行うことで、税制上の優遇措置を受けられる場合もあります。営利を正しく扱うことは、お金のリテラシー向上にもつながります。
「営利」についてよくある誤解と正しい理解
「営利=悪」というイメージは根強いですが、実際には営利活動が雇用を生み社会を支えています。倫理的でない企業活動が報道されると、営利全体が悪いように誤認されることが多いのです。営利そのものは価値中立であり、問題は手段と透明性にあります。
もう一つの誤解は「非営利は儲けてはいけない」というものですが、黒字がなければ施設維持もサービス拡充も不可能です。非営利組織でも有給職員を雇い、市場価格でサービスを提供するケースは珍しくありません。
営利・非営利の線引きは法律や会計基準で定義されますが、一般の人が理解しやすい情報提供が不足しているのも事実です。正確な知識を持つことで、クラウドファンディングや寄付先を選ぶ際の判断力が向上します。
「営利」という言葉についてまとめ
- 「営利」とは利益を目的に事業を営む行為・組織を指す経済概念。
- 読み方は「えいり」で、法律・ビジネス現場では漢字表記が基本。
- 中国古典に由来し、日本では株式会社制度の確立で一般化した。
- 現代はCSRや税務申告など、営利か否かの線引きが実務上重要。
営利という言葉は、単なるお金もうけを超えて、組織運営や社会的責任と深く結びついています。正しい定義と歴史的背景を知ることで、ビジネスの全体像が見えやすくなります。
また日常生活でも、副業やフリマ取引など営利の境界線に触れる機会が増えています。営利を正しく理解し、透明性を確保することで、自分自身と社会の双方にメリットをもたらす行動が取れるでしょう。