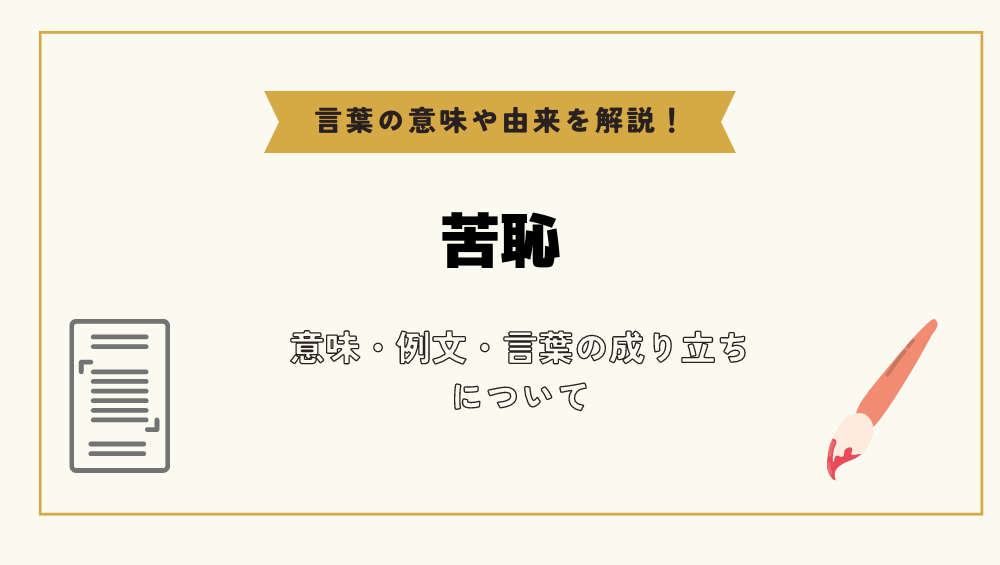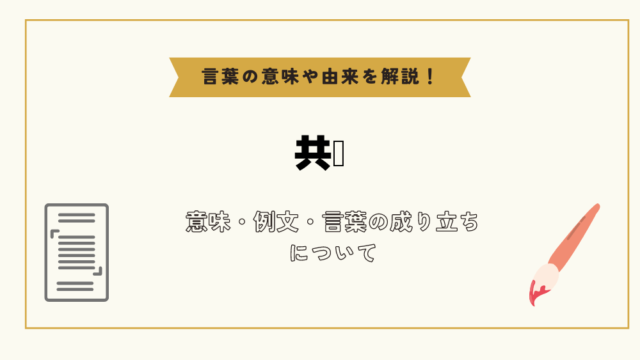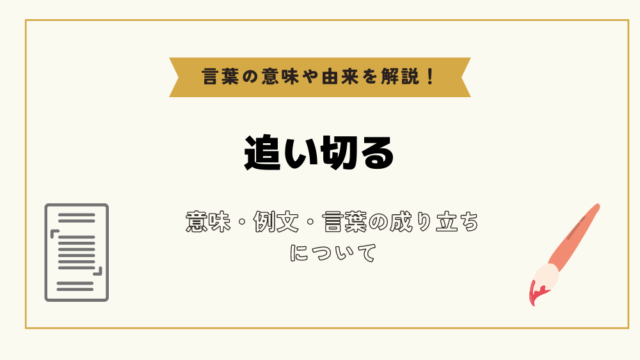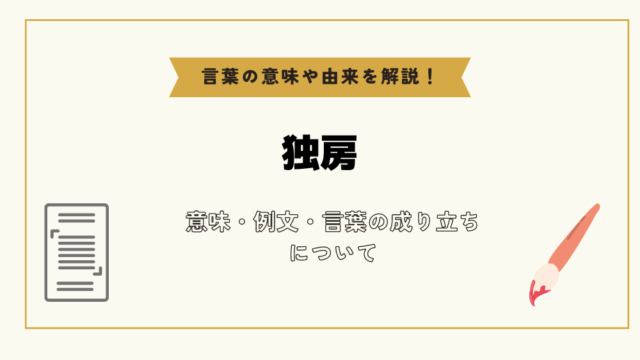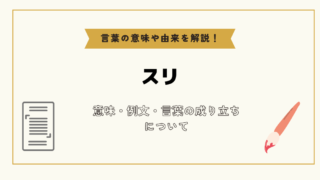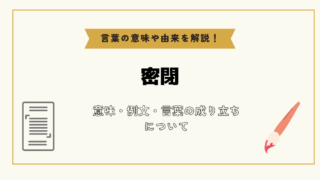Contents
「苦恥」という言葉の意味を解説!
「苦恥」という言葉は、日本語で使われる表現であり、恥じ入ることや後悔することを指します。
何か自分自身の言動や行為に対して、恥ずかしいと感じたり、反省したりする気持ちを表現する際に使われる言葉です。
例えば、失敗した時や過去の行動を振り返った時に、自分自身に苦しみや恥ずかしさを感じる場合に使われます。
苦恥の意味は、自分自身が過ちを犯したり、不適切な行動をとったりしたことによって、内心の中で苦しみや恥ずかしさを感じることを意味します。
「苦恥」という言葉の読み方はなんと読む?
「苦恥」という言葉は、かちと読みます。
読み方は、日本語の音読みのルールに基づいています。
‘苦’は「く」、’恥’は「ち」と読むため、「くち」と合わせて「かち」と読むことになります。
「苦恥」は「かち」と読みます。
。
「苦恥」という言葉の使い方や例文を解説!
「苦恥」という言葉は、普段の会話や文章で幅広く使われる表現です。
例えば、仕事で大きなミスをした際には「大失敗してしまって、苦恥を感じています」というように使うことができます。
また、自分の過去の行動を反省する際には「あの時の自分の行動には苦恥を感じています」というようにも使えます。
「苦恥」の使い方の一例:
。
・ 失敗したことを苦恥と感じる
。
・ 過去の自分に苦恥を感じる
。
・ 若気の至りを苦恥と思う
。
・ 恥じるべき行為に苦恥を感じる
。
「苦恥」という言葉の成り立ちや由来について解説
「苦恥」は、漢字の組み合わせで構成されています。
‘苦’は困難なことやつらいことを表し、’恥’は恥ずかしいと感じることを意味します。
これらの漢字を組み合わせることで、自分自身が過ちを犯したり、恥ずかしい思いをしたりすることによって生じる苦しみや恥ずかしさを表現しています。
「苦恥」という言葉は、漢字の組み合わせによって形成されました。
。
「苦恥」という言葉の歴史
「苦恥」の歴史は古く、日本の古典文献にも登場する言葉です。
古代の人々は、個人の名誉や社会的な評価を重んじる風土があったため、「苦恥」という言葉が生まれました。
人々は、自分自身が恥じ入ることや後悔することが大切であり、そういった内省の精神を持つことが美徳とされました。
「苦恥」という言葉は古代から存在し、内省の精神を表しています。
。
「苦恥」という言葉についてまとめ
「苦恥」という言葉は、自分自身が失敗したり、恥ずかしい思いをしたりした時に感じる苦しみや恥ずかしさを表現する言葉です。
読み方は「かち」と読みます。
日本語の言葉の中で幅広く使われ、自己反省や過去の行動を振り返る際によく使われます。
その由来は古代にまでさかのぼり、内省の精神を表す言葉として長い歴史を持っています。