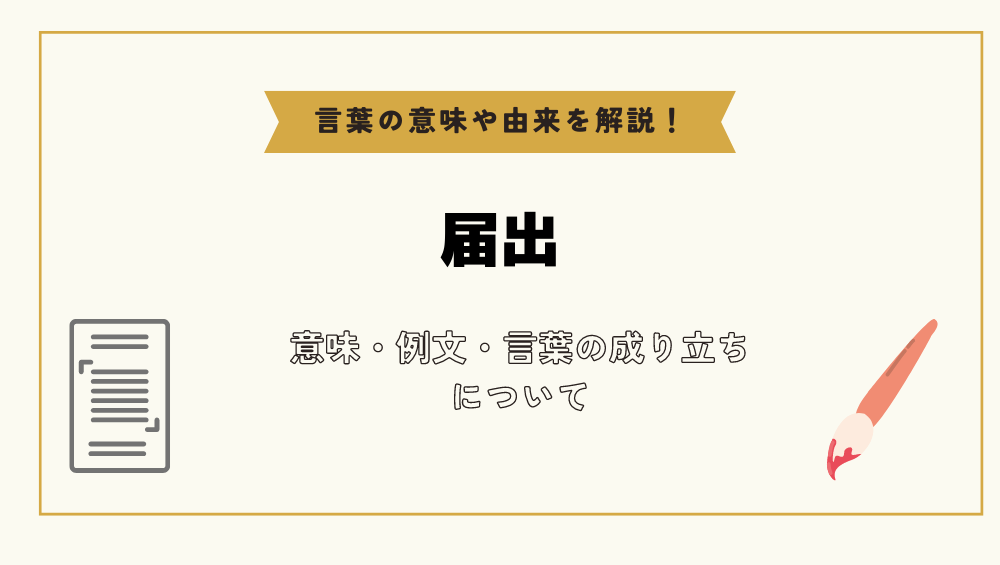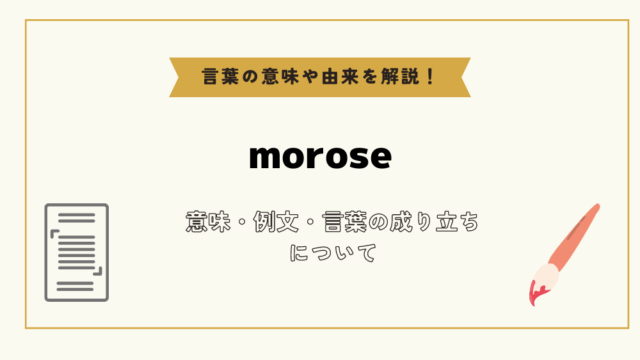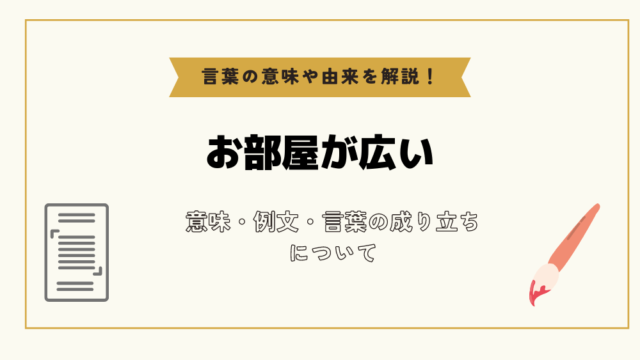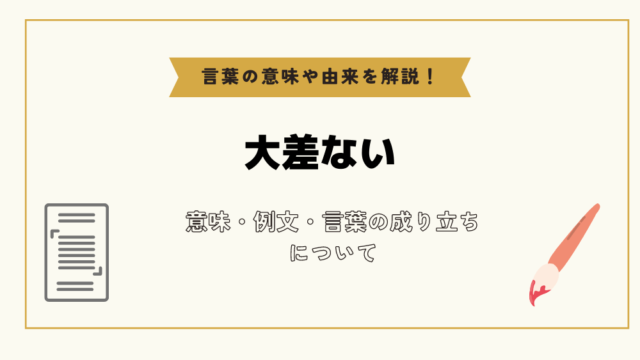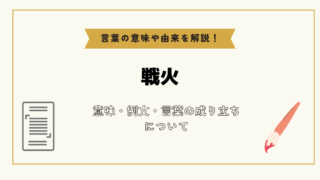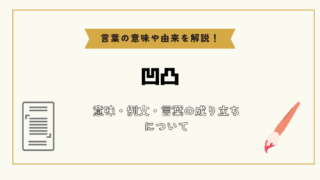Contents
「届出」という言葉の意味を解説!
「届出」という言葉は、何かを公的な機関や団体に報告したり申請したりすることを指します。
具体的には、法律で定められた手続きを踏んで、特定の事実や情報を公に認可してもらうことです。
例えば、結婚や出産、住所変更などの個人の変更届や、商売を始める際の設立届、著作物の著作権登録などが「届出」の一例です。
「届出」の読み方はなんと読む?
「届出」の読み方は、「とどけで」と読みます。
「届出」という言葉の使い方や例文を解説!
「届出」は、法律や公的機関に対して特定の情報を提出する際に使われます。
例えば、結婚する場合には結婚届を提出し、「届出をする」と言います。
また、自営業を始める場合には設立届を提出し、「届出を出す」と言います。
例文としては、「新しい住所に引っ越したので、住民票の移動届を役所に届出した」というような使い方が一般的です。
「届出」という言葉の成り立ちや由来について解説
「届出」は、日本語の「届く」と「出す」の言葉が組み合わさってできた言葉です。
「届く」とは、物や情報などが特定の目的や宛先に到達すること。
「出す」とは、物や情報を特定の場所や相手に向けて送ることを意味します。
「届出」の成り立ちは、何かを特定の機関に提出し、それが受け取られる過程を表しています。
また、この言葉によって報告や申請などの公的な手続きを明確化し、社会の秩序や法的な信頼性を保つ役割を果たしています。
「届出」という言葉の歴史
「届出」という言葉は、江戸時代の徳川幕府の役所や村役場などで、人々が様々な申請や報告をする際に使用されていました。
当時は「届」という漢字のみが使用されていたとされています。
明治時代になると、洋式の行政組織が整備されるにつれて、「出す」という意味の「出」を追加して「届出」と表記されるようになりました。
現代日本でも「届出」は広く使われており、法律によっても定められた行政手続きの一環として重要な意味を持っています。
「届出」という言葉についてまとめ
「届出」という言葉は、公的な手続きで特定の情報を提出することを指します。
結婚や出産、住所変更など、個人や事業者が法律に基づいて行わなければならない手続きの一環として用いられます。
この言葉の成り立ちは、「届く」と「出す」という意味が組み合わさってできたものであり、社会の秩序や法的な信頼性を保つ役割を果たしています。