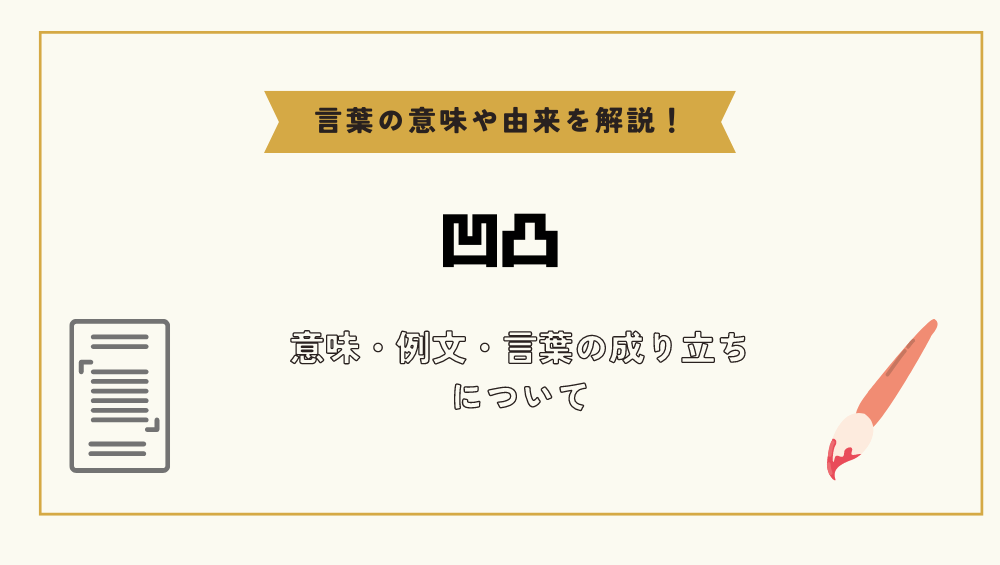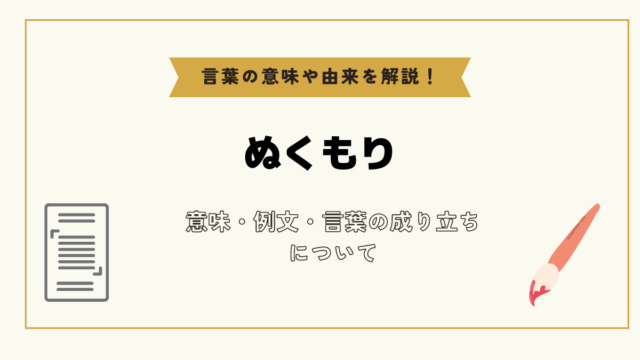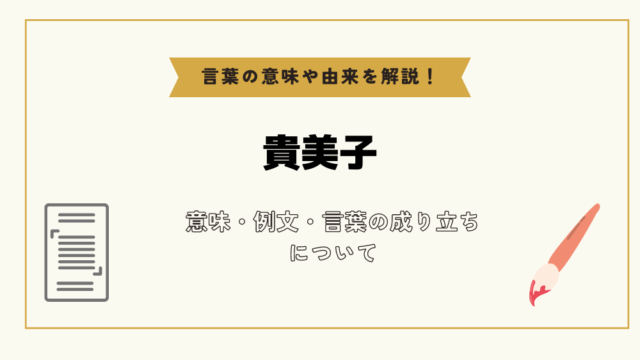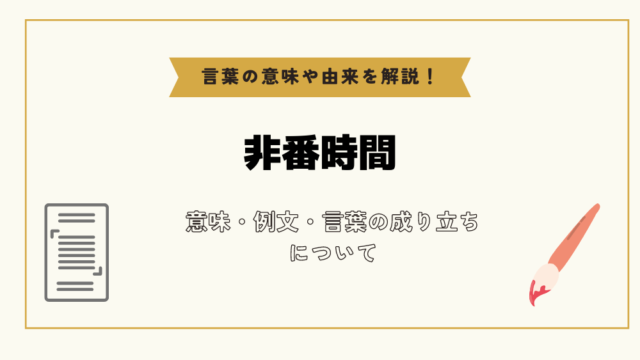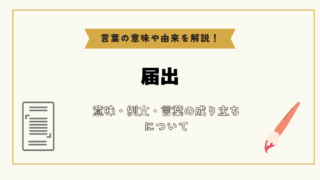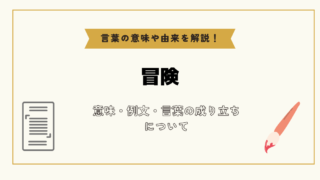Contents
「凹凸」という言葉の意味を解説!
凹凸(おうとつ)という言葉は、物の表面にできた凹みと凸部分を指す言葉です。凹(へこみ)と凸(でこぼこ)の両方を含んでおり、お互いが対照的な存在として使われることが多いです。
「凹凸」という言葉の読み方はなんと読む?
「凹凸」という言葉は、「おうとつ」と読みます。漢字の「凹」と「凸」はそれぞれ単独で読むことは少なく、この言葉で使われることが一般的です。
「凹凸」という言葉の使い方や例文を解説!
「凹凸」という言葉は、主に物の形状や表面の状態を表現する際に使われます。例えば、「この壁には凹凸がある」と言うことで、壁の表面が凹凸していることを指しています。また、「凹凸のある道を歩くと足がすくむ」といった表現も使われます。
「凹凸」という言葉の成り立ちや由来について解説
「凹凸」という言葉は、漢字の「凹」と「凸」を組み合わせてできています。この言葉が初めて使われた時期や由来については特定されていませんが、物の形状を表現する際には、凹と凸の対比がしっくりとくるため、自然に使われるようになったのではないかと考えられています。
「凹凸」という言葉の歴史
「凹凸」という言葉は、日本語の古典や文学作品などで度々使用されてきました。古代の歌や和歌でも、自然や景観の描写において、凹凸のある風景が詠まれています。また、近代以降の文学作品や詩においても、凹凸を通じて物事の美しさや奥深さを表現する詩句が見られます。
「凹凸」という言葉についてまとめ
「凹凸」という言葉は、物の形状や表面の状態を表現する際に使われる言葉です。凹と凸の二つの要素が対照的に組み合わさることで、物の一面的な平坦さを打破し、視覚的な魅力や奥行きを生み出します。古今東西の文学作品や詩においても頻繁に使われており、日本語の表現力の一つとして重要な位置を占めています。