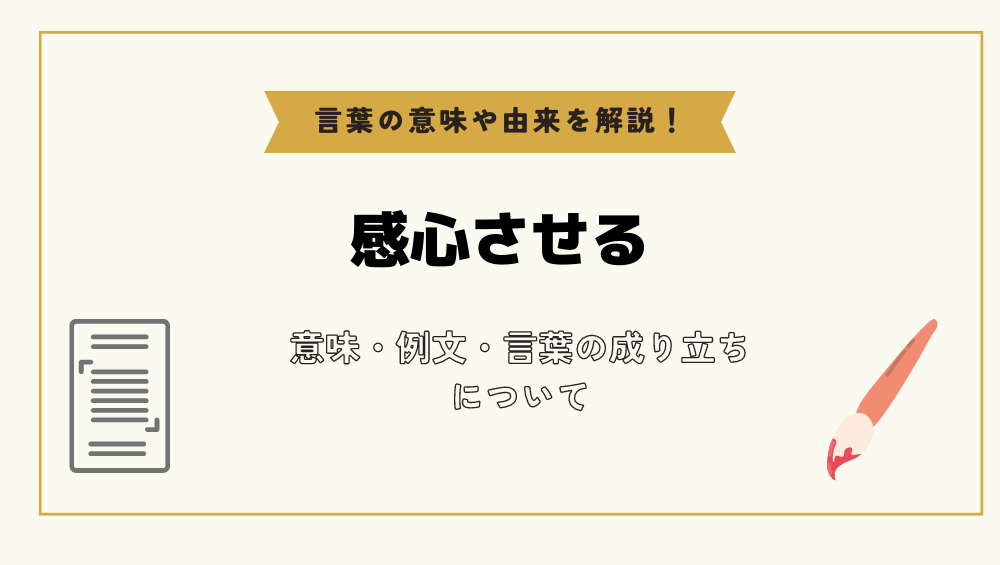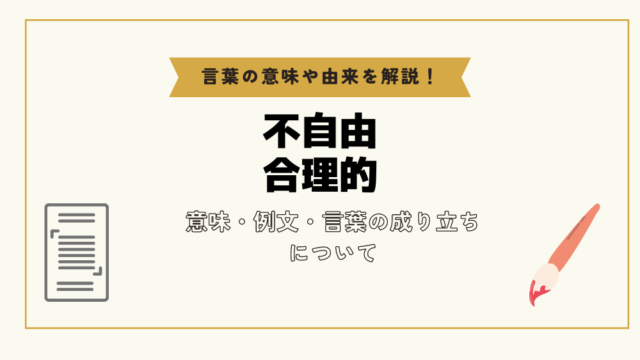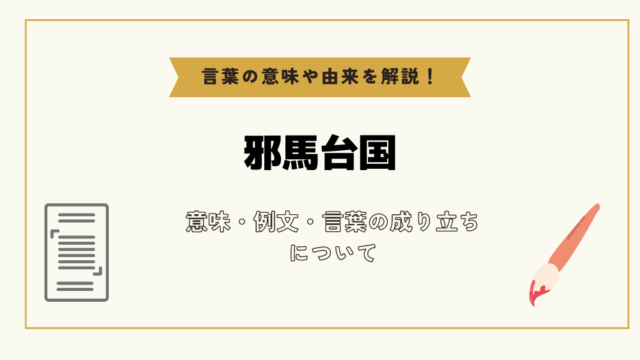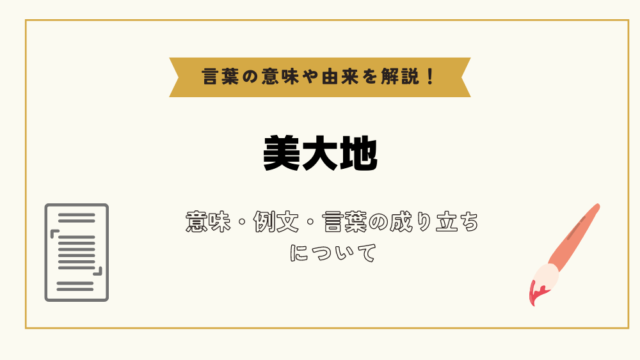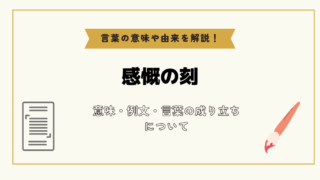Contents
「感心させる」という言葉の意味を解説!
「感心させる」という言葉は、人々の心を動かし、印象付けることを意味します。
何かに対して感心させられるとは、その何かが素晴らしいと感じることであり、驚きや感動を与えることができる能力や行動です。
感心させることは、相手に強い印象を与えるだけでなく、その人や物事に対して一層の興味や関心を抱かせることができるでしょう。
「感心させる」の読み方はなんと読む?
「感心させる」は、かんしんさせると読みます。
この言葉は、日本語の一般的な読み方に従っています。
まずは「かんしん」という読み方を覚え、その後に接頭辞「させる」と組み合わせて使うことで、「感心させる」という意味となります。
「感心させる」という言葉の使い方や例文を解説!
「感心させる」という言葉は、具体的な事例や行動を表現する際に使われることがあります。
例えば、友人が自分の作品を見せてくれた時に、「君の才能にはいつも感心させられるよ」と言うことができます。
また、プレゼンテーションやビジネスの場でも、「彼の熱意ある説明には感心させられた」と言うことができます。
感心させるは、相手の努力や能力を高く評価し、讃える表現としても使用できます。
「感心させる」という言葉の成り立ちや由来について解説
「感心させる」は、日本語の中でも比較的新しい言葉です。
成り立ちや由来についてはあまり詳しくはわかっていませんが、恐らく「感心」という言葉に「させる」という使役形式の接尾辞を付けたものと考えられます。
この言葉の出現は、人々が他者の才能や努力に感心を抱く機会が増えた結果だと言えるでしょう。
「感心させる」という言葉の歴史
「感心させる」という表現の歴史については、はっきりとはわかっていません。
しかし、現代の日本語において「感心させる」という言葉は広く使用されており、日常的な表現として浸透しています。
特に、芸術やビジネスなどの分野で、人々の高い評価を得るために使われることが多いです。
「感心させる」という言葉についてまとめ
「感心させる」という言葉は、人々の心を揺さぶり、強い印象を与える能力を持った表現です。
何かに感心させられることは、その人や物事に対して一層の興味や関心を抱かせることができます。
この言葉は、人々が他者の才能や努力を高く評価し、讃える際にも使用されます。
日本語の中でも比較的新しい言葉であり、現代の日本語においては広く浸透している表現です。