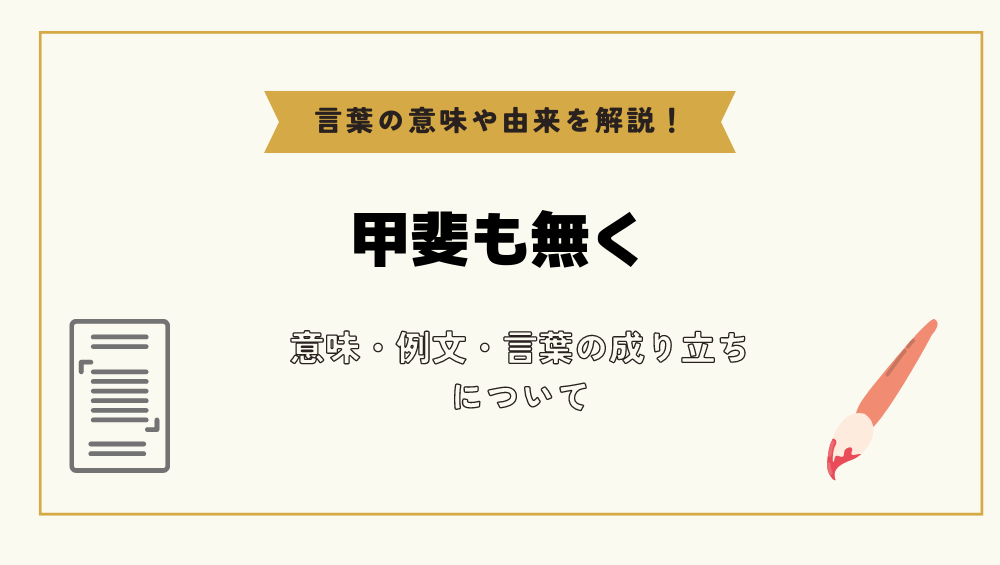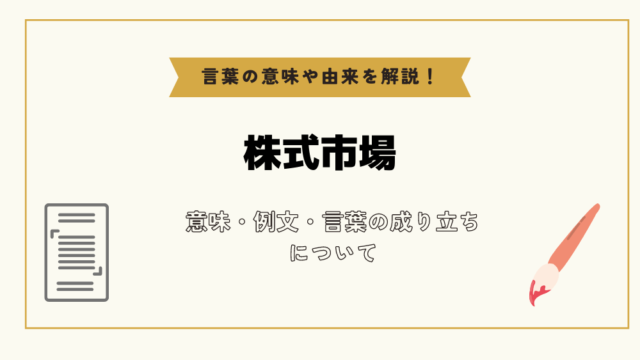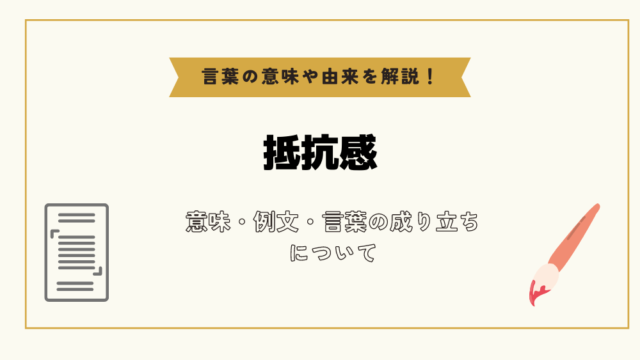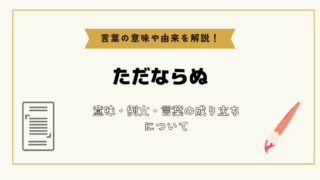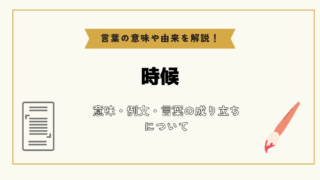Contents
「甲斐も無く」という言葉の意味を解説!
「甲斐も無く」という言葉は、何かをすることに対して、努力や成果が全く意味を持たない、無駄だと感じる様子を表現する言葉です。
つまり、時間やエネルギーを無駄に費やしてしまうことや、努力の甲斐がないと感じる状況を指すことが多いです。
例えば、ある目標に向かって頑張ったものの、結果が芳しくなく挫折してしまった場合に使われることがあります。
また、誰かに頼まれて助力をしても、お互いの努力が報われずに、甲斐も無く終わってしまうこともあります。
「甲斐も無く」の読み方はなんと読む?
「甲斐も無く」は、「かいもなく」と読みます。
読み方は特に難しくなく、一般的な日本語の発音で表現することができます。
「甲斐も無く」という言葉の使い方や例文を解説!
「甲斐も無く」という言葉は、主に否定的な文脈で使用されます。
例えば、「一生懸命勉強しても結果が出ないと感じて、甲斐も無くなってしまった」というように使われます。
また、「頑張っても報われないと感じて、努力が甲斐も無くなってしまった」という風にも使えます。
あるいは「友人にアドバイスしてあげたのに、それが甲斐も無く、結局失敗してしまった」というようにも使うことができます。
「甲斐も無く」という言葉の成り立ちや由来について解説
「甲斐も無く」という言葉の成り立ちは、古代の武士の言葉に由来しています。
「甲斐」とは鎧や武具を意味し、「甲斐がある」とは戦果や努力を意味します。
一方で、「無く」とはない、存在しないという意味です。
この言葉は、武士たちが戦の場で果敢に戦っても成果が出なかったり、優れた戦術を実行してもうまくいかなかったりする状況に直面した時に使用されたのが始まりです。
このような経験から、「甲斐も無く」という言葉が生まれたとされています。
「甲斐も無く」という言葉の歴史
「甲斐も無く」という言葉は、古くは平安時代から使われてきたとされています。
特に、武士の存在が重要視された中世の時代によく使用されるようになりました。
時が経ち、江戸時代になると、一般の人々にも広まりました。
江戸時代の文学や諺にもよく登場し、その後も現代に至るまで使われ続けています。
「甲斐も無く」という言葉についてまとめ
「甲斐も無く」という言葉は、努力や成果が無駄に感じられる状況を表現する言葉です。
これを否定的な文脈で使うことが多く、一生懸命頑張っても報われないと感じたり、努力が無駄に終わってしまったりする場合に使われることがあります。
この言葉は古代の武士の言葉に由来しており、特に中世から広まってきました。
今でも使われ続けており、日本語の豊かな表現力を示す一つの例といえます。