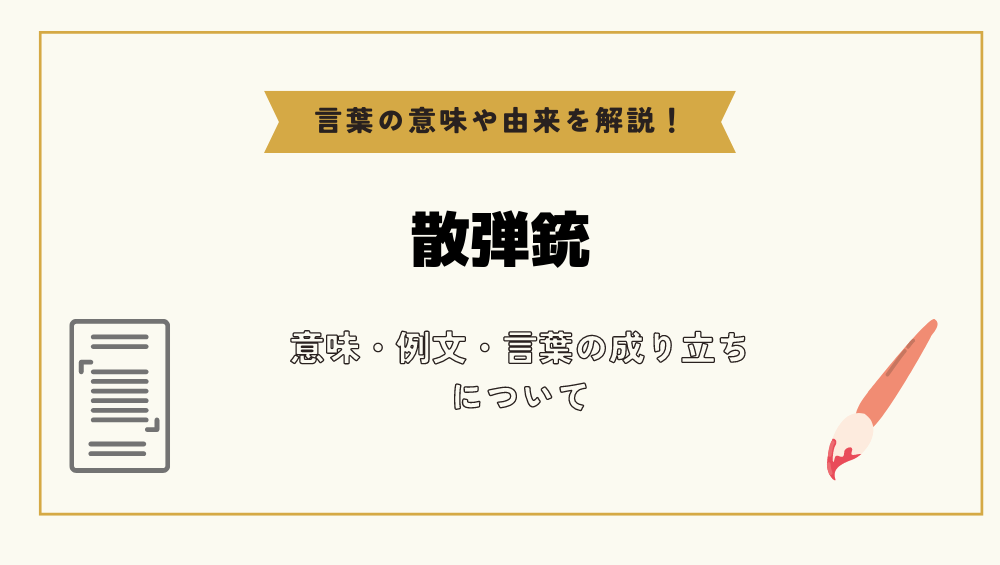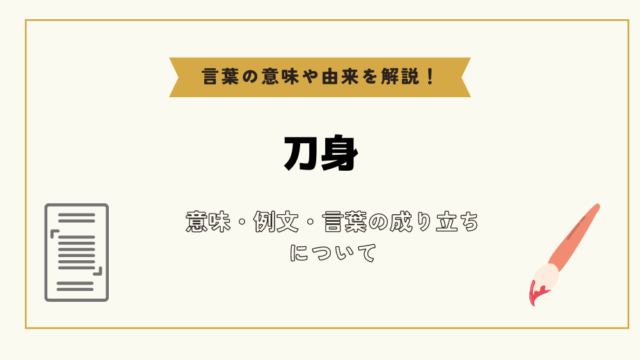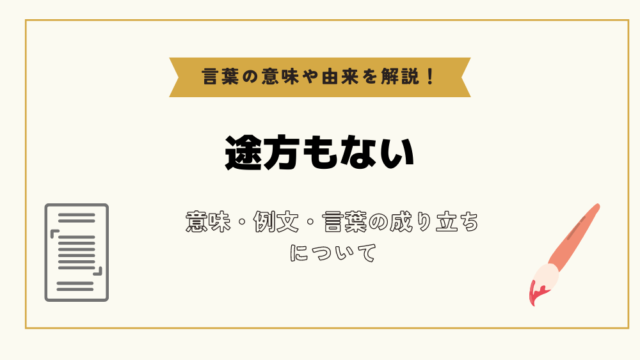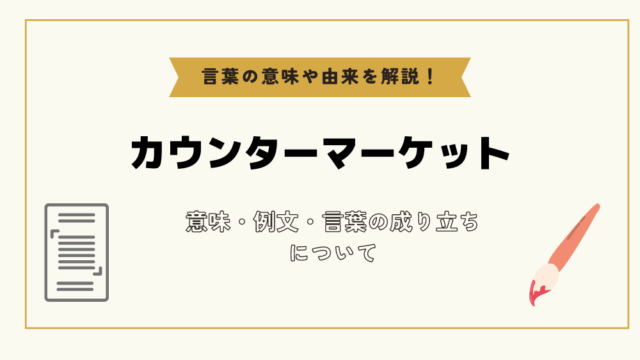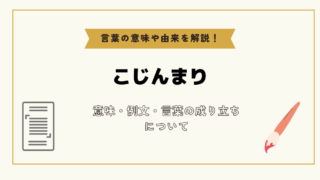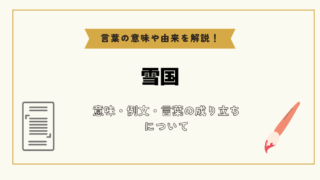Contents
「散弾銃」という言葉の意味を解説!
散弾銃とは、銃の一種であり、散弾(さんだん)と呼ばれる多数の小さな球を発射することができます。
散弾は、弾丸が広範囲にばらまかれるため、一度の射撃で広い範囲をカバーすることが可能です。
主に狩猟や自衛、競技などの目的で使用されます。
散弾銃はその特性から、近距離での戦闘や鳥獣の狩猟に効果を発揮します。
また、広範囲にばらまかれる弾丸が相手に与える威力も大きく、一発で多くの敵に対してダメージを与えることができます。
「散弾銃」という言葉の読み方はなんと読む?
「散弾銃」は、「さんだんじゅう」と読みます。
散弾は「さんだん」という言葉で、銃は「じゅう」という言葉で表されます。
「さんだんじゅう」という言葉は、散弾銃の特徴的な名称です。
「散弾銃」という言葉の使い方や例文を解説!
「散弾銃」は、次のような文脈で使われることがあります。
例文1:彼は狩猟のために散弾銃を持っています。
例文2:散弾銃は近距離での戦闘において威力を発揮します。
このように、「散弾銃」は狩猟や戦闘の文脈で使用されることが一般的です。
その特性から、広範囲にばらまかれる弾丸の特徴や威力を表現する際にも使用されます。
「散弾銃」という言葉の成り立ちや由来について解説
「散弾銃」という言葉は、散弾を発射する特性を持つ銃の名称です。
散弾は、多数の小さな球を含んだ弾薬であり、銃から発射される際にばらまかれます。
その特性から、散弾銃という名称が生まれました。
散弾銃は、古くから狩猟や戦闘に使用されてきました。
鳥獣の狩猟においては、広範囲に弾丸をばらまくことで獲物を確実に仕留めることができます。
また、戦闘でも近距離での攻撃に優れ、敵に強力なダメージを与えることができます。
「散弾銃」という言葉の歴史
散弾銃の起源は古く、16世紀頃には既に存在していました。
当初は、鳥獣の狩猟に使用される道具として発展しましたが、戦争の時代には戦闘での使用も広まりました。
散弾銃は長い歴史の中で様々な改良や発展を遂げ、現代のような高性能な武器へと進化しました。
現在では、狩猟やスポーツ射撃、自衛などの目的で広く使用されています。
「散弾銃」という言葉についてまとめ
散弾銃は、散弾と呼ばれる多数の小さな球を発射する銃です。
広い範囲をカバーすることができるため、近距離での戦闘や鳥獣の狩猟に効果を発揮します。
その特性を生かした使い方や例文も紹介しました。
また、散弾銃の起源や歴史についても触れました。
散弾銃は、その特徴から狩猟や戦闘などの分野で重要な存在です。
その威力や使用方法を学ぶことで、より安全に、効果的に活用することができるでしょう。