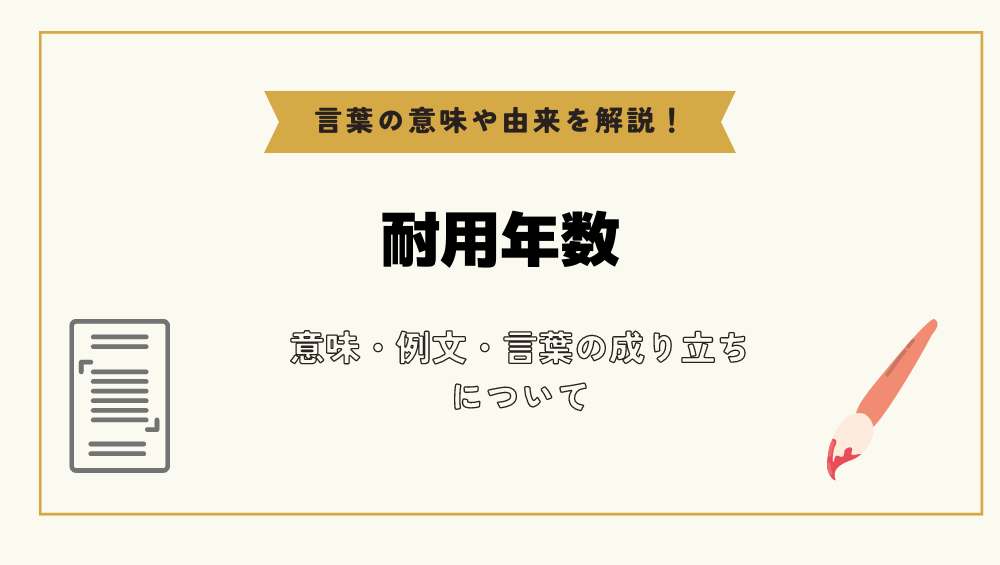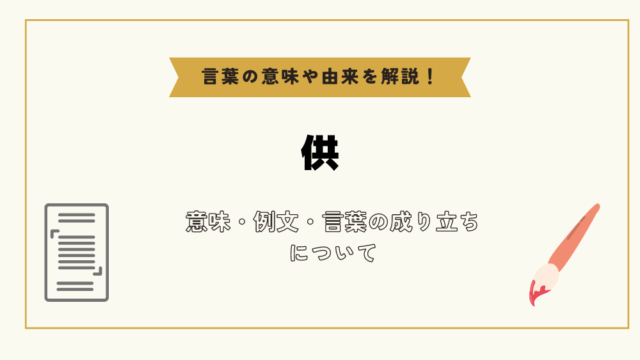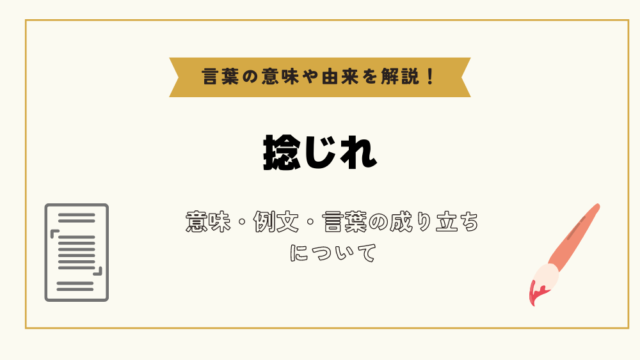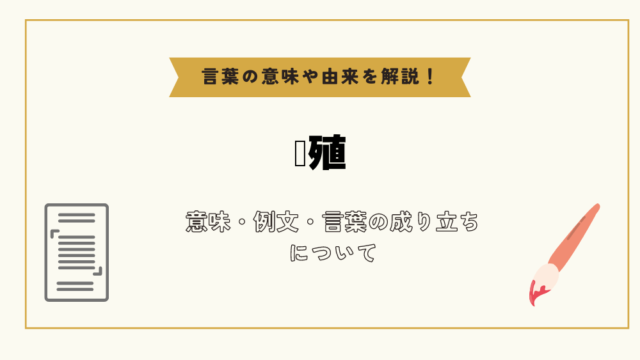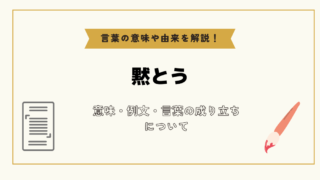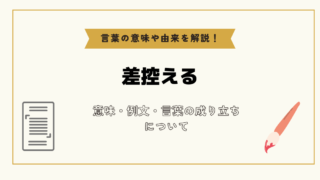Contents
「耐用年数」という言葉の意味を解説!
「耐用年数」とは、ある製品や設備が正常に使用できる期間のことを指します。
つまり、その製品や設備が劣化することなく機能し続けることができる年数のことを指すのです。
例えば、家電製品や自動車などは、一般的には耐用年数が決まっており、その期間内で維持修理がされれば、安心して使用することができるのです。
「耐用年数」という言葉の読み方はなんと読む?
「耐用年数」は、「たいようねんすう」と読みます。
日本語の読み方ですので、言葉自体にはあまり難しい読み方はありません。
ただし、漢字の意味や使い方に注意が必要です。
正しく理解し、適切な場面で使用できるようにしましょう。
「耐用年数」という言葉の使い方や例文を解説!
「耐用年数」は、さまざまな場面で使われる言葉です。
例えば、ある商品の耐用年数が5年とされている場合には、その商品は5年間は問題なく使用できるということを意味します。
また、産業用の設備や建造物においても、耐用年数は重要な要素となります。
耐用年数が長いほど、経済的にも効果的な選択と言えるのです。
「耐用年数」という言葉の成り立ちや由来について解説
「耐用年数」という言葉は、耐用(たいよう)という言葉と年数(ねんすう)という言葉が組み合わさってできたものです。
耐用は、何かに耐えることができるという意味を持ち、年数は一定の期間を意味します。
つまり、「耐えることができる年数」という意味になります。
製品や設備がどれくらいの期間使用できるかを表す言葉として、一般的に使われるようになりました。
「耐用年数」という言葉の歴史
「耐用年数」という言葉が初めて使われ始めたのは、明治時代の終わりごろのことです。
当時、産業が急速に発展する中で、製品の品質や耐久性についての議論が盛んになりました。
そこで、製品や設備の「耐用年数」が重要な指標とされるようになり、その後も浸透していきました。
現代では、多くの業界で耐用年数が規定され、消費者にとっても重要な情報となっています。
「耐用年数」という言葉についてまとめ
「耐用年数」とは、製品や設備の正常な使用期間を指す言葉です。
日本語の読み方は「たいようねんすう」であり、例文や使い方を理解することが重要です。
また、由来や歴史についても知ることで、さらに深い理解が可能です。
製品を選ぶ際やメンテナンスをする際には、耐用年数を考慮することで、経済的で安心な選択ができるのです。