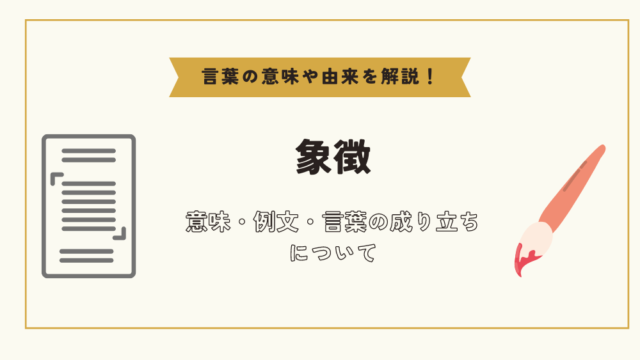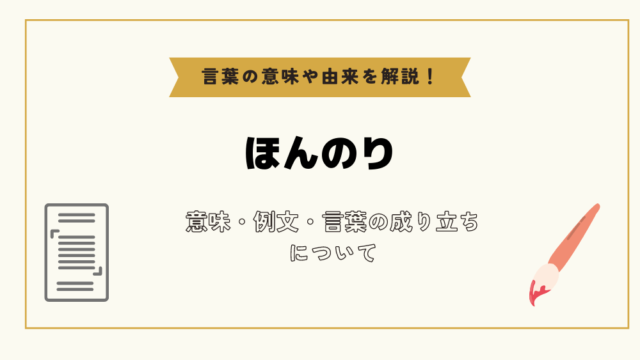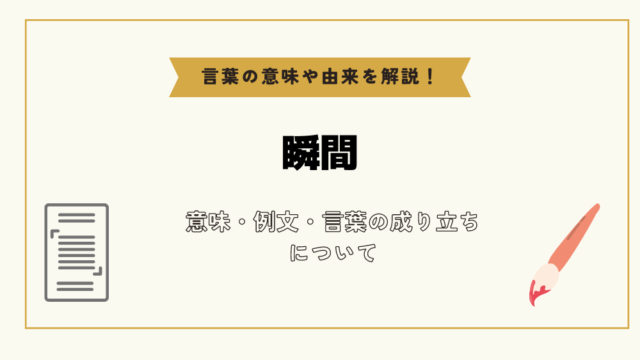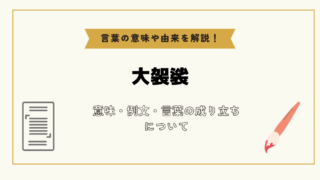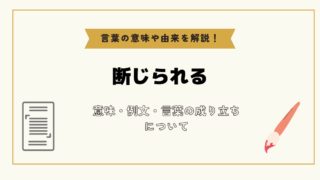Contents
「申し」という言葉の意味を解説!
申し(もうし)という言葉は、日本語の敬語や謙譲語として使われることがあります。この言葉は「言う」「述べる」という意味を持っています。「申し上げる」という表現でよく知られており、相手に対して丁寧に意見や要望を伝える際に使用されることがあります。
「申し」の読み方はなんと読む?
「申し」は、「もうし」と読みます。この読み方は、ほかの言葉と組み合わせて使われることが多いです。「申し出る(もうしでる)」「申し訳ない(もうしわけない)」などが代表的な例です。
「申し」という言葉の使い方や例文を解説!
「申し」という言葉は、相手に対して敬意を表すために使われることが多いです。例えば、上司に対して「申し上げます」と言えば、丁寧な表現になります。「お申し込み」や「申し込む」という表現も一般的であり、謙虚な態度を示すことができます。
「申し」という言葉の成り立ちや由来について解説
「申し」の由来は、古代中国の十二支という暦のシステムにあります。申(さる)は、その中の一つの動物の名前です。中国では申(さる)は長寿と福をもたらすとされており、日本ではこの申の文字が「申し」として使われるようになりました。
「申し」という言葉の歴史
「申し」という言葉の歴史は古く、奈良時代から使用されていました。当時は、主に皇族や貴族の間で使われており、敬意を表す言葉として使われていました。現代でも、特に公式な場面や目上の方に対して使用されることが多くあります。
「申し」という言葉についてまとめ
「申し」という言葉は、敬意を示すために使われる日本語の言葉です。相手に対して謙虚な態度を表すために、「申し上げます」「申し込む」などの表現がよく使われます。その由来は古代中国の十二支にあり、古くから日本で使用されてきました。