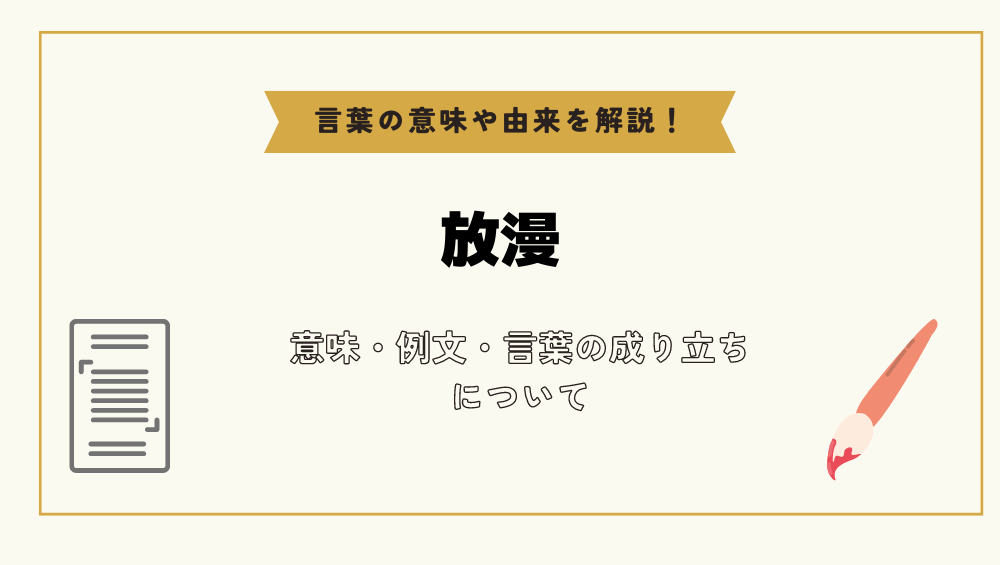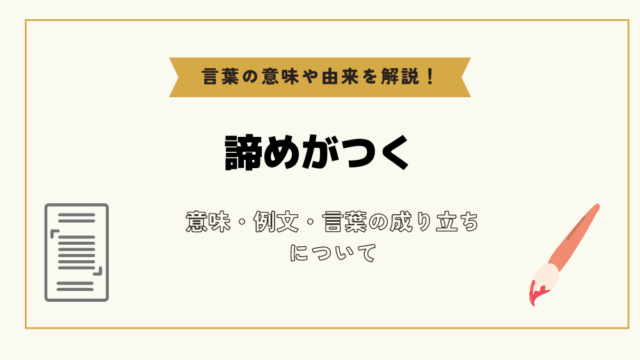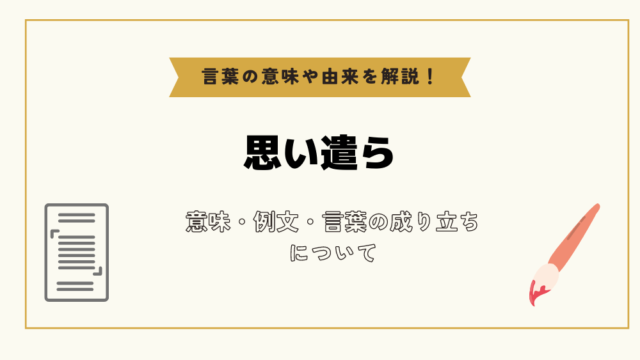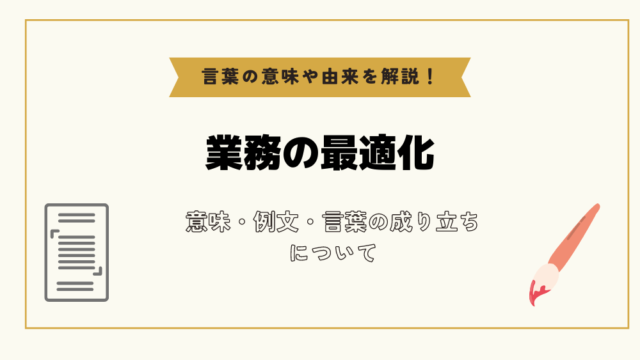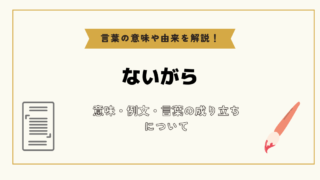Contents
「放漫」という言葉の意味を解説!
「放漫」という言葉は、のんびりとした態度や無計画な行動を指す言葉です。
何かに縛られずに自由に振る舞う様子を表現する際に使われることが多いです。
例えば、予定が詰まっているのに計画がなくゆるいスケジュール管理をしている人を「放漫な人」と言います。
「放漫」の読み方はなんと読む?
「放漫」の読み方は、「ほうまん」となります。
音読みとして「ほう」は「自由な」という意味を持ち、「まん」は「豊かな」という意味を持っています。
この二つの意味が合わさって、無責任で自由な様子を表す形容詞として使われるようになりました。
「放漫」という言葉の使い方や例文を解説!
「放漫」という言葉は、特にマイナスなイメージを持って使われることが多いです。
例えば、仕事や勉強において放漫な態度を持つことは、結果的に成果が上がらず、自身の能力や信頼を損なう可能性があります。
また、「放漫な生活を送る」という表現では、無計画でルーズな生活態度を指しています。
例文1:彼は放漫な態度でプロジェクトに取り組んでおり、周囲からの信頼を失ってしまいました。
例文2:放漫な計画を立てたため、旅行中に予約が取れなくなってしまいました。
「放漫」という言葉の成り立ちや由来について解説
「放漫」の語源は、もともとは中国の古典『論語』に由来しています。
そこで「放漫」という言葉は、「心配せずに自然体で振る舞うこと」という意味を持ちました。
日本へは漢詩や儒家の思想とともに伝わり、現在の意味に変化していきました。
「放漫」という言葉の歴史
「放漫」という言葉は、江戸時代から使われている古い言葉です。
当時、武士や学者たちが経済的な安定を得て余裕が生まれると、無駄遣いや遊興に走ることがあったため、それに対する批判的な言葉として使われました。
昔から人々の行動や態度を表す言葉として使われてきました。
「放漫」という言葉についてまとめ
「放漫」という言葉は、無計画で自由な様子を表現するために使われる言葉です。
特にマイナスなニュアンスを持ち、無責任な態度やルーズな行動を指摘する際に使用されます。
語源や由来は中国の古典にさかのぼりますが、日本語として現代でも使われ続けています。